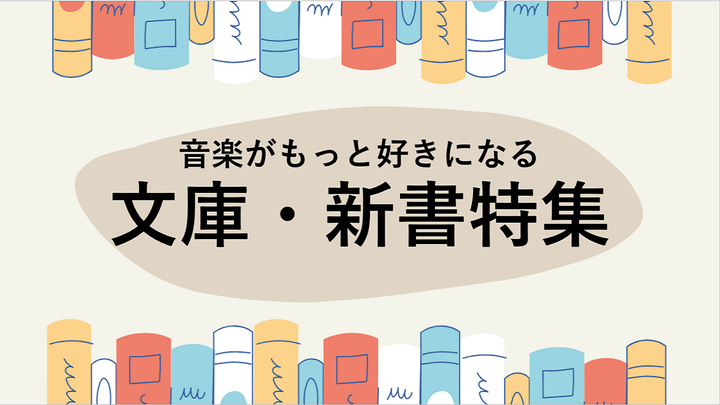音楽ライター・映画音楽評論家の小室敬幸氏が “今、読むべき1冊” を、音楽を愛するあなたにお届けします。第1回は、第35回ミュージック・ペンクラブ音楽賞(研究・評論部門)を受賞した沼野雄司著『現代音楽史――闘争しつづける芸術のゆくえ』(中央公論新社刊)です。
研究者ほどではないと思うが、音楽ライターという仕事柄、音楽に関する書籍に囲まれて日常を過ごしている。以前ならば頻繁に利用する書籍以外は当時勤務していた大学の附属図書館で借りていたのだが、コロナ禍になってからは図書館が長期にわたって閉まってしまうことも多く、全て自宅で完結するように資料を買い集めるように方向転換したからだ。昔は大型の書店に足繁く通っていたが、現在はAmazonを中心に、もっぱらインターネット通販頼りとなってしまった。それまで使ったことのなかったメルカリで絶版となった書籍を探すことも増えている。
蔵書が急激に増えて部屋を圧迫していったため、何の気なしに計算してみると2021年の1年間、Amazonだけで(音楽書以外も含めて)45万円ほど書籍を購入していた。他のWEBサイトで購入した本もあるし、他にもCDやDVD、Blu-rayなども多数購入しているので、働いて稼いだお金で(長期的な目線で)仕事に必要な資料を買い集めているような状況となっている。更には仕事の一環で献本も多数いただくため、積ん読は増える一方だ。
そんな有様なので一冊を通読する場合は流し読み、精読する場合は書物仕事に必要な部分だけを取り出して……という形の読書が普段は多くなってしまうのだが、久しぶりにメモしながら(約18000字)、一冊丸々をじっくりと楽しみながら読んだ本がある。それが今年3月に、第35回ミュージック・ペンクラブ音楽賞(研究・評論部門)を受賞した沼野雄司 著『現代音楽史――闘争しつづける芸術のゆくえ』だ。
発売は2021年1月。その直後に購入して流し読みはしていたのだが、今年4月16日に日本最大級の読書会コミュニティ「猫町倶楽部」で本書を課題本として扱うので、しっかりと時間をかけて読み直したのである。猫町倶楽部については次回以降の連載で触れることとなると思うので、ここではこの『現代音楽史』という本がいかに待望されたものであったかを語ってみたい。

音楽史で「現代音楽」はどのように扱われてきたか?
『現代音楽史』のあとがきは、次のように始まる。
現代音楽史を書こうとした動機はいくつかある。
まず類書がほとんどないこと。日本語で書かれた書物で二十一世紀までを含めて通観できるもの、それもある程度コンパクトなものが必要だと考えていた。実際、いまだに柴田南雄『現代音楽史』(1967初版)を参照する人もいると聞くので(確かに名著ではあるが)、いくらなんでも情報や音楽史観をアップデートしなくてはならない。
今一度、当たり前の事実を強調しておいた方がよいだろう。これは“2021年”に出版された書籍のあとがきである。類書の筆頭格に挙げられた書籍が半世紀以上前のものであることに改めて驚くしかない(ちなみに1967年といえば武満徹の代表作にして、音楽の教科書にも掲載された、いわば日本を代表する現代音楽作品《ノヴェンバー・ステップス》が作曲・初演された年である!)。
もちろん1967年以降に、類書が一切発売されなかったわけではない。そもそも現代音楽に特化せずとも、「西洋音楽史」と題された書籍のなかでも20世紀まで取り扱われることが一般的だ。日本で最も多くの音楽学者から支持されている音楽史であろうグラウト/パリスカ著『新 西洋音楽史』(音楽之友社, 1998〜2001/訳者まえがきに2007年追記あり)は、1996年に出版された原著“A History of Western Music”の改訂第5版を翻訳したもの。上・中・下巻あるうちの下巻の後半で20世紀音楽に頁を割いているのだが、ヨーロッパの作曲家を取り扱った項目ではW. ルトスワフスキ(1913〜94)の交響曲第3番(1983)で、アメリカの作曲家を取り扱った項目ではD. デル・トレディチ(1937〜 )の《ファイナル・アリス》(1975)で締めくくられている。つまり、1980年前後までしか歴史が綴られていないのだ。
この「1980年」という年代は、西洋音楽の歴史を記述しようとする時、ひとつの壁となっているように思われる。2020年8月に出版された金澤正剛『ヨーロッパ音楽の歴史』(音楽之友社)のあとがきでは「若干の例外はあるものの、ほぼ一九八〇年代までを書いたところで筆をとどめた。それ以後の出来事はいまだ「歴史」として判断できかねると感じたからである」と記されている。日本音楽学会の会長などを歴任した金澤氏が、何故このような判断をしたかといえば、この数十年のあいだに「現代音楽」についての認識がかなり変わってしまったからだとしている。多くの人々によって共有されるような認識が得られるまでは、歴史として記述されるべきではないという判断なのだろう。

そうした慎重派もいるなか、西洋音楽史を取り扱った書籍のなかではロングセラーといえるであろう『はじめての音楽史』(音楽之友社,初版1996/増補改訂版2009/決定版2017)では、増補改訂時に少し新しい音楽もフォローしている。ただし多くの紙面が割けるわけではないので、代表的な作曲家に加えて傾向を示すキーワードを示唆するところまでが関の山だ(加えて1996年の初版では、フィリップ・マヌリをスペクトル楽派として紹介する明らかな事実誤認が含まれていた。新しい音楽を紹介する際には、こうした間違いも起こりやすい)。なぜ、そのような傾向が生まれるに至ったのか。説明がなされているとしても音楽の歴史上での影響関係ばかり。ある程度以上、クラシック音楽・現代音楽に対する教養がなければ、その意味や意義は伝わらない上、そもそも外部からの興味をもたれづらいのも当然だ。
通史よりも掘り下げた解説が必要ならば、20世紀以降だけに絞った音楽史の書籍を手に取ることになるだろう。だがテーマを特定の国やスタイルに絞った書籍に比べると、(今回のテーマである沼野雄司 著『現代音楽史』が出るまでは)自信を持って万人に薦められる書籍が挙げづらかった。21世紀以降に出版された、日本語で読めるものに限ってみると、ポピュラー音楽のリスナー視点から歴史を描き直した松村正人『前衛音楽入門』(ele-king books, 2019)は視点も内容も偏りがありすぎる。
美術の専門家とは思えないほど広範な音楽への知識と愛が感じられる宮下誠『20世紀音楽 クラシックの運命』(光文社,2006)は作曲家と作品が見出しになっていて、抜粋しても読みやすいのだがその分、ディスクガイド的な性格が強く、時系列の流れは掴みづらいし、掘り下げは物足りない。
西洋音楽の専門家によるものとしては、大久保賢『黄昏の調べ 現代音楽の行方』(春秋社,2016)があるが、この本の読みどころは著者が専門とする「演奏行為」絡みの部分であって、何章かに分けて叙述される歴史については、これまで様々なところで語られてきた見解が主で、現代音楽に対してある程度の知識を既に持っている読み手からすると正直面白みに欠ける。
読み物として抜群に面白く、多くの示唆にも富んでいるのは、アレックス・ロス著/柿沼敏江 訳『20世紀を語る音楽 The Rest Is Noise – Listening to the Twentieth Century』(みすず書房,2010/原著2007)なのだが、上下巻で600頁ほどと非常に長いのと、純然たる音楽史ではないため現代音楽を体系的に理解するという目的には向いていない。
……といったような状況であったから、現代音楽の研究者として今の日本で第一人者の地位にある沼野雄司氏による著作――しかもコンパクトな新書!――がいかに待望のものであったのか、ご理解いただけるだろう。

音楽ファン以外が読むべきである理由!
しかし、書き手の立場がいかにテーマに相応しいものであろうと、実際の評価は書籍の内容で判断すべきなのは言うまでもない。最後に、沼野雄司 著『現代音楽史』の何が優れているのか、いくつかポイントに分けて解説していく。まずは再び、本書のあとがきから引用しよう。
現代音楽史を書こうとした動機はいくつかある。
〔中略〕文学、美術や映画など、現代の文化に関心のある人ならば、ストラヴィンスキーやケージについては多少の知識があるに違いない。しかし、その後の世代に関してはどうだろうか。
クンデラやゴダールには興味があっても、リゲティやカーゲルの作品を聴いたことがない、アイ・ウェイウェイ(艾未未)や村上隆の名は知っていても、彼らと同世代の作曲家の名はまったく思い浮かばないという人は、かなり多いのではないだろうか。
現代音楽が他分野から興味をもたれづらくなったという問題意識は、沼野氏以外にも少なくない人々がこれまで口にしてきたが、実際にこの視点を一冊まるごと徹底している例は極めて珍しいと言っていいだろう。例えば、第1章では第一次世界大戦を境に変化していった社会の価値観を、ジャン・ルノワール監督の映画『大いなる幻影』(1937)のいち場面を例にして見事に読者に伝えてくれる。映画史に興味がある方であれば、観たことがなくても作品名ぐらいは知っているはずの作品である上、ジャン・ルノワールは誰もが知るあの印象派の画家ピエール=オーギュスト・ルノワールの次男であることを入口にして、映画に興味がない人にも例として挙げる意味が分かるように説明してしまうのだ。
こうした手法による見事な解説のなかでも、とびきり優れていると筆者が感じたのは第4章に登場する、モダニズム建築を例にしてモダニズムの本質を解きほぐし、そこから音楽に適応していく流れだ。21世紀を生きる我々のうち、少なくない人々がカッコいいと感じているであろうモダニズム建築――コンクリート打ちっぱなしなど、装飾が少なく、合理性から生まれたデザイン――における機能美は、「セリー音楽」に共通しているのだという指摘は、(総音列技法を含む)セリー音楽がどのようなものであるのか、音楽を専門としない人々にむけた最善の解説であるように思える。

ホラーやSF映画などで使われてきたことを除けば、我々の日常と何の関係もなさそうな現代音楽が、実は既に親しんでいる何らかの文化と驚くほど多くの共通性をもっていることを様々な角度から詳らかにしてくれる。それが沼野雄司『現代音楽史』、最大の魅力だ。そう考えてみると、本書を読むべきはクラシック音楽・現代音楽のファンというよりも、様々な西洋芸術(美術、文学、映画、建築など)に対する興味や知識はあるのにもかかわらず、現代音楽に興味をもてない人々であるはず。クラシック音楽や現代音楽に興味がなくとも、西洋文化全般に強い興味をもっているのならば、是非とも読んでいただきたい一冊である。
もうちょっと専門的な目線でみていくと、第2〜3章にかけて「新古典主義」という言葉を再考して、広い視野で捉え直したり、第4〜5章ではこれまで多様な作曲技法で語られてきた戦後の音楽を「数」「音響」という切り口で鮮やかに整理し直したりする見事さは痛快極まりない。第6章以降では、沼野氏が博論でテーマにしていた「前衛の終焉と現代音楽のゆくえ」という視点が存分に活かされていくのも本書の読みどころなのだが、こうした話はどうしても西洋音楽に対するある程度以上の教養を要求することになってしまう。だから、ここではこれ以上語らない。まずは、騙されたと思って沼野雄司『現代音楽史』を読み、音だけでは正直わけのわからぬ、現代音楽なるものの不思議な面白さに触れていただきたい。
(本記事は、2022年6月に執筆した記事を再掲載しています。)
Text:小室敬幸
<今回の紹介書籍>
『現代音楽史――闘争しつづける芸術のゆくえ』
(中央公論新社刊・中公新書)
沼野雄司 著
初版刊行日:2021年1月19日
判型:新書判
定価:990円(税込)
ISBN:978-4-12-102630-9
https://www.chuko.co.jp/shinsho/2021/01/102630.html
プロフィール

小室 敬幸
音楽ライター/大学教員/ラジオDJ
東京音楽大学と大学院で作曲と音楽学を学ぶ(研究テーマはマイルス・デイヴィス)。現在は音楽ライターとして曲目解説(都響、N響、新日本フィル等)や、アーティストのインタビュー記事(レコード芸術、intoxicate等)を執筆する他、和洋女子大学で非常勤講師、東京音楽大学 ACT Projectのアドバイザー、インターネットラジオOTTAVAでラジオDJ(月曜18時から4時間生放送)、カルチャースクールの講師などを務めている。
X(旧Twitter):https://x.com/TakayukiKomuro
この記事を読んだ方におすすめの特集