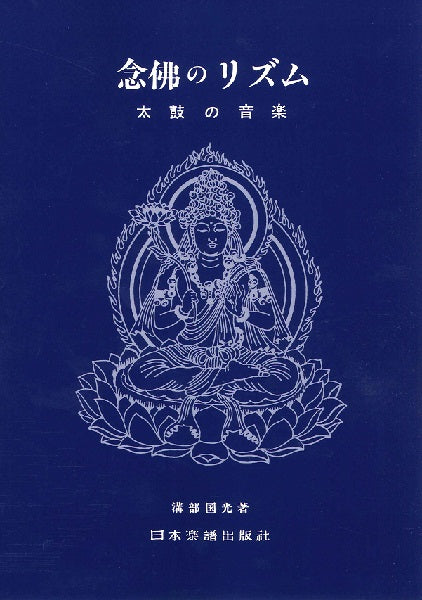日本には数え切れないほど多くの祭り、民俗芸能が存在する。しかし、さまざまな要因から、その存続がいま危ぶまれている。生活様式の変化、少子高齢化、娯楽の多様化、近年ではコロナ禍も祭りの継承に大きな打撃を与えた。不可逆ともいえるこの衰退の流れの中で、ある祭りは歴史に幕を下ろし、ある祭りは継続の道を模索し、またある祭りはこの機に数十年ぶりの復活を遂げた。
なぜ人々はそれでも祭りを必要とするのか。祭りのある場に出向き、土地の歴史を紐解き、地域の人々の声に耳を傾けることで、祭りの意味を明らかにしたいと思った。
わずか350名の町民で支えている火祭の困難
祭りの担い手不足という継承課題を支援するため、石川県は2025(令和7)年にボランティア制度「祭りお助け隊」を開始した。前編では県の担当者に取材し、その意義を確認するとともに、実際に支援先となった「向田(こうだ)の火祭」(石川県七尾市・能登島)に参加して、ボランティア活動の様子と祭りの現場をレポートした。
石川県能登島向田
では、祭り主催者には「祭りお助け隊」という取り組みがどう受け止められたのか。後編では、ボランティアの取りまとめ役を務めた火祭実行委員・高橋俊朗さんにインタビュー。祭りお助け隊を導入した経緯について話を伺った。

火祭り実行委員 高橋俊朗さん
まず現在、向田の火祭が抱える継承課題について聞いてみた。
「七尾市には四大祭りと呼ばれる代表的な祭りが四つあります。青柏祭(せいはくさい)、石崎奉燈祭(いっさきほうとうまつり)、お熊甲祭(おくまかぶとまつり)、そして向田の火祭です。向田の火祭は、ほかの三つが複数の町会の連合で行われるのに対し、向田という一つの町だけで執り行われるのが特徴です。あの規模の祭りを、人口350人ほどの町民だけで支えなければいけない、そこが祭りを執行するうえでの難しい点ですね」

デカヤマと呼ばれる巨大な曳山が有名な「青柏祭」
七尾市の公表している人口集計表を見ると、2014(平成26)年1月の能登島向田町の人口は515人、2024(令和6)年1月は398人と、10年で20%近くもの人口減少が起きていることがわかる。この状況で同じような規模の祭りを維持しようとすると、町民一人一人の負担も当然に大きくなってくる。
「例えば、柱松明に使う柴は、住民が総出で集めます。各世帯のノルマは7束です。自分で用意できない家は、近所や親戚に頼んで用意してもらいます。松明起こしなどの重労働も住民が力を合わせて行いますが、どうしても人手を出せない場合は、出不足金を納めれば免除される仕組みもあります。ただ、近年は一人暮らしの高齢者が増え、労働力も資金も負担が難しい世帯が目立ってきています」
また、課題は労働力だけにとどまらない。たとえば、オオナワづくりに欠かせない稲わらの確保も大きな問題だ。現在、火祭で使う稲わらを提供しているのは高橋さんの父である。良質な稲わらを得るため、コンバインではなく手押しのバインダーで刈り取り、さらに「稲架(はさ)掛け」と呼ばれる昔ながらの方法で天日干しを行い、その後に脱穀。こうした手間のかかる工程を経て、稲わらが準備されている。誰でも気軽に引き受けられる仕事ではないからこそ、持続的な稲わら確保の方法も検討していく必要があるだろう。

稲わらの調達を引き受ける高橋さんの父。しかも稲わらは無償での提供だという
「人がいないから祭りはできない」は成り立たない
こういった課題を抱える中で、向田の火祭は震災の起こった2024年、祭りを続けるか否か、大きな岐路に立たされた。高橋さんの話によると、向田は他の地域と比べると比較的地震による被害は少なかったそうだが、やはり「いまは祭りをやっている場合ではない」という声も出てくるようになる。しかし高橋さんの中では、すでにコロナ禍で2年の休止を経験していることもあり、このタイミングでまた休止をしてしまっては、今後の再開はいっそう難しくなるのではという危惧があった。
「地震が起きた2ヵ月後、議決権を持っている51名の住民が集まって、火祭をするか否かという決をとったんです。結果、やりたいという人が27名、やるべきでないという人が24名。まさに紙一重で祭りの実施が決まりました」
この時、開催の方向を決定づけたのは、若い世代の意思だ。
「高校卒業から40歳までの男性が集まった“向田壮年団”という組織があるのですが、彼らが実質的な祭りの実行部隊になるんですね。そんな壮年団の士気が高く、“祭りをやりたい”という声が大きかったんです。ちょうど子育て世代でもあるので、やはり自分の子どもに祭りを見せたいという思いも強くて。壮年団がまとまれば祭りはできるので、彼らをサポートする壮年部(壮年団を卒業した41歳以上の男性が所属する組織)も、そこまで言うのなら我々も手伝おうか、ということになったんです」

柱松明づくりに精を出す壮年団の姿
現在、47歳の高橋さんも壮年部の一員であり、また町会の役員を務めるほか、火祭に関する「祭礼委員」にも関わり、祭りや地域を盛り上げるための、さまざまな取り組みを推進している。
具体策の一つとして、2024年から「応援金(義援金)」の募集を始めた。これまでは、地区内で商売を営む人々に壮年団が寄付をお願いして資金を賄ってきた。だが、地震の影響で商売が立ちゆかなくなり、寄付の確保が難しくなった。そこで、祭りの公式サイトなどを通じて広く応援金を呼びかける方針に切り替えたのである。

祭りの公式サイトに掲載された応援金募集の呼びかけ
また「地域の結束を強め、地縁というリソースを最大限に活用する」という目的で、2025年初頭から電子回覧板サービス「結ネット」を導入した。地域の各種情報をアプリで共有できる機能があり、祭りなどの行事案内もここで発信している。
「電子回覧板のいいところは、紙の回覧板ですと基本的にその家の世帯主しか見ることがないんですけど、アプリで見られるようになれば、子どもたちも情報をチェックできるようになるんですよね。さらには、能登島から離れて住んでいる人たちにも、地域の情報が届くようになる。それで、火祭の日は地元に帰ろうかなとか、現地には行けないけど応援金は出そうかなとか思ってもらえるかもしれないですし、地域行事に関わるきっかけにもつながるんです」
導入には他の役員から反対もあったが、説得を重ねて進めた結果、現在は約100世帯中80世帯が電子回覧板を受け入れるまで、浸透しているという。
そして、今回の祭りお助け隊の取り組みも、やはり高橋さんが中心となって話を進めている。
「今年の4月くらいから、(県職員の)若林さん(連載第15回参照)から祭りお助け隊の話は聞いていて、役員会で“こういう話があるんですけど、どうしますか?”と提案してみたんです。最初は祭りのボランティアというものにみんなアレルギーがあるんじゃないか、これはうちらの祭りだという意見が出るかなと思ったんですが、意外とすんなり話が通って、じゃあ誰が(ボランティアの)面倒を見るんだとなった時に、やるんだったら僕しかいないだろうということで、引き受けました」
では実際に、祭りお助け隊を受け入れて、どういう感想を持ったのだろうか。
「良かったと思います。みなさん能動的に動いて、本当に一生懸命やっていただきました。今回、祭りお助け隊に来ていただいて実感したのは、手伝ってくれる人がいるなら“人がいないから祭りはしない”という判断は、もう選択肢から外すべきだということです。お金についても、私たちが意義のあることを続けていれば、あとから集まってくるんです」

奉燈を曳く祭りお助け隊のメンバー
その上で、高橋さんは次のようにも言う。
「ただ忘れてはいけないのは、あくまで向田の住民が中心になって祭りを行うこと。人もお金も外部に頼りきりになると、祭りの意味や価値が薄れてしまいます。自分たちが手綱を握って主体的に進め、できない部分だけを手伝ってもらう。このバランスをどう保つかが課題だと思います」
「何もやらない」の先には縮小しかない
新しい取り組みを果敢に取り入れていく高橋さんの姿勢は、いささか冒険的すぎるきらいもあるかもしれない。しかし、本人は「何もやらないという選択肢は“ない”」と言い切る。
「その(何もやらないという)選択肢の先には、“縮小”しか待ってないですから。何事もやってみないとわかりません。今年これをやって成功したから次はあれをやろうとか、失敗したから来年はよそうとか、すべての挑戦が経験値になる。だから“やらない”よりも、“やる”という選択肢を増やしていった方がいい。それができないのは、責任を負う人がいないからですよ。誰かが“僕が責任を持つんでやりましょう”と言えば、みんなが動き出します。あの人のせいだと責任を押し付け合っていては、新しいことは生まれません。大切なのは、自分が責任を引き受けて前に進めること。さらに、自分のためではなく“誰かのため”という大義があれば、周りは自然と力を貸してくれます」
高橋さんが抱える大義は「町のため」、そして「若い世代のため」だ。
「子どもたちが楽しみにしているのに、大人の都合で祭りをやめるのはカッコ悪いと思うんですよね。子どもたちが望むなら、やるべきだと思います。それに、祭りは町のつながりを保つうえでとても大切なものです。ひとつの祭りを成立させるには、幅広い世代が集まり、話し合い、合意を重ねていく必要があります。時には揉め事も起きますし、若い人にとって年長者へ意見するのは怖いことかもしれませんが、それも良い経験です。そうしたコミュニケーションを通じて地域の結束は強まっていきます。新しい祭りをいま一からつくるのは難しい。だからこそ、いまある祭りを大事にし、続けていくべきだと思うんです」

祭り囃子に熱狂する若者たち

父親に肩車されながら祭りに参加する幼児
何のために私たちは祭りをするのか
かつて祭りは、地域の人々にとって欠かせない行事だった。当たり前すぎて、「なぜ祭りをするのか」をあらためて考える機会もなかったし、「言語化できていなかった」と高橋さんは言う。
「僕たちは、何のために祭りやるんだ? 子どもたちが楽しみにしているからだろう、と。だったらやろうよって、思うんです」
もちろん、この「何のため」は、人によっても、地域によっても変わってくるだろう。何のために祭りをやるのか。その問いは、むしろ「祭りを廃止する」という決断を早めることにつながるかもしれない。しかし、祭りの継承問題を考える上で、高橋さんの口から出てきた「言語化」というキーワードは、私にとってしっくりとくるものだった。
いまや「伝統を守る」というスローガンだけでは、祭りを続けるモチベーションを保ちにくい時代になってきている。だからこそ、「何のために祭りを続けるのか」を、私たちはいま一度問い直さなければならないのではないだろうか。言語化は、「主体性」を獲得していく作業でもある。誰のためでもない、自分たちがやりたいから祭りをするんだ、そう思えるようになることで、祭りは未来へとつながっていくはずだ。(了)
Text:小野和哉
プロフィール

小野和哉
東京在住のライター/編集者。千葉県船橋市出身。2012年に佃島の盆踊りに参加して衝撃を受け、盆踊りにハマる。盆踊りをはじめ、祭り、郷土芸能、民謡、民俗学、地域などに興味があります。共著に『今日も盆踊り』(タバブックス)。
連絡先:kazuono85@gmail.com
X:hhttps://x.com/koi_dou
https://note.com/kazuono
この記事を読んだ人におすすめの商品