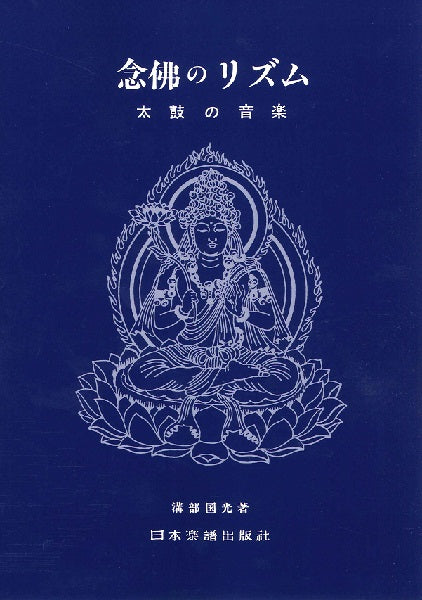日本には数え切れないほど多くの祭り、民俗芸能が存在する。しかし、さまざまな要因から、その存続がいま危ぶまれている。生活様式の変化、少子高齢化、娯楽の多様化、近年ではコロナ禍も祭りの継承に大きな打撃を与えた。不可逆ともいえるこの衰退の流れの中で、ある祭りは歴史に幕を下ろし、ある祭りは継続の道を模索し、またある祭りはこの機に数十年ぶりの復活を遂げた。
なぜ人々はそれでも祭りを必要とするのか。祭りのある場に出向き、土地の歴史を紐解き、地域の人々の声に耳を傾けることで、祭りの意味を明らかにしたいと思った。
地域で故人を弔うという風習
2025年8月、広島県の離島・大崎上島の木江(きのえ)地区で行われている盆踊り「あら盆供養盆踊り大会」に参加した。
当地の盆踊りは一風変わっており、踊りの際にその年、新盆を迎えた故人の遺影を遺族や地域の人が背負って踊る。遺影や位牌を抱えて踊る盆踊りが、瀬戸内地方のいくつかの地域で伝わっているという話はかねてから噂に聞いており、数年前から訪問の機会をうかがっていた。しかし、開催情報というのが世の中にほとんど出回っていない。そのため、二の足を踏んでいたが、このまま機会を逃がしていては、いつかその伝統も絶えてしまうかもしれない。空振りに終わっても、まずは行ってみようということで、ようやく重い腰をあげたのだった。
実際にその盆踊りを目の当たりにすると感動は大きく、自分もこのように弔われたら心地いいだろうなとも思った。旅を終えてから、さっそくその動画をSNSに投稿。すると私同様、感銘を受けた人は多かったようで、多くの反響が寄せられた(Xで2025年12月7日時点で5,346Like)。遺影を背負って盆踊りをするという、ある意味ではショッキングな光景ではある。しかし、多くの反応は好意的なもので(希少な文化への驚き、消えゆく伝統への郷愁、故人を重んじる姿勢への共感など)、この反響もまた、私にとっては印象深いものだった。
しかし肯定的な意見が集まるほどに、私たち日本人の中にある、ある種の引き裂かれるような感覚を意識せずにはいられない。地域で故人を弔う風景に心を温め、憧れのような感情を抱く一方で、現実として、私たちの「死」はいま、地域社会から大きく乖離している。将来、自分自身の葬儀に地域の人が参列してくれると期待できる人は、どれほどいるだろうか。むしろ私たちは、自らの意思で地域住民を葬儀から遠ざけてはいないだろうか。もっと言えば、知人や友人の参列すら望まず、煩わしい儀式を避け、ひっそりと弔う・弔われることを肯定する声も、決して少なくないはずだ。
「日本人」と大きく括ってしまったが、これは私自身の中にある問題意識である。遺影を背負う盆踊りを支えている「弔い」の社会システムに迫ることで、この「引き裂かれた意識」の正体を探ってみたいと思った。
瀬戸内エリア特有の盆踊り文化
旅のレポートに入る前に、大崎上島の盆踊りについて、まず全体像を整理しておきたい。そもそも私がこの盆踊りの存在を知ったのは、木下恵介「大崎上島の盆踊りについて」(『広島商船高等専門学校紀要』2018年 第40巻)という論文がきっかけである。現在、インターネット上で閲覧できる資料の中では、大崎上島の盆踊りを体系的に扱った、ほぼ唯一の資料と言ってよいだろう。
同報告書では、木江地区のほかに矢弓区、原田区の盆踊りも紹介されている。同じ島内でも地区によって盆踊りの形態には多少の違いがあるものの、初盆の霊を供養することを目的としている点、CDやテープといった音源ではなく、音頭取りが「口説き」と呼ばれる物語形式の唄を歌い、それに合わせて踊り子が踊る点は共通している。また地区によっては、盆踊りの最後に手拭いを使った「手拭い踊り」が披露されることや、遺影を手にしたり、背負ったりすることがあるとも記されている。
他の資料も見ると、大崎上島・旧東野町の郷土史である馬場宏著『移りゆくとき ふるさと東野シリーズ7』には、かつて音頭取りが傘をさして口説きを歌ったという話が紹介されている。この様式は、連載第10回で取り上げた沼島(兵庫県南あわじ市)の盆踊りにも通じるものだ。ただし、同書には遺影を背負うといった風俗についての言及は見られない。
ところで、大崎上島以外にも、遺影を用いる盆踊りは存在するのだろうか。調べてみると、いくつか類例が見つかる。たとえば香川県坂出市の「櫃石(ひついし)の盆踊り」では、過去1年間に亡くなった人の位牌を、家族や親戚が布に包んで背負い、交代しながら踊るという。また、愛媛県松山市・怒和島(ぬわじま)の元怒和地区では、盆踊りで遺影を背負うだけでなく、親族同士が仮装して踊る風習もある。この怒和島の盆踊りは、2023年に愛媛朝日テレビが取材しており、その様子は現在もYouTube上の公式映像で視聴できる。映像では、遺影を納めた箱が花などで華やかに飾られ、地元の人びとが明るく故人を送り出そうとする気概が伝わってきた。
愛媛ニュースチャンネル【eat愛媛朝日テレビ】より(2023年8月21日放送)
さらに、インターネット上で個人の発信をたどると、愛媛県松山市・中島、今治市・大三島、大分県津久見市・保戸島などでも、遺影を背負う盆踊りが行われているという記述が見つかる。こうした盆踊りが、瀬戸内エリアの離島を中心に伝承されていることは、たいへん興味深い事実である。遺影や位牌を抱えたり背負ったりする盆踊りが、どのように生まれ、どのような経路で広がっていったのか。深く掘り下げていけば、きっとおもしろい研究テーマとなるだろう。この点については、今後の宿題としたい。
さて、次からいよいよ、大崎上島の盆踊り模様をレポートしていきたいと思う。
レンタサイクルで島を横断
大崎上島へのアクセスは、そこまで困難なものではない。空路や、島に架かる橋がないので、基本はフェリーや高速艇での移動となるが、島内にアクセスできる港は本州や四国に5つもある。いずれも、航行時間は10〜60分程度だ。私は広島県広島市の竹原港からフェリーに乗り、島へ上陸するルートを選んだ。
広島市の竹原港からフェリーで大崎上島へ向かう
大崎上島の周辺には、大小いくつかの島が点在している。なかでも一際大きい「生野島(いくのしま)」は、大崎上島の北端に近接し、竹原港からの航路は、その合間を縫いながら進んでいくよう設定されている。島と島の間を船で分け入っていくような感覚は面白く、始終、私は外のデッキスペースに居座り船の進む先を眺めていた。

フェリーの船上から大崎上島を眺める。右端に見切れているのが生野島

ちょうどお盆の時期であったが、港は帰省で賑わうという様子もなかった
島に到着すると、私は港に隣接する「大崎上島町観光案内所」へと一直線に向かった。島の移動手段として予約していたレンタサイクルを確保するためだ。建物の前に着くと、開け放たれたドアから思いもかけず、盆踊り唄と思しき音楽が聞こえてくる。ああ、やっぱり盆踊りのシーズンなんだな、と実感する。
「今日は、島で盆踊りありますか?」
受付でレンタルの手続きをしながら、スタッフさんに何気なくそう聞いてみると、「盆踊りに興味あるんですか?」と、その表情に笑顔が灯る。それから、事務所にいた観光案内所のスタッフさんが総出になって島の盆踊り情報や、おすすめのスポットを教えてくれた。

2020年設立という、まだ歴史の浅い観光案内所。中に入ると、おしゃれな物産などが並んでいる
話を聞くと、案内所のメンバーの多くは島外からの移住者だという。島の文化に関心が深く、盆踊りについても毎年自分たちで各地に足を運び、情報を集めている。ただ、まだすべての集落を回りきれているわけではなく、木江の盆踊りについては未知の領域だそうだ。そう聞くと、なおさら自分の目で確かめに行きたくなる。
レンタサイクルにまたがり、さっそく木江地区を目指すことにした。だが、その道のりは自転車乗りにとって少々手ごわい。大崎上島は「島」とはいえ、面積は43.11平方キロメートルあり、芸予諸島に点在する有人島の中でも中規模クラスの大きさを誇る(200近くある島々のうち最大は、愛媛県の大三島で64.54平方キロメートル)。しかも目的地の木江の町は、私が上陸した東野地区の白水港から見ると、ほぼ島の反対側に位置している。そこへ向かうには、島の海岸線に沿って延びる環状道路をぐるりと走るか、あるいは最短ルートとして、内陸の丘陵地を山越えしていくか、いずれかの道を選ばなければならない。


山間部の道から、木江の町を見下ろす
結局、時間の関係で山越えのルートを選択したが、ここ連日続く灼熱の気象もあいまって、その道程は驚くほど険しい道のりとなった。
かつて造船業でにぎわった街
木江の中心街は、急峻の山が左右に迫る狭い平野部に形成されている。海沿いは開けているが、山側に近づくほど建物の密度が高まり、島特有の家屋がひしめき合う光景が広がる。盆踊り会場を探していると、海に面した広場にヤグラを確認することができた。周囲に地元の方とおぼしきご婦人などがチラホラ見受けられる。しかし、まだ盆踊りの始まる気配はなかったので、しばらく町を散策してみることにした
会場のそばには、島を周回する「大崎上島循環線」という道路が通っている。道の両脇には商店らしき建物が立ち並ぶが、どの店もほとんど営業している気配はほとんどない。人通りもまばらで、通りには静けさが漂っていた。

道路脇に立ち並ぶ商店らしき建物

「百貨店」と書かれた看板が目を引くが、ここも営業している気配はない

目抜き通りから少し離れた場所にある、世にも珍しい五階建ての木造家屋。
かつても木江を訪れた民俗学者・宮本常一も本の中で、この建物を紹介している
町の歴史をひもといてみると、木江は江戸時代までは民家が数十軒ほどの、ささやかな村にすぎなかったようだ。ところが明治期以降、造船や航海技術が発展し、日本海と大阪を結ぶ航路が、本州沿岸をたどる「地乗り航路」から、沖合を進む「沖乗り航路」へと主流が移る中で状況が変わる。潮の流れが変わるのを待つために船が立ち寄る「潮待ちの港」として木江が栄え始め、さまざまな商店が立ち並ぶようになり、やがては遊郭まで形成されるほどの繁盛を見せたのである。

とある飲食店の軒先には、かつての木江の風景を写したと思われる古い写真が貼られていた
加えて、造船業の発展もまた、この町の繁栄を大きく支える要因となった。『地場産業の町 上』(古今書院、1979)所収の大段徳行「造船業の木江町」によれば、木江の造船業は豊臣秀吉の文禄の役(1592〜1593)で軍船を造ったことに端を発するという。とりわけ木造船の製造では、長い歴史に裏打ちされた技術力を誇り、全盛期には「一〇〇〇トンを超える超大型木船を造った」「木江における1カ月の生産量が隣県の一年の生産量に匹敵した」時代もあったとされる。戦後の不況で木造船業はいったん陰りを見せたが、その後は時代の変化に合わせて鋼船建造に転じ、再生を図っていった。
現在も、名産のみかん栽培と並び、造船は木江の基幹産業である。しかし、全盛期の勢いはすでに失われているようである。

木江の造船所
大正8年(1919)には、島内で急激に造船業が発展し、木江地区に豊田郡立造船徒弟学校が設立、その後、広島商船の分校を経て広島県立木江造船学校となった。同校の卒業生は地元のみならず、全国各地の造船業を支える人材として大いに活躍した。しかしながら、経済発展の流れで、造船や海運は木造船から鉄鋼船へ、大量輸送に向けた大型化へ転向が進み、地域基幹産業であった造船業等が衰退することとなり、当地における人口減少の要因となった。
(清田 耕司・千葉 元・岸 拓真・水井 真治「消滅可能性離島における海事史のデジタルデータ化とデータ活用方法についての一考察」より)
踊りながら故人を供養する
日が暮れてきた頃に、盆踊り会場へと戻る。設営は着々と進んでおり、興味深く観察していると、ヤグラの前には祭壇が設けられ、さらにパイプ椅子も並べられた。しばらくすると遺影を抱えた、おそらく故人の親族とおぼしき方々が、それぞれにやってきて祭壇に遺影を安置する。最終的には、4つの遺影が並んだ。

祭壇に今年初精霊となった故人の遺影が並べられる
人々が着席すると、2名の僧侶が現れ、厳かにお経の読み上げが始まった。すると人々が列をつくり、順番に遺影の前で焼香をあげる。親族に限らず、盆踊りの参加者全員で故人を供養するのだ。

祭壇の前で合掌をする人々
読経と焼香が終わると、速やかに祭壇とパイプ椅子は片付けられ、盆踊りが始まる。驚いたのは、最初にかかったのが、東京ではおなじみの「東京音頭」であったことだ。揃いの衣装を着たご婦人方が踊りをリードするが、あっという間に終わってしまう。ちょっとした余興という感じであったのだろうか。それが終わると、今度はヤグラの上に法被を着た男性陣が上がり、生の歌と太鼓で口説きを歌い出した。

太鼓は二人がかりで叩く
ゆったりとした歌、ゆったりとした太鼓に合わせて、輪踊りが進行する。そして、やはり注目したいのが、背中に背負った遺影である。木製とおぼしき箱の中にすっぽりと遺影が収まり、さらに両脇にはLEDのローソクが添えられ、仏壇の雰囲気をかもし出している。

遺影を背負う人

子どもが背負う姿はほほえましい

他の3つとは形状の異なる箱がある。遺影を納める箱は、地区で共有しているものを借りる場合もあれば、遺族が自作することもあるという
遺影は親族だけのみならず、通りの輪の中にいるすべての人が交代に背負っていく。大人も、そして子どもも、みんな平等に、だ。また、特徴的なのは、喪服を着て踊る人がいることだ。逆に浴衣姿の人はほぼ見かけない。これも、供養の盆踊りらしい光景だ。
踊りの様子を眺めていると、ある女性が声をかけてくれた。彼女は、ある遺影を指して「この人、私の同級生だったんだよ」と教えてくれる。写真の中の人々も、かつては踊りながら先人たちの霊を慰める立場だった。それを見る生者の私たちも、いずれは遺影の中に収まり、踊りで送られる側になる。連綿たる供養の連鎖を感じ、じわっと心が温かくなった。
またしばらくすると、踊りの輪の中から、こちらに手招きをする女性がいる。「あなたも踊りなさい」というお誘いだった。少し遠慮をしていたが、故人を弔うつもりで思い切って飛び込んでみる。踊り自体はとても素朴な振り付けで、覚えるのは難しくない。しばらく踊っていると、本来は子どもだけに配っているはずのアイスを分けてくださり、申し訳ないと思いつつ、その気遣いに感謝する。

見れば見るほど不思議な光景
よそ者がいると、すぐ目につくのだろう。他にもいろいろな人たちが声をかけてくださった。盆踊りは1時間近く続いたが、終わったあとも「よかったら一緒に飲みませんか?」と誘っていただき、撤収後、盆踊り保存会の若い衆たちの打ち上げにも混ぜてもらえた。
盆踊りを運営する組織の変遷
木江の盆踊りをもっと深く知りたい。そう思った私は、後日ある人物にコンタクトをとった。木江の盆踊り保存会のリーダー、秋山英雄さんである。秋山さんは、盆踊りの最中に声をかけてくれた地元の方の一人でもあった。メールでオンライン取材をお願いしたところ、快く応じてくださった。

盆踊りで司会進行役を務める秋山さん
秋山さんは島を出て広島の大学に4年間通った後、1985(昭和60)年に大崎上島へUターンし、役場に就職すると同時に地元の青年団に加入した。それ以来、長年にわたり盆踊りの運営に関わっているという。話を聞くと、秋山さんがUターンで島に戻った当時には、すでに木江の盆踊りは継承の危機に直面していたそうだ。
「当時はまだ木江にも青年団があって、盆踊りの運営も木江町青年団が担っていましたね。ですが、昭和の終わりとともに青年団は解散。私が、その最後の青年団長となりました。解散の理由は、時代とともに若い人たちの興味が変わったからです。地域の行事よりも、テニスや音楽、ボランティア活動など、自分の好きなことに時間を使いたい。そういう流れになっていきました。ただ、一つの組織をなくすということは、本当に勇気の要ることで。先輩たちが受け継いできた伝統でもありますからね。そこで、“青年団は解散させるけど、これからも盆踊りは手伝うよ”ということで、当時新設されたばかりの地元の和太鼓グループが、運営に関わることになったんです。具体的には、和太鼓グループと区長会、女性会で新たに“盆踊り実行委員会”を組織して、実行委員会として盆踊りを運営していくことになりました」
秋山さんによれば、1980年代、日本各地で町おこしの一環として太鼓団体が結成されたという。島内でもかつては3つの和太鼓グループがあって、その一つが秋山さんの所属する木江神峰太鼓(1989年結成)だった。一時はメンバーも30名おり盛況だったが、時の流れとともにメンバーも減少。最終的には5〜6名程度となり、2004(平成15)年の合併直後に解散してしまう。
青年団、和太鼓グループと、盆踊りの後ろ盾となる組織が移り変わっていくなかで、転機となったのは7〜8年前。当時の区長の呼びかけで、「盆踊り保存会」なる組織が結成された。
「その区長さんが、“(地域の)祭りや、盆踊りはなくしちゃいけん”という、意欲のある人でね。地域の若いもんを集めて、それまでテープを流して踊っていたのを、昔のように生歌で踊るように変えたんですよ。歌詞集も、どこかから古いものを引っ張り出してきて。もしカセットテープだけてやっていたら、テープが切れたらそこで盆踊りも終わり、となっていたはずなので、この取り組みは良かったと思います」
担い手の若返りを一挙に図る。思い切った行動であったが、これが、盆踊りの伝統を次世代へつなぐ力になった。
「あれから時間は経ちましたが、まだまだメンバーは40代。若いので、あと10〜20年は盆踊りを続けられると思っています。ただ、彼らも年をとっていくので、次の世代も育てていかないといけない。それが課題ですね」

木江盆踊り保存会の面々
地域社会から切り離される「葬儀」
担い手はまだ確保できている。しかし、もう一つの問題がある。それは、「供養」という、この盆踊りの核となる要素についてだ。秋山さんは次のように話す。
「木江の盆踊りは、新盆のご家庭から事前に依頼をいただき、そのうえで盆踊りの場で供養をさせていただく、という仕組みをとっています。例年はだいたい10件ほどのご家庭からお申し込みがあるのですが、今年は依頼がかなり少なかったですね。亡くなられた方が少なかったということもありますが、それ以上に家族葬の増加が大きく影響していると感じています」
つまり、地域を上げての供養の場である「盆踊り」の需要に変化が起きている。その要因となるのが家族葬の増加であると、秋山さんは指摘しているのだ。
「例えば、私の住んでいる地区では、以前は地区の集会所で、地域の人たちが運営する葬儀を行うのが一般的でした。ところが、今ではその形はおよそ半分に減り、残りの半分は家族葬として家族だけで葬儀を済ませたり、火葬場で簡易な形で行ったり、あるいは地元ではなく、入院していた病院のある町で葬儀を行ったりすることも増えています。たとえ地域で葬儀をした場合でも、遺族が島外で暮らしていて、いずれ親族が誰もいなくなることが見えているので、“もう香典は結構です”と辞退されるケースも増えています」
葬儀に対する人々の意識の変化は、遺影を背負う盆踊りの継続に少なからず関わってくる問題だ。そこで、ここからは盆踊りから少し離れ、現代の葬儀のあり方について考えてみたい。
そもそも家族葬というのは明確な定義はないが、おおよそ家族や近親者のみで執り行う葬儀のことを指す。親族のみならず、故人の知人や友人、会社関係者など、参列者を限定せず幅広く招く、いわゆる「一般葬」と比べると、規模の小さい葬儀となる。
葬儀相談サイト「いい葬儀」が隔年で実施している「お葬式に関する全国調査」によると、2015(平成27)年時点で、直近1年以内に喪主を経験した40歳以上の回答者の葬儀形態は、一般葬が58.9%、家族葬が31.3%と、大きな差があった。ところが2020(令和2)年には、一般葬48.9%・家族葬40.9%と差が縮まり、コロナ期(2022年)に入ると密な葬儀を避ける動きも影響し、一般葬25.9%・家族葬55.7%と数値が逆転。コロナ後の最新調査では、一般葬がやや持ち直しているものの、依然として家族葬の割合が上回る状況に変わりない。
葬儀業界を研究テーマとする社会学者・玉川貴子によると、「家族葬」という言葉が登場したのは1990年代以降のことだという。玉川は、家族葬という形態が注目され始めた背景として、高齢化、核家族化、都市化などの影響を指摘する。
葬儀の会葬者も高齢化し、故人も喪主も定年退職しているケース、葬儀における地域との付き合いや手伝いが少なくなったことなど、さらには高額な葬儀費用への批判もありました。つまり、葬儀に対する不満や不安などが人々の間で高まっていったということがわかります。
(玉川貴子『葬儀業:変わりゆく死の儀礼のかたち』より)
急な出費による金銭的な負担もさることながら、亡くなった直後から葬儀までに発生するさまざまな手続き、遠方から忙しい合間を縫って来てくれる会葬者への気遣いなど、精神的・肉体的な負担も、従来スタイルの葬式を敬遠させる要因となっている。その結果、シンプルかつコンパクトな葬式の形が支持されるようになってきているというのだ。家族葬も、参列者の範囲を狭めているとはいえ、葬儀の費用はそれなりにかかるので、最近では通夜や告別式も省略した「直葬」と言われるスタイルも注目されている。
地域の助け合いで成立していた葬儀
しかし、葬儀を執り行う主体が、現在のように近親者や葬儀業者ではなく、地域社会が中心となっていた時代には、喪主や喪家(死者を出した家族)の負担は、ここまで大きくはなかったようだ。いくつかの例を見ていきたい。
八王子市市史編集専門部会民俗部会 編『八王子市東部地域由木の民俗』で報告されている、昭和40年頃までの東京八王子市の鑓水(やりみず)地区での葬儀洋式を例にとると、鑓水では、かつて冠婚葬祭の一切が、隣近所同士でなる「組合」という組織の手で行われていた。葬儀では、まず死者が出ると組合のメンバーで集まり、手伝いの役割分担や、通夜や告別式の日程について話し合いが行われる。その役割というのが多岐にわたり、死亡の知らせを親戚などに連絡する係(イイツギ)、寺や市役所へ手続きに行く係、葬具類を用意する係、お勝手でごはんを作る係(主に女性)、土葬用の穴を掘る係(メドバン)など、さまざまであった。葬儀業者が進出する前は、葬具を棺の上に被せる天板を自分たちで作ったり、葬式に使う幕や、葬列のなかで使う「龍の口」と呼ばれる道具をお寺から借りたりしていた。
民俗学者の山田慎也は『現代日本の死と葬儀: 葬祭業の展開と死生観の変容』(東京大学出版会、2007)の中で、和歌山県東牟婁(ひがしむろ)郡串本町古座地区を事例に、地域社会における葬儀の変容を分析している。古座地区では、火葬が導入される昭和40年頃までは、日頃の近所付き合いにもとづく人々「テッタイド」と呼ばれる地域住民が葬儀の主体を担っていた。この仕組みのもとで、喪主の役割は葬儀の規模を決めることにほぼ限られており、それ以外の実務、葬儀の知らせまわり、会場の準備、葬具の調達、買い物、土葬のための穴掘り、食事の用意などは、すべてテッタイドが引き受けていた。また驚くべきなのは、こうした役割分担が個々のテッタイドの自主性に委ねられていたという点だ。全体を指揮するリーダーがいなくても、各人が各人で自分の役割を見つけ、葬儀は自律的に遂行されていったという。
かくも、かつての葬儀は血縁関係に限定されず、地域社会と密接に結びついていた。遺影を背負う盆踊りのような、地域ぐるみで故人を供養する儀式も、こういった社会背景なしには成立しえなかったろう。
現代人が直面する死後の不確実性
強調しておきたいのは、昔ながらの地域住民に支えられた葬儀が、誰かの一方的な無償奉仕で成り立っていたわけではないという点だ。そこには「助けてもらったら、次は自分が助ける」という相互扶助の前提があり、その関係があってこそ成り立つものだった。先に紹介した古座地区でも、テッタイドのメンバーは、日頃から故人が付き合いのあった人間にほぼ限られていた。
こうした、隣り合う人どうしの「貸し借り」を土台としたつながりは、現代の感覚では「しがらみ」と受け止められ、煩わしく感じられるかもしれない。だが地域住民の相互扶助によって支えられた葬儀システムには、見逃せない利点もある。死後の行く末が、生前からある程度見通せる、その安心感である。
互助的な関係は、実際に自分が行っていることをしてもらうため、自らも死後どのようにされるのか推測することができた。よって自らの葬儀がどのように行われるかという推測可能なシステムは、それでなくとも死後どうなるか誰もわからない死に対して、少なくとも死後の変換に関しては相当の安堵感を持つことができたのであった。(中略)基本的に商取引というものは、物品、サービスの提供の代価として、金銭をその場で支払うことで、その関係は解消される。つまり葬祭業を利用するということは、業者と死者、喪家との関係は一回ごとに精算されるのである。
(山田慎也『現代日本の死と葬儀: 葬祭業の展開と死生観の変容』より)
「死に方を選べない」ということは今も昔も変わらないが、地域社会に委ねられた葬儀では、少なくとも死んだあとの弔われ方、葬られ方は、極論すれば生まれながらにしてほぼ確定している。誰が自分を弔ってくれるのか、その顔ぶれも自然にある程度は見通せたまま逝けたのである。
一方、葬儀業者の提供するサービスによって成り立つ現代の葬儀では、その契約段階まで、自分が、または家族がどのように弔われるか確定しない。日頃、この不安が表出することはほとんどないが、潜在意識の奥底では、多くの人が「地域社会のしがらみから自由になる」ことの代償として、死後への漠然とした不安を抱えているのではないだろうか。
最後に、再び話を木江の盆踊りに戻したい。結局、遺影を背負う盆踊りを見た時に生じる温かな感情というのは、この不安に起因しているのだと私は思う。死後、自分を送ってくれる親しい人がいる、そんな安心感を、この盆踊りからは感じることができる。しかし「自由」を獲得するために、地縁社会から積極的に距離をとってきたのは、他ならぬ私たち自身でもある。これが、「引き裂かれた意識」の正体だ。
祭りに惹かれながら、祭り的な地縁から逃れてきた私はなんなのだろうか。祭りを見るたび、私はこうした「ジレンマ」に直面する。しかし、こうも言えるかもしれない。この「ジレンマ」に向き合うためにこそ、私は祭りの現場に通っているのだ。(了)
Text:小野和哉
プロフィール

小野和哉
東京在住のライター/編集者。千葉県船橋市出身。2012年に佃島の盆踊りに参加して衝撃を受け、盆踊りにハマる。盆踊りをはじめ、祭り、郷土芸能、民謡、民俗学、地域などに興味があります。共著に『今日も盆踊り』(タバブックス)。
連絡先:kazuono85@gmail.com
X:hhttps://x.com/koi_dou
https://note.com/kazuono
この記事を読んだ人におすすめの商品