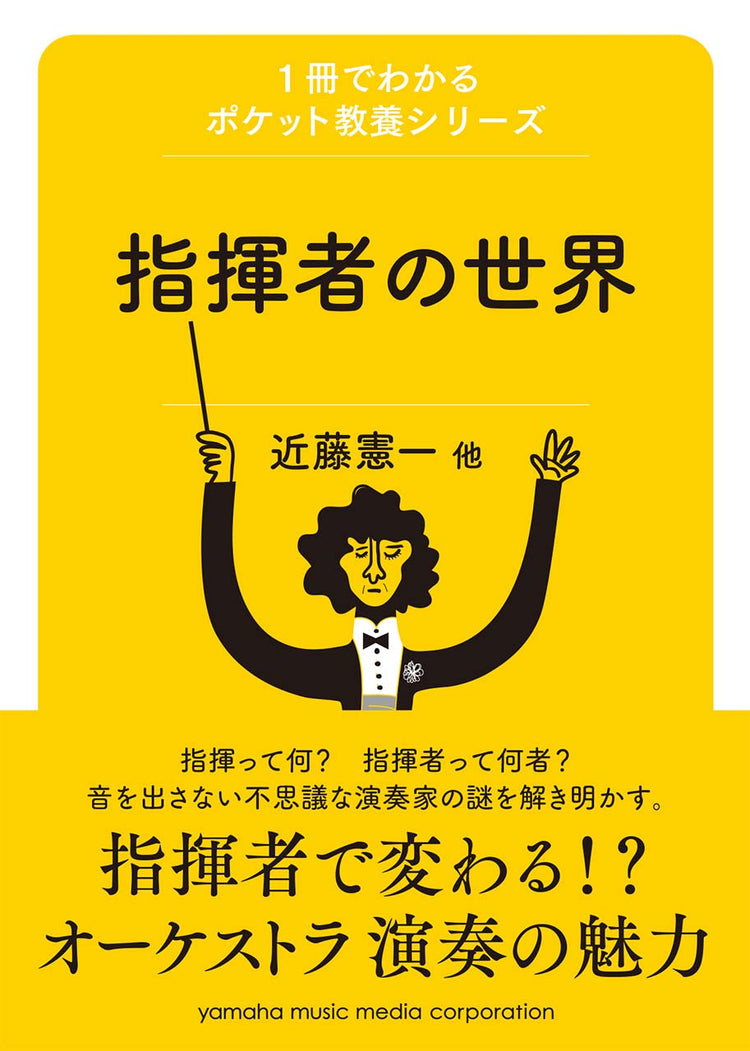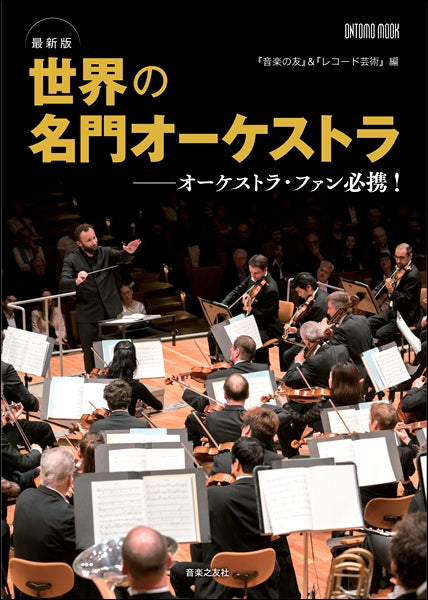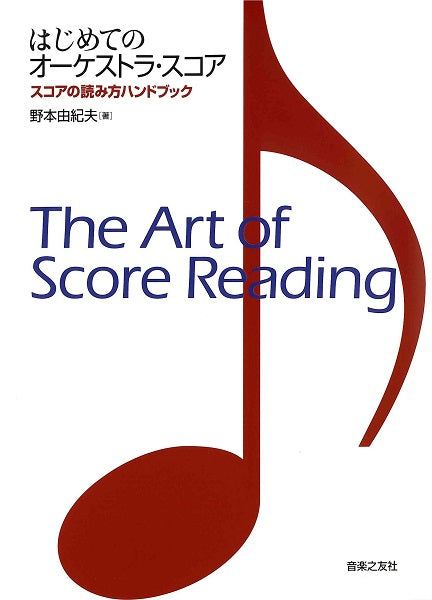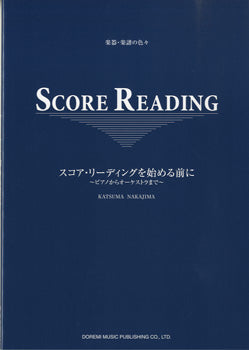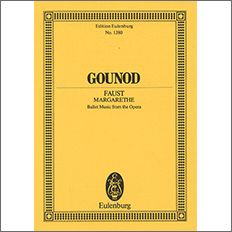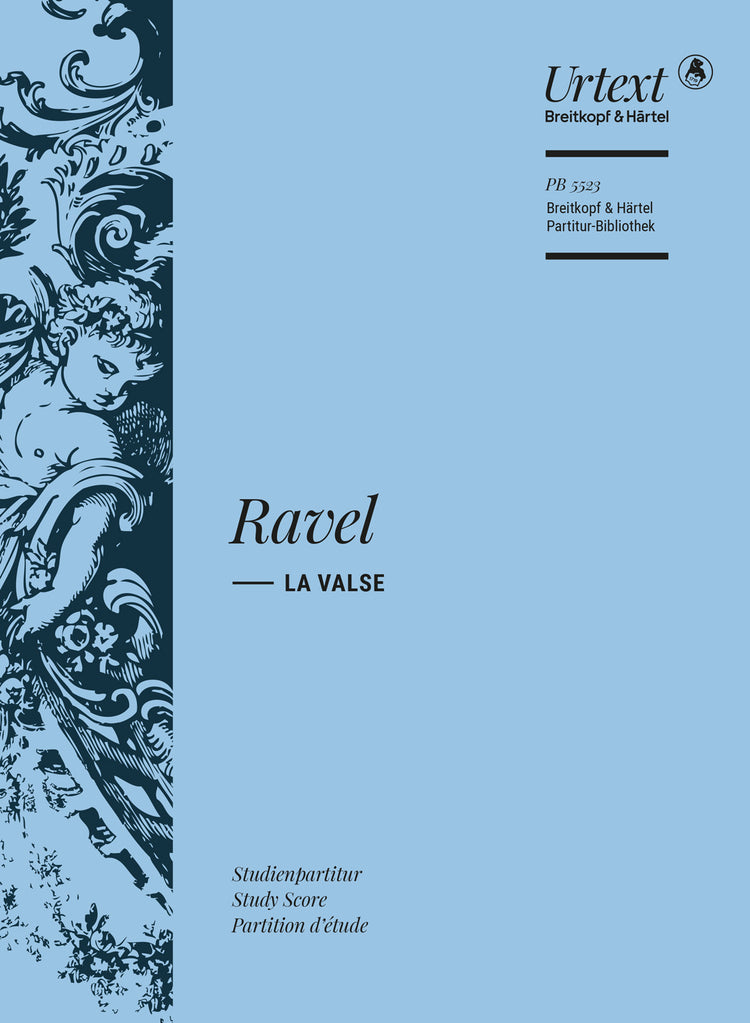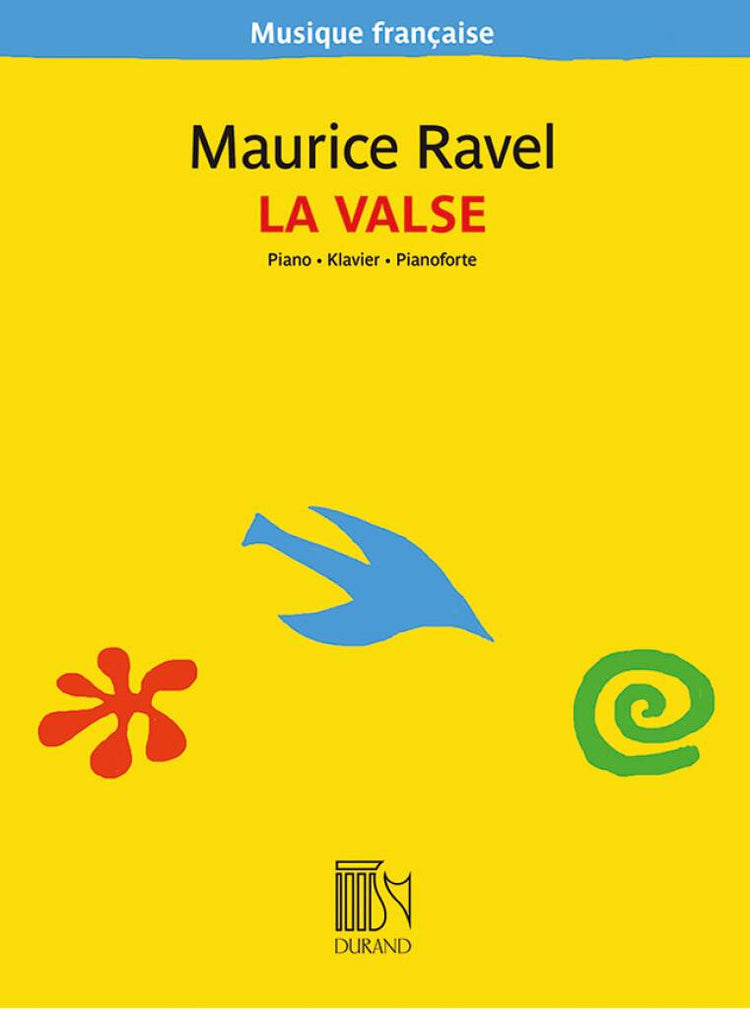ある時は指揮者、またある時は作曲家、そしてまたある時はピアニスト……その素顔は世界平和と人類愛を追求する大阪のオバチャン。ヨーロッパを拠点に年間10ヵ国以上をかけ巡る指揮者・阿部加奈子が出会った人、食べ物、自然、音楽etc.を通じて、目まぐるしく移りゆく世界の行く末を見つめます。
時代の転換期
みなさん、こんにちは! 今月から、3月にオランダ国立歌劇場で初演する現代オペラのリハーサルが始まりました。《ゼロ度の女》の作曲家、ブシュラ=エル・トゥルクさんの新作オペラ《ウンム》です。「ウンム」というのは、アラブ世界では誰もが知る有名な歌姫ウンム・クルスームの名前。アラビア語で歌われる彼女の歌を背景に、とある母と息子の物語が展開します。
演奏は、アムステルダム・アンダルシア・オーケストラ。オーケストラといっても奏者は12人、ほぼ全員が民族楽器の演奏者で楽譜を読める人はわずか数人、という編成です。いわゆる西洋のクラシック音楽とはチューニングも楽器の特性も異なるので、指揮もなかなか一筋縄ではいきません。しかし彼らと仕事をしていると、世界にはまだまだいろんな音楽や多様な表現方法があるということをヒシヒシと感じます。新しいことをたくさん吸収したい私にとっては、毎回が刺激と発見の連続です。
西洋の占星術によると、我々は今ちょうど200年に一度の大きな転換期にあるんだそうです。なんでも、形あるものを重視する物質主義の「土の時代」から、多様な価値観や自由な精神性に重きを置く「風の時代」に移り変わりつつあるのだとか。特に占星術を信じているというわけではないんですが、私自身もこの数年、自分が身を置いている世界の変化を感じていました。
「女性指揮者ブーム」の到来
その変化の一つに、「女性指揮者ブーム」があります。しばらく前からこの言葉を耳にするようになりました。確かに、指揮台に立つのは長らく男性がほとんどでした。もちろん、女性がまったくいなかったわけではないですよ。でも、私の二世代くらい前の先輩方には相当な苦難があったようです。指揮者になったものの壮絶ないじめにあったとか、安定したポストにつけなくて苦労した、という話をたくさん聞きました。それが、現在ではだいぶ潮目が変わっています。日本では沖澤のどか(1987~)さんがブザンソン国際指揮者コンクールで優勝した2019年頃からでしょうか、指揮者として活躍する女性が増えてきました。

世代の異なる2人のポーランド人指揮者、ゾフィア・ウィスロッカさん(左から2人目)とアンナ・デュツマルさん(右)。女性の指揮者がほとんどいなかった時代に苦労を味わったゾフィアさんは、国際女性マエストロ協会の発起人として女性指揮者の育成・活躍にも尽力されています。
世の中全体がダイバーシティを推進するようになったことも、もちろん影響しているでしょう。これまでの反動か、ヨーロッパではむしろ「女性をどんどん使いましょう!」といって、エージェントが女性の指揮者を積極的にプッシュすることもあるようです。私も知り合いの男性指揮者から、「君は女だからいいよな。今の時代、女性指揮者の方が仕事をもらえるもんな」なんて言われたことがありましたっけ。言ってみれば、今は前の時代の反動で、振り子が正反対に振り切れているような状態なのでしょう。
昨年だけでも、世界有数のオーケストラの音楽監督や芸術監督に就任した女性の指揮者が何人もいました。でも、彼女たちの就任は決して「女性指揮者ブーム」に乗じたものではなく、然るべき実力を評価された結果だと私は見ています。これまでは、実力があっても女性はなかなか相応のポストにつくことはできませんでした。時代の風向きが変わって、今ようやく実力が正当に評価されるようになったのだと思います。
しかしこの「女性指揮者」という言葉、皆さんは違和感ありませんか。私にはなんだか「男がすなる指揮といふものを、女もしてみむとて……」というニュアンスが含まれているように感じてしまいます。今でも時々「女性指揮者の阿部加奈子さんです!」と紹介されることがあり、思わずモヤッとした気持ちになります。もちろん本人に他意はないことはわかっているんですけどね。
同じような言葉に、「マエストロ」「マエストラ」という使い分けがあります。フランス語も男性なら「le chef d'orchestre」ですが、女性になると冠詞もその次の単語も変わって「la cheffe d'orchestre」になる。でも私自身は、わざわざ性別によって言い換えなくていいんじゃない?と思っています。日本語には少なくとも文法上「性の一致」がありませんから、あえて「女性指揮者」という必要はないですよね。もしかしたら、「女性指揮者ブーム」が落ち着く頃には、この言葉自体も使われなくなっているのかもしれません。

リハーサル中の一場面。休憩時間に奏者の質問に答えているところ。
「女性指揮者ブーム」の背景にあるもの
ブームのもう一つの背景として、プロオーケストラの水準が向上したことも大きいと思います。カラヤンやフルトヴェングラーに代表されるように、かつてはカリスマ的な指揮者が強いリーダーシップを発揮し、オーケストラを引っ張っていくやり方が主流でした。しかし現在、プロオーケストラの技術は全体的に当時よりもずっと向上しています。その要因としては音楽教育制度の充実と普及、またそれによって個々の演奏家の技術が向上したことなども挙げられるでしょう。オーケストラはある意味一つの生き物のようなものなので、集団で一つの音楽を作ることを通じて優れた技術が次の世代に受け継がれ、時間と共にグループ全体が成熟を遂げていきます。そうしてオーケストラのレベルが向上した結果、強権的なリーダーを必要としなくなった、と言えるのではないかと思います。
今や、ベルリン・フィルとかウィーン・フィルのようなトップレベルのオケは、指揮者がいなくても定番の交響曲ぐらいは演奏できるんです。つまり、単に拍子を取るとか音を揃えるだけなら、もはや指揮者は必要ない。では、オケが指揮者に何を求めているのかというと、それは「音楽性」なんです。指揮者がいったいどんな優れた解釈を持っていて、自分たちをどれほど驚きに満ちた新しい世界に導いてくれるのか? 自分たちの魂をどれほど崇高なところへ誘ってくれるのか? それを期待しているはずです。だって、楽員の一人一人がすでに経験豊かな、音楽を愛する人々なのですから。

リハーサル中、オケのメンバーに特殊な奏法の説明をしている図。
カリスマ指揮者の時代は、オーケストラの運営もトップダウンで決められることが多かったのが、今では楽員の意見を尊重し、民主的に運営されるようになっています。たとえば、初めて客演した指揮者がその後も同じオーケストラから呼ばれるかどうかというのは、楽員さんたちの意見によるところが大きい。それはカラヤンの時代にはありえないことでした。
今の時代に求められる指揮者像
今の指揮者に求められるのは、自分の持つ音楽的信念を押し付けるのではなく、すべてのメンバーが納得して理解できるように伝えるコミュニケーション力。そして多くの人に目を配り、耳を傾ける細やかな気配り。そうしたことができる指揮者が、オーケストラから支持されるようになっています。この時代の流れに、「女性指揮者」という存在がうまくフィットしたのではないでしょうか。
もちろん、女性だからといって必ずしも全員が同じような指揮のスタイルを持つわけではないし、男性指揮者の中にも神経の細やかな人はたくさんいます。あまり物事を「男性・女性」という属性で判断してはいけませんが、「統計的に」女性によく見られる気質とか傾向というのはきっとあるでしょう。昨今の「女性指揮者ブーム」は、今の時代が求める指揮者像に、女性が持つ特質が当てはまった結果なのではないかと考えています。
父性と母性を持ち合わせた指揮者
もっと言うと、私が「優秀だなぁ」と思う人は男性か女性かにかかわらず、父性と母性を両方兼ね備えていることが多いと感じます。父性とは、物事を大局的に捉え、包容力を持って判断する力のこと。母性は、見過ごされがちな細部にまで心を配り、的確にフォローする細やかさ。そんなイメージでしょうか。
私の師匠で現在N響の首席指揮者であるファビオ・ルイージ(Fabio Luisi, 1959~)さんは、まさにそんなイメージの代表格。プライヴェートでお会いすると本当に気さくで偉ぶったところがないんです。以前彼と待ち合わせをしたとき、ほんの数分遅れただけなのに遠くの方から息を切らしながら走ってきた師匠を見てなんだか感動してしまいました(笑)。どんなに偉くなっても、人と接する態度が変わらないんです。以前、師匠の自宅で練習をしたときも、みんなが飲み終わったティーカップをサッと片づけてキッチンで手際よく洗っている姿がとても印象に残りました。気遣いの細やかさって、そうした普段の些細な行動に表れますよね。

私の師匠、ファビオ・ルイージさんとミュンヘンにて。
それから数年前に、現代オペラの指揮法講座で一緒に教授役を務めたシャーン・エドワーズ(Sian Edwards, 1959~)女史。彼女は英国王立音楽院の指揮科主任教授で、私よりも一世代上の大先輩ですが、女性の指揮者がまだほとんどいなかった時代にイングリッシュ・ナショナル・オペラの音楽監督を務めていたというパイオニア的存在です。
私がこれまでの人生で出会った女性のなかで、彼女ほど頭の切れる人はいなかったですね。とにかく頭の回転が速い。彼女の指導方法を見ていても、とても余裕があってネガティブなことを絶対言わないんですが、実は非常によくいろんなことを見ているんです。そして一番的確なタイミングで、本人がポジティブなアクションを起こせるようなアドバイスを伝える。
講座ではエドワーズ女史と私で2つのグループに分かれて、それぞれのチームで指導をおこなったのですが、エドワーズ女史は受講生だけでなく教授役の私のことまでよく見ていて、「あなたの教え方、これこれこういう点がさすがね」と言われたときはびっくりしてしまいました。そんなところまで見ていたの!?と。彼女も父性と母性をバランス良く兼ね備えた指揮者だと感じました。

指揮法講座を終えたあとの集合写真。中列右から3人目がエドワーズ女史、その右隣が私。
人生の不思議な巡りあわせ
余談ですが、エドワーズ女史のポスト(英国王立音楽院指揮科主任教授)には元々、別の男性が着任する予定でした。それは、そこから遡ること約20年前、私が指揮科学生の頃に受講した指揮法講座で「日本人で女の子の君に、クラシック音楽がわかるのか?」と言い放った教授(連載第4回参照)です。残念ながら、彼は着任する直前に病気で亡くなってしまったのでした。彼の代わりに着任したのがエドワーズ女史だったのです。
衝撃のトラウマ体験から20年を経て、彼が着任する予定だったポストで教鞭を執るエドワーズ女史と共に自分が指揮法講座の教授を任される日が来るとは、人生とは不思議なものです。ちなみに、このときの講座は「女性指揮者のための現代オペラ指揮法」というものでした。(つづく)
著者出演情報
▼2025年5月15日(木) 19時00分開演
- 東京女子管弦楽団 第6回定期演奏会
- 指揮:阿部加奈子
- 出演:東京女子管弦楽団
- 会場:紀尾井ホール
- URL:https://tokyowo.art/-/2024-1126-2/
[曲目]
オッフェンバック:喜歌劇「天国と地獄」序曲
ラヴェル:ボレロ
ベルリオーズ:幻想交響曲 Op. 14
▼2025年5月25日(日) 15時00分開演
- 2025年度 武満徹作曲賞本選演奏会
- 審査員:ゲオルク・フリードリヒ・ハース
- 指揮:阿部加奈子
- 出演:東京フィルハーモニー交響楽団
- 会場:東京オペラシティ コンサートホール
- URL:https://www.operacity.jp/concert/award/finalists/2025.php
[曲目]
審査員ハース氏による譜面審査の結果、最終選考に残った3ヶ国4名の作品(世界初演)
チャーイン・チョウ(中国):潮汐ロック
我妻 英(日本):管弦楽のための《祀》
金田 望(日本):2群のオーケストラのための《肌と布の遊び》
フランチェスコ(イタリア)・マリオッティ:二枚折絵
▼2025年7月26(土)、27(日)
- 日生劇場ファミリーフェスティバル
物語付きクラシックコンサート「アラジンと魔法の歌」 - 指揮:阿部加奈子
- 演出:眞鍋卓嗣
- 作曲・編曲・音楽アドバイス:加藤昌則
- 出演:又吉秀樹(アラジン)、岡田誠(ランプの精)、宮地江奈(カンタービレ)、町英和(魔法使いムーサ)
- 演奏:ニッセイシアターオーケストラ
- 会場:日生劇場
- URL:https://famifes.nissaytheatre.or.jp/
▼2025年9月5日(金)、6日(土)、7日(日) 14時00分開演
- 藤原歌劇団公演《ラ・トラヴィアータ》
- 指揮:阿部加奈子
- 演出:粟國淳
- 出演:
ヴィオレッタ:迫田美帆(5日)、田中絵里加(6日)、森野美咲(7日)
アルフレード:笛田博昭(5日、7日)、松原陸(6日)
ジェルモン:折江忠道(5日、7日)、押川浩士(6日)
フローラ:古澤真紀子(5日、7日)、北薗彩佳(6日)
ガストン:堀越俊成(5日、7日)、工藤翔陽(6日)
ドゥフォール:アルトゥーロ・エスピノーサ(5日、7日)、龍進一郎(6日)
ドビニー:坂本伸司(5日、7日)、大塚雄太(6日)
グランヴィル:豊嶋祐壹(5日、7日)、相沢創(6日)
アンニーナ:石井和佳奈(5日、7日)、萩原紫以佳(6日)
ジュゼッペ:濱田翔(5日、7日)、原優一(6日)
使者:江原実
召使:岡山肇 - 合唱:藤原歌劇団合唱部、新国立劇場合唱団、二期会合唱団
- 演奏:東京フィルハーモニー交響楽団
- 会場:新国立劇場オペラパレス
- URL:https://www.jof.or.jp/performance/2509-la_traviata
※2025年2月21日現在の情報です
プロフィール

阿部加奈子
指揮者/作曲家/ピアニスト。
オランダ在住。東京藝術大学音楽学部作曲科を経て、パリ国立高等音楽院にて作曲に関連する6つの課程とともに日本人として初めて同音楽院指揮科で学び、フォンティス総合芸術大学大学院指揮科(オランダ)にて修士号を取得。パリ国立高等音楽院在学中より、ヨーロッパを活動の拠点に、指揮者、ピアニスト、作曲家として多方面で活躍する。2025年11月に横浜みなとみらいホールの委嘱による作曲家・阿部加奈子の新作を、阿部自身の指揮にて神奈川フィルハーモニー管弦楽団が初演する予定である。
公式ホームページ:https://www.kanakoabe.com/(英語、フランス語、日本語)
この記事を読んだ人におすすめの商品