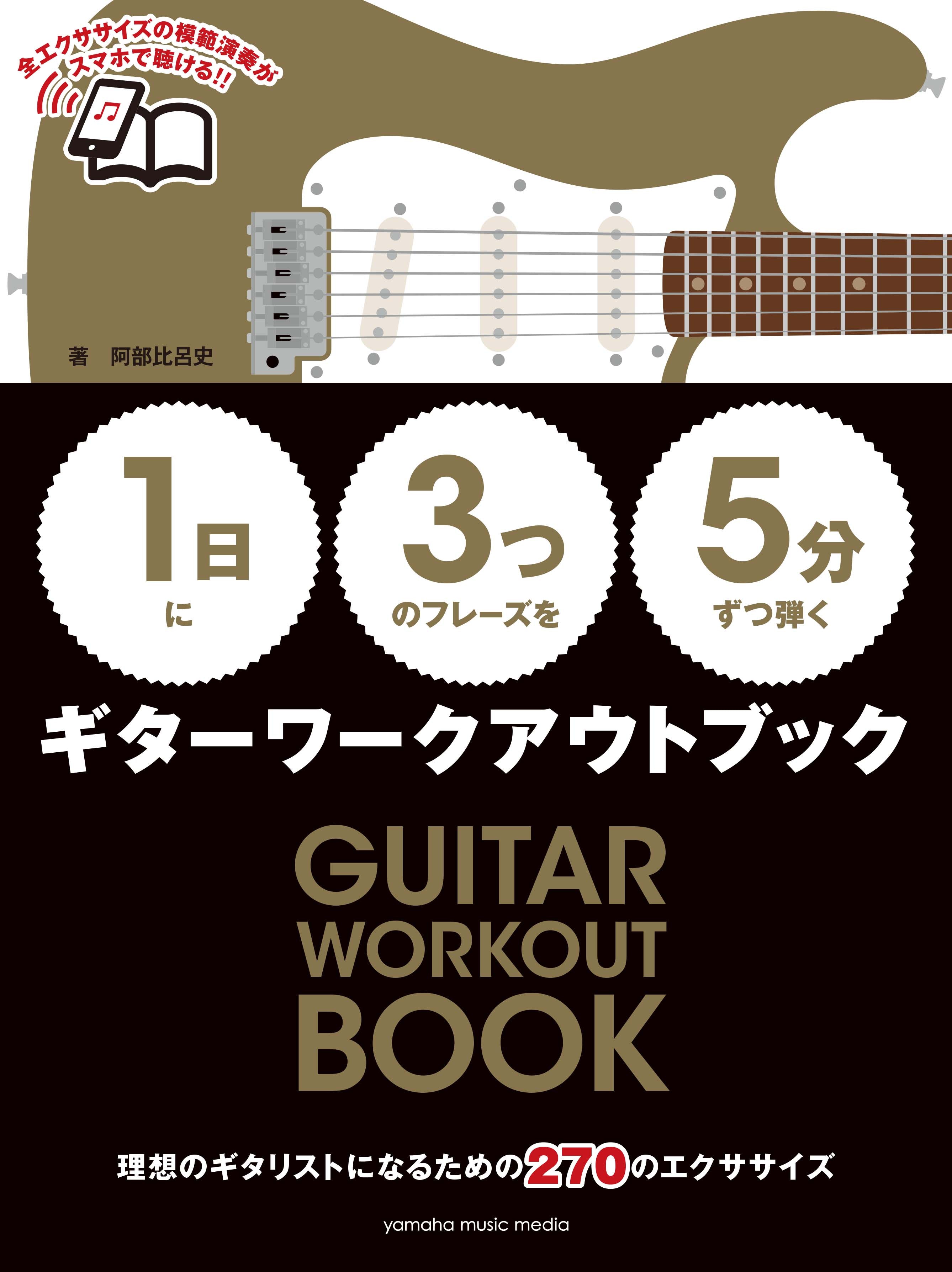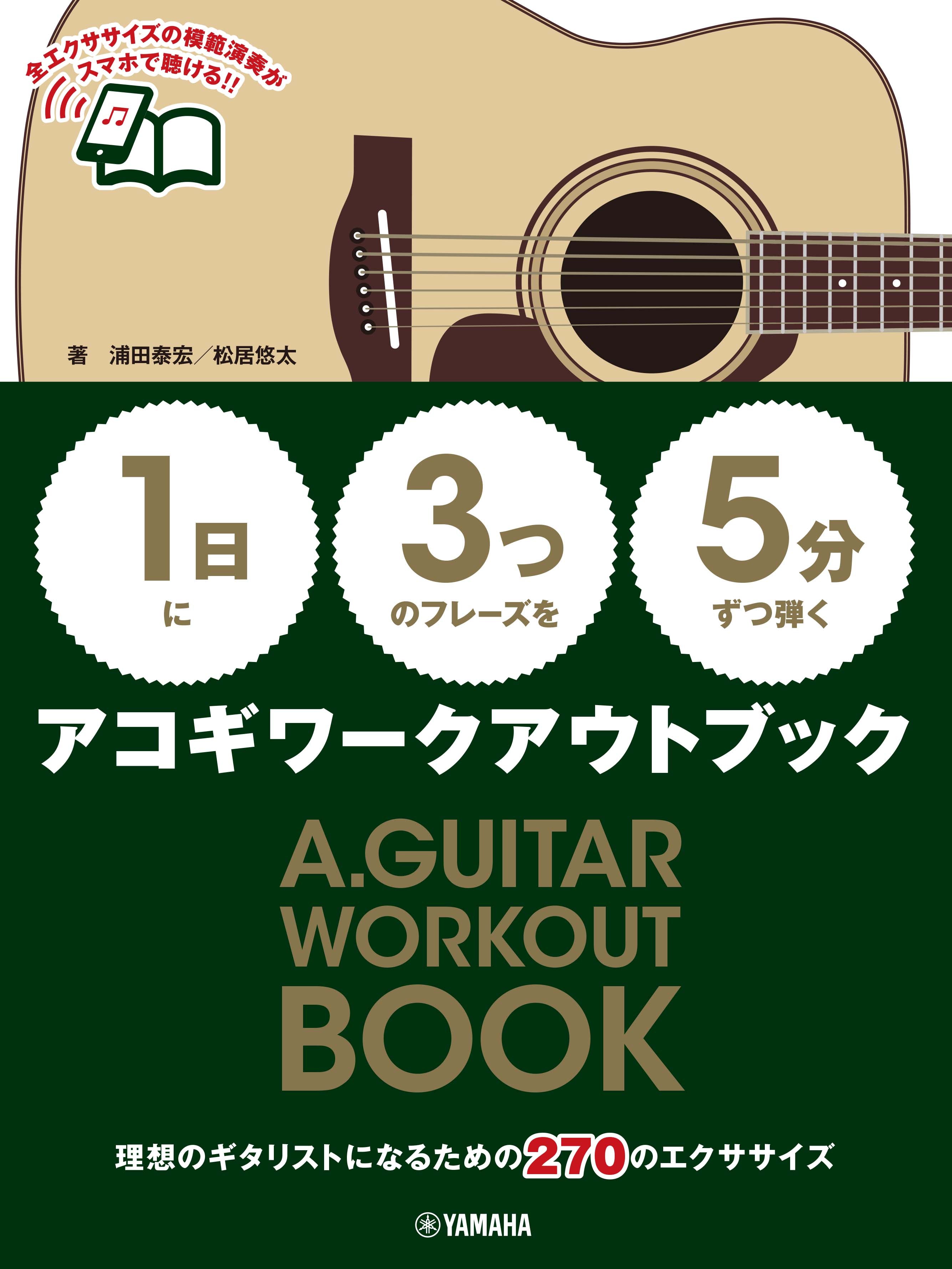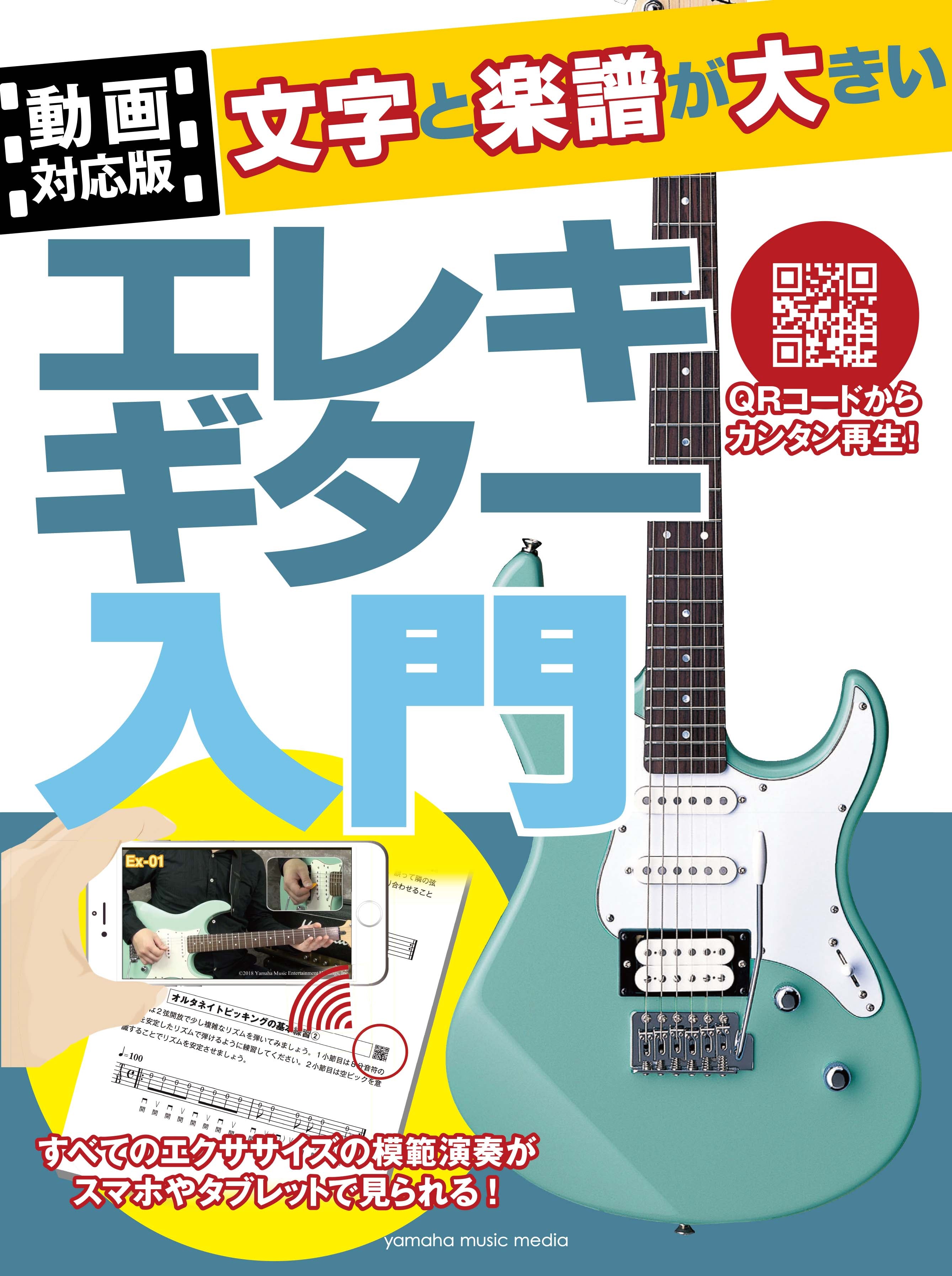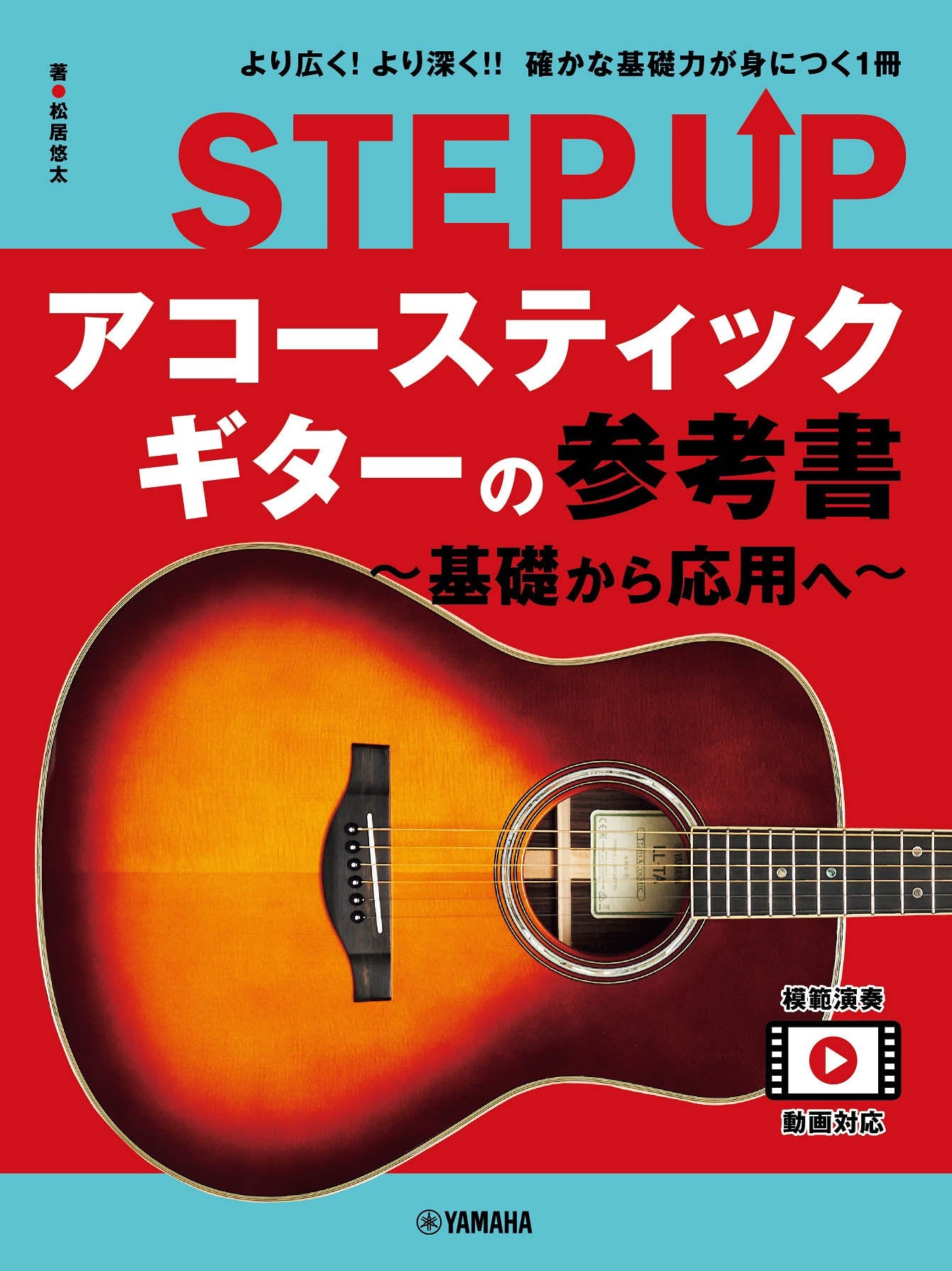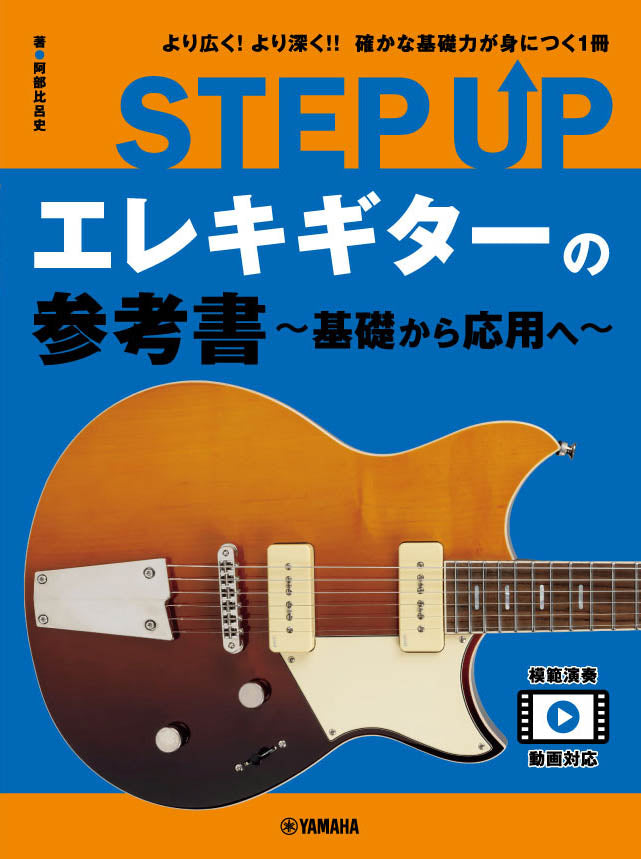1人でギターの練習をしていると、知らぬ間に間違ったやり方をしているなんてことがある。言葉は知っていても、実際にどうやるか分からなくて、「変なクセがついちゃった!」な~んて結果にもなりかねない。方向を間違うことはあっても努力だけは怠らないザセツ君と、ギター奏法の基礎を一緒に学んでいこう!

【プロフィール】
左:ザセツ君 (本名: 財園寺せつ夫)
遠足といえばお弁当。最近はキャラ弁というデコレーションしたものがあるみたい。僕のお弁当?もちろんキャラ弁だよ! おにぎりがピック型(≧▽≦)。ってそのままじゃん(´・ω・`)
右:ジミ先生
物理の先生で科学部の顧問。エフェクター作りが趣味で、エレキのことはこの人に訊け!と評判。老けてみられるが実は27歳。日サロ通いが欠かせない。
解説/竹内一弘 マンガ/ Dobby.



今回は、コードネームを見ただけでそのコードの構成音がわかるようになるために、コードネームの仕組みを知ろう。
図1がコードネームの表記のルールだ。1度の位置にはそのコードのルートが入る。ルートとは一番低い音のことで、Cナントカというコードのルートは必ずC音(ド)だ。
1度の次に3度の音の状態を示すのだが、メジャー3度(M3)のときは何も表記せず、マイナー3度(m3)のときだけ「m(マイナー)」と表記する。つまり、3度の位置に何もなければそれはメジャーコード、mがあればマイナーコードだ。
右下は7度の場所で、コードに7度が含まれるときのみ使用する。7度には2種類あるのだが、マイナー7度(m7)のときは7とだけ書き、メジャー7度(M7)のときは文字通りM7と表記。この辺りはちょっとややこしい。
右上はテンション(後述)を示す場所。コードに9、11、13や、それ以外のテンションが含まれるとき、そのひとつひとつをすべて表記する。
5度を表記する場所がないが、5度は必ずコードに含まれているので表記する必要はないんだ。例外として、5度が♭や♯したときだけテンションの位置に表記する。仕組みさえわかればとても簡単なので、しっかり覚えよう。


コードネームはアルファベットと数字でできている。一番左にある大文字のアルファベットは音名なので簡単。図2でアルファベットの音名度数表記を覚えよう。
次に数字だが、これはテンションを表しているんだ。数え方はいたって簡単だけど、ちょっと慣れが必要だね。図3のように鍵盤で見るとわかりやすい。C音(ド)のテンションは、まず「C」を1として、白鍵を2、3……というように順番に数えていく。注意したいのは2はコードネームの中では7を足して9に読み替える。というのは、テンションはルートから1オクターブ以上離れた音を指すんだ。同じように4と6も7を足して11と13に読み替える。
次はオルタードテンションだ。これは黒鍵にあたる音のことで「レ」が半音下がる、つまり9が♭するから♭9。簡単だね。♯9も同じような考え方で「レ」が半音上がった音ということがわかるね。
このように、度数は1〜13で表され、9以上の音をテンションと呼ぶんだ。



分数の形をしたコードネームがある。基本的には分子のコードを弾くんだけど、一番低い音は分母の音(単音)で弾くというもの。最低音を指定するケースで使われるもので、分数コードと呼ばれる。
図4を見ればその仕組みは簡単に理解できるだろう。分数コードは図5のように3種類の表記があり、それぞれ呼び方が違うが意味は同じだ。出版社によって表記が違うのと、国によっても違うので、3つとも覚えておこう。



分数コードと同様に、コードネームの表記は出版社や国によって違うし、印刷物と手書きでも違うことがある。ここでコードネームの表記のバリエーションを一気に紹介しよう。
図6のような種類がある。バリエーションは主に手書きの譜面で使われるもので、要は書くのが大変なので簡略化しただけ。どれもよく使われる表記なので覚えておこう。それでは最後にクイズ。CmM7(9)に含まれる音を度数で答えてみてね。答えはこのページの一番下にあるよ。


クイズの解答=ルート(ド)、♭3(♭ミ)、5(ソ)、7(シ)、9(レ)。
(Go!Go! GUITAR 2015年1月号に掲載した内容を再編集したものです)
Edit:溝口元海
この記事を読んだ人におすすめの商品