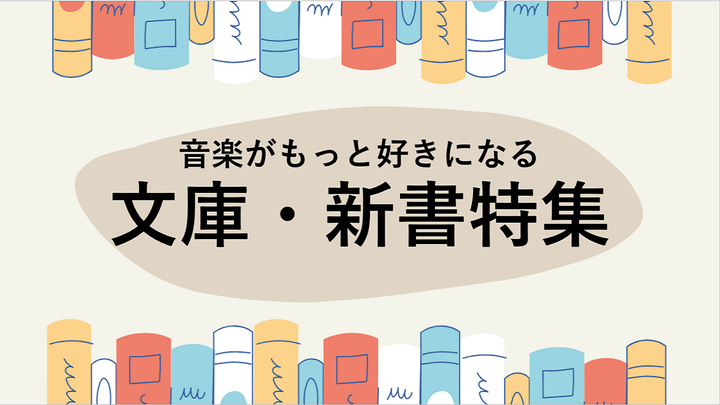音楽ライター・映画音楽評論家の小室敬幸氏が “今、読むべき1冊” を、音楽を愛するあなたにお届けします。第4回は、音楽批評についてです。
100年前の『アンサイクロペディア』……としての『悪魔の辞典』
いきなりだが『アンサイクロペディア』というWEBサイトをご存知だろうか? 2005年から運営されているウィキペディアのパロディサイトである。例えば「音楽」という記事を検索して、最初の見出し“概要”を読んでみると「音楽は、人間が開発した依存性のある薬物の中で最も広く蔓延し、極めて強い作用を持つ危険ドラッグの一つである」という書き出しになっており、該当の事物を風刺するような視点やブラックユーモアでもって記述されている。ウィキペディア同様、特定の著者がいるわけではなく、誰でも編集が可能な「フリー八百科事典(※八百科は、嘘八百に掛かっている)」だ。

▲アンブローズ・ビアスの肖像
(出典:Wikimedia)

こうした辞書・事典パロディの古典とされているのがアメリカのジャーナリスト、アンブローズ・ビアスによる『悪魔の辞典 The Devil's Dictionary』(1911)である。日本では筒井康隆ほか、様々な人々によって訳されているので、読んだことはなくても存在は知っているという方が一定数いるに違いない。例えば岩波書店から出版された邦訳で「ピアノ」という項目を引いてみると「性こりもなくやってくる訪問客を取って押えるのに使う客間用の道具。これを操作するには、この機械の鍵盤を下へ押し下げると同時に、聞いている奴の気を滅入らせさえすれば、それでよい。(西川正身 訳)」と書かれている。
うーむ、なんだか分かるようで分からない、意味を掴みきれない文章だ。英語の原文にあたってみると前半は「A parlor utensil for subduing the impenitent visitor.」となっている。先ほど引用した邦訳ではsubduingを“取って押える”と訳しているのだが、「(ピアノで)取って押える」という表現はどうにもピンとこない。どちらかといえばSubduingを「制圧する」というニュアンスに捉え、「ピアノ〔の演奏〕は不都合な来客さえ黙らせることができる」という主旨の文章と理解すべきではないか。
一方、原文の後半をみてみると「It is operated by depressing the keys of the machine and the spirits of the audience.」となっているので、depress[ing]を「(ピアノの鍵盤を)押し下げる」と「元気をなくさせる」という二重の意味で用いて、掛詞としての面白さが込められていることが分かる。いずれにせよ、簡潔にセンス良く翻訳することが難しいタイプの文章であることは間違いない。
こういう類の書籍は翻訳するよりも、読者と同時代・同言語・同じ文化圏を生きる別の著書によって新たに書かれたものの方が楽しめる。クラシック音楽で例を挙げれば、鈴木淳史『クラシック悪魔の辞典 完全版』(洋泉社,2002)という快著(怪著?)がある。私自身が高校時代に読んで影響を受けた本のひとつ、とだけ述べておこう。唯一残念なのは絶版なので、中古で探すしかないことだ……。
昨年3月、邦訳が出版されて話題となった『クラシック名曲「酷評」事典』(ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス,2021)は単独の著者が執筆したものではなく、編者が数々の事例を集めたものであるが、これもまた『悪魔の辞典』の系譜に位置するものの一種であろう。原著『Lexicon of Musical Invective』の初版は1953年と古いが、編者であるニコラス・スロニムスキー(1894〜1995)の没後、2000年になってから新装版が発売されている。なお邦訳が世に出たのは今回が初めてではなく、2008年に伊藤制子を中心とする5名の共訳者によって『名曲悪口事典 ベートーヴェン以降の名曲悪評集』(音楽之友社,2008)として出版されていた。
新訳である『クラシック名曲「酷評」事典』について、私は過去にFREUDEというWEBメディアに書評を寄稿したことがあるので、今回はこの本自体をどうこう語るだけでなく、書籍を出発点として「音楽批評」「音楽評論」なるものをいま一度考え直してみたい(本稿では「批評」と「評論」のどちらも、criticismの邦訳という前提で話を進める)。
音楽批評は未来を語れるか?
音楽之友社版の『名曲悪口事典』のあとがきでも触れられているように、音楽批評の歴史を顧みた時、ヨハン・マッテゾン(1681〜1764)による『クリティカ・ムシカ Critica musica』(1722〜25)を今日における音楽批評の原点とみなすことが多い。それは何故か? 久保田慶一が著書『音楽分析の歴史』(春秋社,2020)の「18世紀の音楽批評と音楽分析」という項目で説明しているように、マッテゾン以前は「批評者が一般の聴衆を啓蒙したり、作品の作曲技法上の誤りを指摘して、音楽家自身を教育したりするという目的が見出だせないから」だという。
つまり、音楽批評の基本となる目的は「聴衆の啓蒙」と「音楽家の教育」なのである。では、それはどのような価値観に基づいておこなわれるのだろうか? 例えば『クリティカ・ムシカ』において「音楽における自然の規則とは、耳に他ならない」と記しているのが象徴的なように、マッテゾンは複雑で人為的とみなした多声音楽よりも、「耳」馴染みする「自然」な旋律をもつ音楽を高く評価しようとする価値観をもつ人物だった。それ故にマッテゾンは、1730年代の著書においてバッハの複雑な音楽を否定的に評している(詳細は松原薫『バッハと対位法の美学』(春秋社,2020)を参照のこと)。

▲ヨハン・マッテゾン
(出典:Wikipedia)

こうしたマッテゾンの例に限ることなく18世紀から現在まで、「批評者が理想とみなしたスタイルに合致しているかどうかを判断する」ことが音楽批評の典型例のひとつであり続けている。だがそれに対し、所詮は批評者の「好き嫌い」に過ぎないのではないか?……という批判的な意見が繰り返されてきたのも事実だろう(単なる趣味的な「好き嫌い」ではない価値観であることへの担保として、作曲・理論・演奏・研究などの能力・実績といった批評以外の音楽に関する専門性を批評者に求める人もいるように見受けられるが、細分化した個別ケースになりすぎるため、深追いはしない)。
また想像に難くないように、「既存のスタイルへの合致」で判断している限り、そこから大きく逸脱した新しい価値観――例えば1980年代の調性回帰も一種の新しい価値観だ!――が提示された時にポジティブに捉えることが難しくなってしまうという問題がある。「新しい価値観」の評価が難しいのは、特定の音楽に表れた新しさにどれほどの意味があるかは、その音楽単体だけでは判断できないからだ。その新しい試みに追随するフォロワー(ただし、数の多寡は必ずしも重要ではない)も含めることで初めて、意味や価値の判断ができるようになる。
そのため、過去を振り返る形で記述される“音楽史”では、それぞれの時代におけるどの「新しい価値観」が重要であるかを判断しやすいが、ほぼリアルタイムで判断を下す“音楽批評”でそれを行おうとすることは、未来予知・予言とあまり変わらないのである。だからこそ、ここで強調しておきたい。未来の見通しを語った音楽批評はその内容が肯定的・否定的であろうとも、批評者の希望的観測に過ぎないということを。価値観が変化する予兆を感じ取って的確に未来を評した例はあるが、それは博打に勝ったに過ぎないのだ。
『クラシック名曲「酷評」事典』は復讐の書である!
批評対象である作曲家と作品が、未来において定評を得る……という選択肢を選ばなかったことで、「賭けに負けた」のが『クラシック名曲「酷評」事典』に掲載されている酷評の正体である。しかし博打に負けたと表現してしまうと、それが失敗だったように思われるかもしれないが、少なくとも私はそう思っていない。何故なら、批評は未来予測である前に、各々の時代においてその作曲家と作品にどうリアクションをしたのかを記録する役目を担うべきであるからだ。
その作品が当時どのように受け取られたのかという調査研究は、(デジタルデータが多く残された時代を研究するのであれば、また事情も変わってくるだろうが、紙ベースでの研究が前提となる時代の場合は)基本的に書き手がプロ・アマであるかを問わず、批評的な文章にあたっていくしかない。つまり『クラシック名曲「酷評」事典』に掲載されている「酷評」は、非常に真っ当な音楽批評なのである。
読み手にとっては『悪魔の辞典』のような魅力――巻末の「罵倒語索引」が付くことでその性格が強調されている!――が詰まっている書籍であることは間違いない。だけども、言うまでもないことだが『悪魔の辞典』では著者が自身の文章で笑われることを望んでいるのに対し、『クラシック名曲「酷評」事典』は(編者はともかく)批評者自身は非常に大真面目なものとして文章を書いている。それを恣意的に集めて引用し、『悪魔の辞典』のように見せるという、結構きわどいことをしているので、編者であるスロニムスキーは引用した文章の書き手たちを「彼らの多くは非常に教養豊かで文才のある人物」と褒めることも忘れない――ただし一瞬ではあるが。

▲ニコラス・スロニムスキー
(出典:Wikipedia)

そしてスロニムスキーは「音楽は発展し続けている芸術であると示すこと、そして、音楽界の革新者に向けられた抗議は、どれも同じ心理的抵抗〔=なじみなきものに対する拒否反応〕から生じたものであると示すこと」が『クラシック名曲「酷評」事典』の「目的」であり、どれほどの類例に事欠かないかを、まえがき(事典への前奏曲)で執拗に繰り返す。ところが、この編者は前述した「目的」を果たそうとした理由までは明言していない……それどころか敢えて隠している節さえあるのではないか?
隠された理由を読み解くヒントは、新訳である『クラシック名曲「酷評」事典』に新しく設けられた「編者略歴 スロニムスキーについて」に書かれている。1994年にロシアで生まれたスロニムスキーは、パリなどを経て、1923年にアメリカへ。その後、指揮者として活動をはじめ、同時代の新しい音楽を積極的に取り上げてゆく(ちなみに、そのハイライトともいえるのがアイヴズ《ニューイングランドの3つの場所》とヴァレーズ《イオニザシオン》の世界初演を担ったことだ!)。
ところが「編者略歴」によれば、「当時の最先端の音楽は聴衆になかなか受け容れられず、彼の指揮者人生は短期間で終わってしまった」らしい。実は彼が指揮した演奏会に対する酷評も、それと分かる形で3つ掲載されている。すべてヴァレーズの項目に載っているのだが、そのうち最も短いものを引用してみよう。
ヴァレーズの《イオニザシオン》を拝聴し、私が二台のストーブと台所の流しのために書いた曲をぜひとも見ていただきたいと思いました。《震動交響曲》という題で、ジャガイモが強力な噴霧器の力で崩壊する様子を描写したものです。
(イオナ・ロッタ・バンクの署名のあるはがき。ニコラス・スロニムスキーが、ハリウッド・ボウルでヴァレーズの《イオニザシオン》を演奏したあとに受け取ったもの、1933年7月16日)
少し説明をしておくと、イオナ・ロッタ・バンクというのは偽名であろう。そして《震動交響曲》で「震動」と訳されているのは脳震盪という意味もある“Concussion”なので、(脳にダメージを与えるぐらいの)相当に強い震動であることが分かる。加えて、妻ドロシー・アドロフとの書簡集にもこのはがきの話が出てくるのだが、そこでは“Concussion Symphony op. 1”と書かれていた。つまり、《イオニザシオン》は作曲家の初期作品に相当すると当てつけたいのであろう。

▲エドガー・ヴァレーズ
(出典:Wikipedia)
それにしても偽名であるとはいえ、本来はスロニムスキー以外の目には入らない私信を、受け取ってから20年後に事典に掲載して「晒す」というのは、どのような思いがあったのか? 指揮者としての活動を阻害する要因となった批評家・聴衆の無理解に、何らかの形でアゲインストしたくても、真っ当に反論しても水掛け論で平行線を辿るのは目に見えている。新しい音楽への支持を、どうやったら取り付けられるのか?
その解決策として考えられたのが、いつの時代も音楽批評が「なじみなきものに対する拒否反応」を示してきたことを、エンターテイメント化して大衆に訴えかけた『クラシック名曲「酷評」事典』だったのではないかと思うのである。これは指揮者スロニムスキーの遺恨を、辞書編纂家スロニムスキーが晴らそうとした一種の復讐なのだ。
(本記事は、2022年9月に執筆した記事を再掲載しています。)
Text:小室敬幸
<今回の紹介書籍>
『クラシック名曲「酷評」事典 上』
(ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス刊)
ニコラス・スロニムスキー 著、藤村奈緒美 訳
初版刊行日:2021年3月27日
判型:四六判
価格:2,090円(税込)
ISBN:978-4-63-696892-7
https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01096892
『クラシック名曲「酷評」事典 下』
(ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス刊)
ニコラス・スロニムスキー 著、藤村奈緒美 訳
初版刊行日:2021年3月27日
判型:四六判
価格:2,090円(税込)
ISBN:978-4-63-696893-4
https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01096893
プロフィール

小室 敬幸
音楽ライター/大学教員/ラジオDJ
東京音楽大学と大学院で作曲と音楽学を学ぶ(研究テーマはマイルス・デイヴィス)。現在は音楽ライターとして曲目解説(都響、N響、新日本フィル等)や、アーティストのインタビュー記事(レコード芸術、intoxicate等)を執筆する他、和洋女子大学で非常勤講師、東京音楽大学 ACT Projectのアドバイザー、インターネットラジオOTTAVAでラジオDJ(月曜18時から4時間生放送)、カルチャースクールの講師などを務めている。
X(旧Twitter):https://x.com/TakayukiKomuro
この記事を読んだ方におすすめの特集