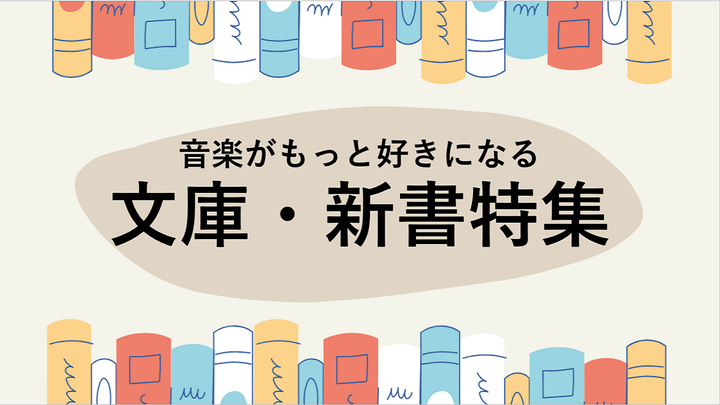音楽ライター・映画音楽評論家の小室敬幸氏が “今、読むべき1冊” を、音楽を愛するあなたにお届けします。第3回は『小澤征爾さんと、音楽について話をする』『マエストロ・バッティストーニのぼくたちのクラシック音楽』といった「指揮者が語る、指揮者について語る」音楽書を紹介いたします。
「実際に音を出しているのはオーケストラなのに、指揮者でそんなに変わるの?」
これまでの人生であまりクラシック音楽に触れてこなかった人にとっては、当然の疑問のようだ。人生の折々で似たような質問を投げかけられた。ちなみに今の私は「スポーツチームの監督のような存在。いくら能力の高い選手が揃っていても、監督の采配が悪いと実力を発揮できないでしょ? その逆も然り」と答えることにしている。本番の采配だけでなく、ビルダーとしての能力が求められる点も指揮者と監督は似ている。
指揮者によって演奏解釈がどれほど異なるかは、同じ楽曲を違う指揮者で――それもロマンティックなフルトヴェングラーと古楽のアーノンクールのように、対極に位置する指揮者を――聴き比べることで、誰の耳にも明らかになるだろう。
フルトヴェングラー
だが「何故そのように違う解釈に辿り着いたのか?」という疑問に(クラシック音楽オタク的な聴取体験をもとにした帰納的回答ではなく)答えるためには、その指揮者の思想や思考過程を追う必要があるので案外と厄介だ。弟子に教え継がれている口伝の情報も大事だが、一般の音楽ファンが気軽に触れられるのは指揮者が残した著作になるだろう。
指揮者が語る
指揮者本人が指揮について語った本を大きく分類すると、おそらく3つに分けられるのではないか。
1つめは、バトンテクニック(指揮の振り方)を具体的に解説したもの。最も有名なのは、小澤征爾をはじめ国内外で活躍する指揮者を数多く育てた齋藤秀雄の『指揮法教程』(音楽之友社,初版1956年)だ。日本では今もこれを教科書として指揮のレッスンをしている先生が多いのだが、実際に指揮を習うのでなければ特に読む必要はないだろう(指導してくれる先生がいないと理解しづらいという問題もある)。
2つめは、自らの思想を抽象的に語ったもの。フルトヴェングラーの『音楽を語る』(河出書房新社)や、チェリビダッケの『増補新版 チェリビダッケ 音楽の現象学』(アルファベータブックス)あたりが代表例だろう。結論からいえば、ファーストチョイスに一番向かない本で、その指揮者のことを理解した上でないと読み解いていくのは困難なのだ。そういう意味で、例えばフルトヴェングラーについて理解を深めたいなら、まずは第三者が書いた伝記を参照すべきだ。
3つめは、自らの経験をシェアしていくもの。自伝やエッセイのなかで語られる音楽論も多くはこれに分類される。最も豊富に残されたこのタイプのなかで、私が一番衝撃を受けたのはサー・エードリアン・ボールト(1889〜1983)の『指揮を語る』(誠文堂新光社)になるだろうか。日本語訳が出版されたのは1970年と古い本ではあるのだが、指揮姿が映像の遺されていない作曲家のエルガーや伝説の指揮者ニキシュについて語っている内容などが非常に興味深い。19世紀末に生まれたボールトの世代と、それから10〜20年後に20世紀になってから生まれた指揮者では、指揮法の考え方にかなり断絶があるのではないか等、考えさせられることが多かったため、今も印象に残っているのだが、いかんせん絶版になってから久しいので図書館でお探しいただくしかない……。
その他に、学者のようなスタンスで研究成果をもとに演奏法を論じた、アーノンクールの『古楽とは何か――言語としての音楽』(音楽之友社)、『音楽は対話である モンテヴェルディ・バッハ・モーツァルトを巡る考察』(アカデミア・ミュージック)のような例もあるが、これは指揮者による著作というよりも、(指揮者以外も含めた)古楽の演奏家の文脈にあるものと捉えた方がよいだろう。

ここまでお読みいただければ分かるように、3つめにご紹介した「自らの経験をシェア」するタイプの指揮者の著作が、多くの人にとっては最も読みやすいはず。現在も手に入れやすい本のなかでお薦めしたいのはまず、小澤征爾×村上春樹『小澤征爾さんと、音楽について話をする』(新潮文庫)だ。音楽書としては異例の大ヒット――それは音楽書ではなく村上春樹本として売れたからなのだろうが――になり、現在は文庫版(追加の文章が掲載されているので、文庫版および電子版を推奨!)で手軽に購入できる。
小澤が音楽を語った本は他にもあるのだが、(実際がどうであるかはさておいて)必要以上に編集が加えられていないかのようなやり取りが文字として起こされているのが本書最大の魅力である。自身がどのように音楽を理解しているのか、それを巧く言語化できているとは正直言い難い小澤の語りを尊重しつつ、村上春樹が話の広げ方によってその部分を自然と補ってゆく。村上春樹がこれまで手掛けてきた音楽関連の書籍のなかでも、最高峰に位置する一冊といってよいだろう。
もうひとつ、全く別の角度からお薦めしたいのは『マエストロ・バッティストーニのぼくたちのクラシック音楽』(音楽之友社)だ。書名の通り、指揮者アンドレア・バッティストーニの著作で、20歳半ばで書かれた。イタリア語で書かれた原著のタイトルは『シニアのための音楽じゃない』からも分かるように、若い世代にクラシック音楽を聴いて欲しいという願いが込められているのだが、私が最も興味深く読んだのは第3章「マエストロ」だ。
自らがどのような指揮のレッスンを受けてきたのか? そしてどんな歴史上の指揮者に影響を受けてきたのか? かなり包み隠さず語っているのだ。言い換えれば、若き天才と称されるバッティストーニが、過去の指揮者から何を取り入れた結果、そう評価されるに至ったのかを自己分析してネタバラシをしているに近い。この若さにして、それをしてしまう(そして読み手にとっても面白い内容になっている)のだから、やはりバッティストーニは只者ではない。

指揮者について語る
先ほどフルトヴェングラーの部分で少し触れたように、第三者が執筆した記述を通して、その指揮者の思考に迫ることも出来るだろうが、伝記となると活動歴・キャリアに主眼があてられることが多くなってしまう。「指揮」という行為そのものに興味があるならば、指揮者個々人の伝記ではなく、ルーベルト・シェトレ著/喜多尾道冬訳『指揮台の神々 世紀の大指揮者列伝』(音楽之友社)をお読みいただくようお勧めしたい。
専業指揮者の先駆けハンス・フォン・ビューロー(1830〜1894)や、現在では作曲家として知られるグスタフ・マーラー(1860〜1911)などが指揮者という職業および、指揮という行為に何をもたらしたのかを知ることができ、最終的には現在活躍中のサー・サイモン・ラトル(1955〜 )に至るまで、どのように変遷してきたのか? 数々のユニークなエピソードとともに掘り下げてくれる。注意点としては、原著が出版されたのは2000年なので21世紀の情報が取り扱われていないこと。取り上げられているのは独墺圏で活躍した指揮者が中心であるため、これで指揮者の歴史全体を一望できるわけではないこと。それでも本書を読めば、指揮と指揮者について理解を深めることができるだろう。
余談だが、『指揮台の神々 世紀の大指揮者列伝』には、『舞台裏の神々 指揮者と楽員の楽屋話』(著者・訳者・出版社同じ)という姉妹編が出版されている。前著で「指揮台の神々」と崇められた偉人たちの、非常に人間臭い側面を包み隠さず明かした一種の暴露本だ。なかでも巨匠オットー・クレンペラー(1885〜1973)が老齢になってから言い放った数々の「下ネタ」は強烈すぎて、ここに引用するのも憚られるほど……(苦笑)。崇高な演奏を聴かせてくれる指揮者も当然、いち人間であって、聖人君子ばかりではないことを知ることもまた、指揮者という存在を理解するためには必要かもしれない。
(本記事は、2022年8月に執筆した記事を再掲載しています。)
Text:小室敬幸
<今回の紹介書籍>
『小澤征爾さんと、音楽について話をする』
(新潮文庫刊)
小澤征爾 著、村上春樹 著
初版刊行日:2014年7月1日
判型:新潮文庫
定価:781円(税込)
ISBN:978-4-10-100166-1
https://www.shinchosha.co.jp/book/100166/
『マエストロ・バッティスト―ニのぼくたちのクラシック音楽』
(音楽之友社)
アンドレア・バッティストーニ 著、加藤浩子 監訳、入江珠代 訳
初版刊行日:2017年4月
判型:四六判
定価:2,090円(税込)
ISBN:978-4-27-620382-2
https://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail.php?id=203820
プロフィール

小室 敬幸
音楽ライター/大学教員/ラジオDJ
東京音楽大学と大学院で作曲と音楽学を学ぶ(研究テーマはマイルス・デイヴィス)。現在は音楽ライターとして曲目解説(都響、N響、新日本フィル等)や、アーティストのインタビュー記事(レコード芸術、intoxicate等)を執筆する他、和洋女子大学で非常勤講師、東京音楽大学 ACT Projectのアドバイザー、インターネットラジオOTTAVAでラジオDJ(月曜18時から4時間生放送)、カルチャースクールの講師などを務めている。
X(旧Twitter):https://x.com/TakayukiKomuro
この記事を読んだ方におすすめの特集