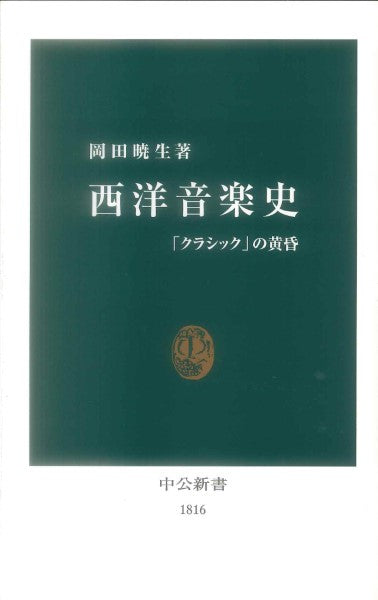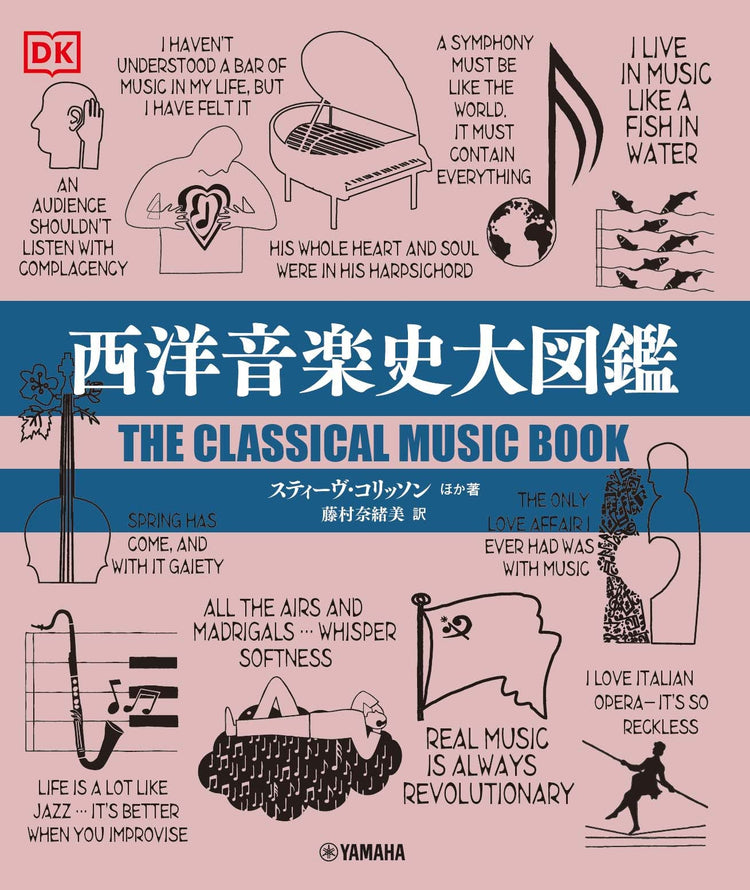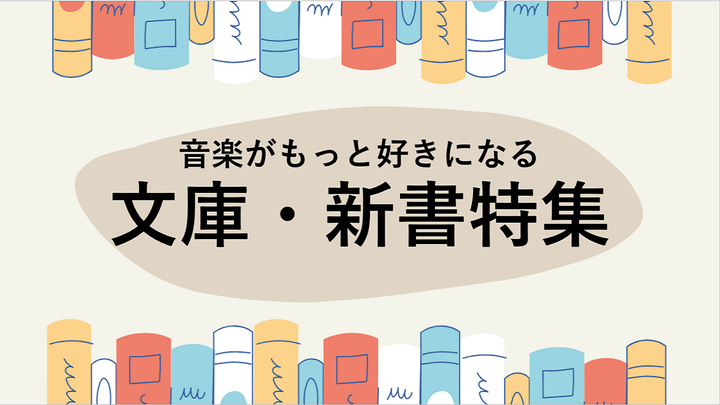音楽ライター・映画音楽評論家の小室敬幸氏が “今、読むべき1冊” を、音楽を愛するあなたにお届けします。第8回は「避けては通れない“音楽史”について」です。
クラシック音楽をただ聴いて楽しむだけでなく、“少し”詳しくなろうとした時、絶対に避けられないのが「音楽史」である。何故なら、作曲家と作品の位置づけは前後の歴史的な関わりと紐付けられることによって、適切に語ることが出来ると考えられているからだ。言い換えれば、歴史的な文脈(コンテキスト)に位置づけられないものは、評価をしようがない……これが西洋文化の本質ともいえる。
素朴な感覚からすれば、作曲されてから数百年後も演奏されている作品を残した作曲家を偉大な存在とみなしていると思ってしまうかもしれないが、実際のところは影響を与えた範囲が大きいほど偉大な作曲家とみなされる傾向がある。だからこそ音楽史を知らずに、有名な作曲家たちについて語ることは出来ないのだ。
(※『フランス音楽史』『オペラ史』のように、範囲を限った音楽史もさまざま出版されているが、今回はクラシック音楽の通史だけを取り上げる。)

――入門編
日本語で読めるクラシック音楽の歴史で、おそらく最も読まれているのは音楽之友社から出ている『はじめての音楽史 : 古代ギリシアの音楽から日本の現代音楽まで』だ。初版は1996年だが、その後2009年に増補改訂版、2017年に決定版が出版されているので、今から手に取る場合は必ず2017年に出たものを選んでほしい。
特に決定版で新しく書き下ろされた「もうひとつの音楽史」というコラムでは、旧来の音楽史では削ぎ落とされてきた視点が追加されており、時代遅れの内容にならないような対処がなされている(この部分を深く学びたいなら、村田千尋 著『西洋音楽史再入門 : 4つの視点で読み解く音楽と社会』(春秋社,2016)をお薦めしたい)。
ただし「はじめての〜」と銘打たれている時点で仕方がないのだが、限られたページ数に紀元前から現代にいたる西洋と日本の音楽の歴史を詰め込んでいるため、記述が非常に教科書的で、正直面白いとは言い難い。また事前にある程度、作曲家や作品名を知らないと、読んでも情報が頭に残らない可能性は高そうだ。
読み物としての面白さを重視するなら、定評があるのは岡田暁生 著『西洋音楽史 : 「クラシック」の黄昏』(中央公論新社,2005)である。本書の魅力は、著者自身が何故そのような判断を下すに至ったかの経緯や前提がちゃんと共有されているため、(その見解に同意するかはさておき)読者を置いてけぼりにすることがないのだ。アカデミックな見地を、そうとはみせないで的確に解きほぐして解説していく手腕は極めて鮮やかだ。
もっと回りくどくなく、スパッとした語り口が良いのならば、片山杜秀 著『ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる』(文藝春秋,2018)がいい。本書最大の欠点はミスリードになってしまっているタイトルで、実態は9〜10世紀から20世紀初頭の第一次世界大戦頃までの音楽と文化を扱っている音楽史なのだ。先に挙げた岡田の『西洋音楽史』と同様、新書なので網羅性は低いが、音楽を歴史に紐付ける意義や面白さを感じてもらえる第一歩になる。そういった意味で、この手の書籍の存在は重要なのである。
――上級編
上級編の代表格といえるのが、音楽之友社から出ているグラウト/パリスカ著『新西洋音楽史』だ(上巻・中巻は1998年、下巻は2001年出版)。原著は英語で書かれた西洋音楽史のなかで最も定評のあるもので、著者のドナルド・ジェイ・グラウト(1902〜87)とクロード・V.・パリスカ(1921〜2001)は共に、アメリカ音楽学会の会長を務めた音楽学者である。日本語訳は3巻合わせて1200ページほどのボリュームで、音楽大学の大学院受験にむけて音楽史全体をしっかりと学び直すことも可能だ。
ただ上級編扱いにしている通り、易しい内容ではない。それに加えて一部の国の作曲家について原語での発音にこだわるあまり、とっつきづらいカナ表記が散見される。例えばチャイコーフスキイ(チャイコフスキー)、バラディーン(ボロディン)、ムーサルクスキイ(ムソルグスキー)、フォレ(フォーレ)、ドビュシ(ドビュッシー)、プラコーフィエフ(プロコフィエフ)、シャスタコーヴィチ(ショスタコーヴィチ)、ホウルスト(ホルスト)、ティピト(ティペット)、ヴィッラ=ロブス(ヴィラ=ロボス)、ミヨ(ミヨー)等など……。カッコ書きした通例のカナ表記(勿論この本には載っていない!)も分かった上で読まないと、かえって混乱してしまうだろう。
同様の路線でもう少し読みやすいのが全3巻の『西洋音楽の歴史』(シーライトパブリッシング, 2009〜2011)である。こちらはイタリアで書かれた音楽史で、著者はマリオ・カッロッツォ(1961〜 )とクリスティーナ・チマガッリ(1961〜 )と世代はグラウトとパリスカより若いが、原著自体が書かれたのは90年代後半とほぼ同時期だ。
翻訳が時々怪しいという難こそあるが、前述の『新西洋音楽史』よりかなり読みやすく、何より「考察」と題されたセクションが充実している。単に通史を学ぶだけでなく、重要トピックについては具体的な作品を分かりやすく分析してみてくれるのだ。楽譜が読める必要はあるが、古代の音楽や中世の聖歌から、20世紀後半のブーレーズやシュトックハウゼンまで、この3巻だけでしっかりと基礎を学ぶことが出来る。
――変化球(?)編
さて、ここまでは真っ当な、ある意味では正統派のセレクトでお送りしてきたが、最後に少しばかり変化球の2冊を取り上げたい。まずは山根悟郎 著『歴代作曲家ギャラ比べ〜ビジネスでたどる西洋音楽史』(Gakken, 2020)だ。
読んでそのまま、タイトル通りの内容なのだが、この手の路線をとった書籍のなかでは誠実な内容だ。「金額の“完璧な”置き換えは極めて困難で、唯一絶対の正解はない」とした上で、どのように現代の日本円に換算したのか計算方法まで開示されているのだから。そして作曲家を神聖化せず、作品は芸術である前に当時の社会から生まれたプロダクト(生産物)であり、コンテンツであることをいま一度思い出させてくれるという意味で、現代の学問的な研究から遠くないところにある考え方を平易なエンタメとして読ませてくれる。

なぜ、そういった考え方が必要なのか? この記事の最初の方で触れたように、影響を与えた範囲が大きいほど「大作曲家」としてみなされる傾向がある。しかし「大作曲家」を普遍的な存在として絶対視しすぎると、その系譜から外れた作曲家を評価しづらくなってしまうのだ。もっと言ってしまえば、意に沿わない作曲家を批判する理由にも使われてしまうのである。「大作曲家」は、それ以外の「(群小)作曲家」との違いを際立たせることで作られるのだ。
そもそも現代に近いほど評価の共通認識がとれていないため、確定的なことが書きづらいし、書かれた時期による限界性はある。とはいえ、様々な音楽史を読み比べてみると、どの時代まで記述しているのかに、著者のスタンスが表れていることが多い(第二次世界大戦後の前衛音楽と実験音楽を取り扱うのか? そのあと前衛芸術が停滞していくポストモダンの時代も範囲に含めるのか……?等など)。
そうした難しいバランスを絶妙な感覚で舵取りしながら、通史を描いているのが英国と米国の老舗が合併したアメリカのペンギン・ランダムハウス社から2018年に出版された『The Classical Music Book』(スティーヴ・コリッソンほか著)を訳して、ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスが2021年に日本で出版した『西洋音楽史大図鑑』である。そう! “書”いているだけでなく、“描”いているのだ!邦題に「大図鑑」と付けたのは的確な判断だったといえる。
目次をみれば明らかなように、見出しには必ず何らかの作品がセットになっている。J.S.バッハとベートーヴェンだけは2つの見出しで取り上げられているが、あくまでもそれは例外。他の作曲家は1作品ずつしか選ばれていない。見出しのトピック次第で割かれているページ数は異なるが、それにしても従来の音楽史に比べると「大作曲家」と「群小作曲家」の扱いの差は少ないのが特徴的だ。
アカデミックな視点からみると、つっこみたくなる内容もある(例えば、リヒャルト・シュトラウスの見出しになっている言葉はマーラーの発言なのだが、その説明がない等)。しかし、リスナーのための拓かれたガイドとしては、かなり魅力的な内容だ。最初から読み通さなくても楽しめる作りになっているので、パラパラとめくりながら気になった項目だけを読んでも得るものがあるはずだ。作曲家が主役というよりも、あくまでも歴史の登場人物として登場してくるバランスだからこそ、流れも掴みやすい。
そして非常にユニークな点として、戦後の現代音楽における最重要人物であるはずのピエール・ブーレーズを見出しにあてがっていないのは非常に興味深い。シュトックハウゼンのページに少し名前が出るだけなのである。書かれている内容を踏まえるとシュトックハウゼンの音楽に含まれる空間性の方が、重要であると判断したのだろう。
そしてシュトックハウゼンのあと、16人の作曲家が見出しになっているのだが、そのうち原著が書かれた2018年の時点で存命中だったのは9名(2023年3月時点で存命中は7名)で、最後から3番目に登場する現代アメリカを代表する女性の作曲家ジェニファー・ヒグドン(1962〜 )に2ページをあてがっているのは本書の方針を、ある種象徴しているように思われる。
原著のタイトルは『The Classical Music Book』――つまりクラシック音楽の歴史であって、現代音楽の歴史ではないのである。現代音楽も含まれ得る「西洋音楽(Western Music)」ではなく、クラシック音楽の本であるとタイトルで明言することで、これまでとは異なる音楽史を描き、リスナーに同時代の美しいクラシック音楽を紹介しようとしているのであろう。クラシック音楽が今後も長らく聴かれていくためには、こうしたスタンスの書籍も増えていくべきではないかと思う。
(本記事は、2023年4月に執筆した記事を再掲載しています。)
Text:小室敬幸
<今回の紹介書籍>
『西洋音楽史「クラシック」の黄昏』
(中央公論社刊)
岡田暁生著
初版刊行日:2005年10月25日
判型:新書判
定価:902円(税込)
ISBN:978-4-12-101816-8
https://www.chuko.co.jp/shinsho/2005/10/101816.html
『ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる』
(文藝春秋社刊)
片山杜秀著
初版刊行日:2018年11月20日
判型:新書判
定価:880円(税込)
ISBN:978-4-16-661191-1
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166611911
『西洋音楽の歴史 (1)(2)(3)』
(シーライトパブリッシング刊)
M.カッロッツォ/C.チマガッリ 川西麻理訳
初版刊行日:
(1)2009年3月6日
(2)2010年3月31日
(3)2011年3月28日
判型:B5判
定価:
(1)4,180 円(税込)
(2)5,060 円(税込)
(3)5,720 円(税込)
ISBN:
(1)978-4-90-343906-8
(2)978-4-90-343908-2
(3)978-4-90-343910-5
(1)http://www.c-light.co.jp/contents/books/978-4903439068.html
(2)http://www.c-light.co.jp/contents/books/978-4903439082.html
(3)http://www.c-light.co.jp/contents/books/978-4903439105.html
『歴代作曲家ギャラ比べ ビジネスでたどる西洋音楽史』
(Gakken刊)
山根悟郎著
初版刊行日:2020年12月10日
判型:A5判
定価:1,760 円(税込)
ISBN:978-4-05-801236-9
https://hon.gakken.jp/book/2380123600
『西洋音楽史大図鑑』
(ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス刊)
スティーヴ・コリッソン監修 藤村奈緒美訳
初版刊行日:2021年12月27日
判型:B5変形判
定価:4,840 円(税込)
ISBN:978-4-63-697833-9
https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01097833
プロフィール

小室 敬幸
音楽ライター/大学教員/ラジオDJ
東京音楽大学と大学院で作曲と音楽学を学ぶ(研究テーマはマイルス・デイヴィス)。現在は音楽ライターとして曲目解説(都響、N響、新日本フィル等)や、アーティストのインタビュー記事(レコード芸術、intoxicate等)を執筆する他、和洋女子大学で非常勤講師、東京音楽大学 ACT Projectのアドバイザー、インターネットラジオOTTAVAでラジオDJ(月曜18時から4時間生放送)、カルチャースクールの講師などを務めている。
X(旧Twitter):https://x.com/TakayukiKomuro
この記事を読んだ方におすすめの特集