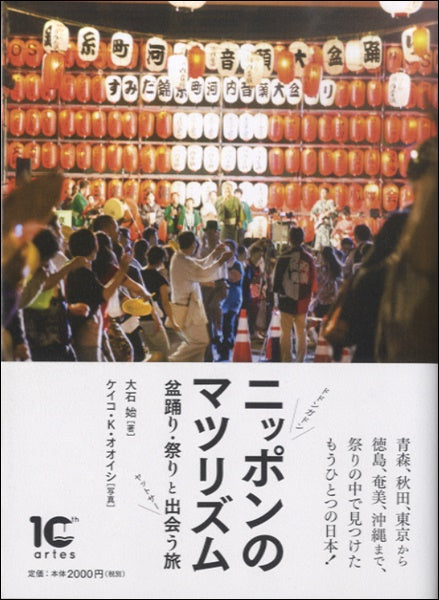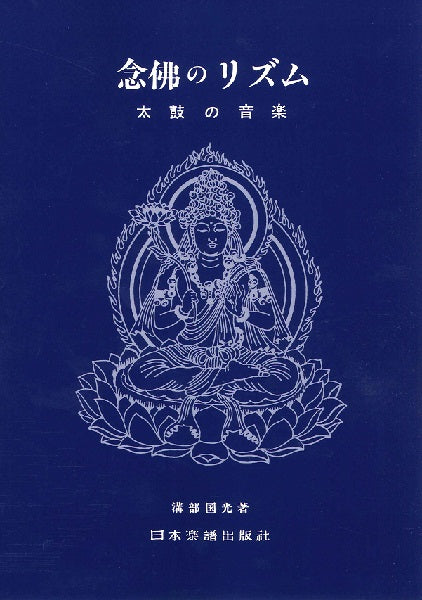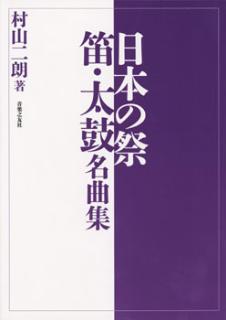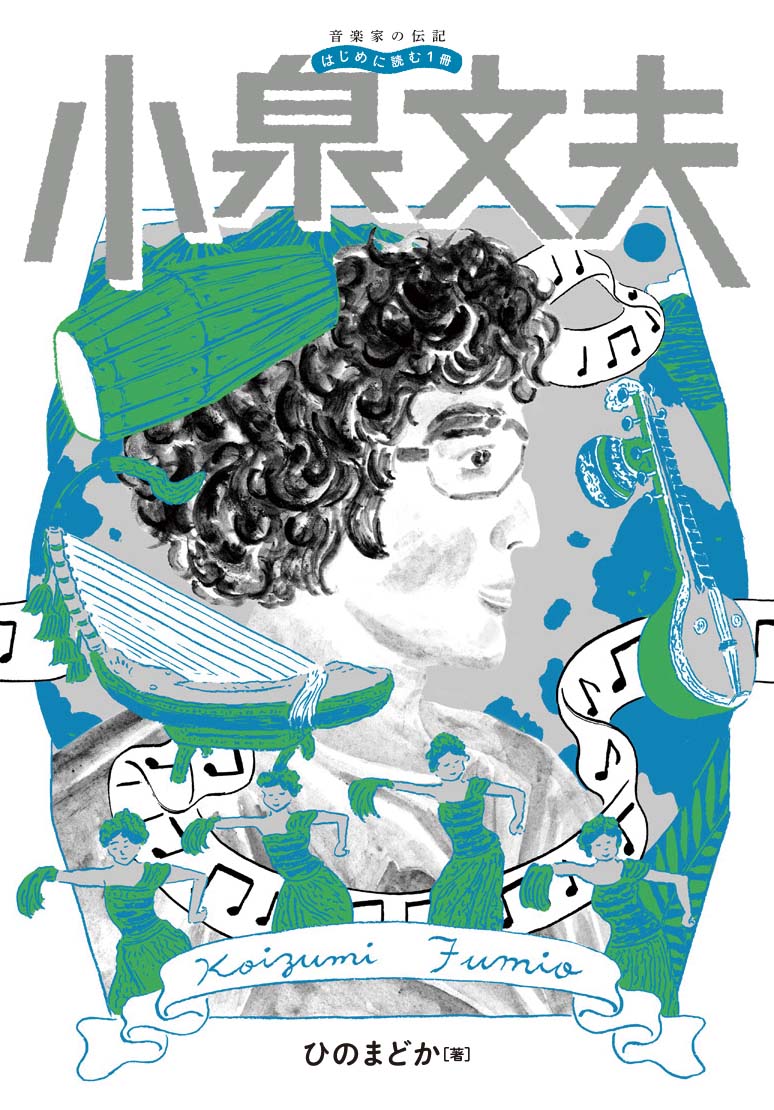日本には数え切れないほど多くの祭り、民俗芸能が存在する。しかし、さまざまな要因から、その存続がいま危ぶまれている。生活様式の変化、少子高齢化、娯楽の多様化、近年ではコロナ禍も祭りの継承に大きな打撃を与えた。不可逆ともいえるこの衰退の流れの中で、ある祭りは歴史に幕を下ろし、ある祭りは継続の道を模索し、またある祭りはこの機に数十年ぶりの復活を遂げた。
なぜ人々はそれでも祭りを必要とするのか。祭りのある場に出向き、土地の歴史を紐解き、地域の人々の声に耳を傾けることで、祭りの意味を明らかにしたいと思った。
「青年たちに健全な娯楽を授ける」ために始まった獅子舞
伝統的な祭りには、ほぼ必ず「由緒」というものが存在する。どれくらいの歴史があるのか、何のために始められたのか、その内容が立派であればあるほど、祭りの権威性や正当性も高まってくる。それゆえに、なかには神話めいた由緒というのも存在するが、一方で、おそらくほぼ何の脚色もなく、事実ベースでその来歴を伝える祭り・民俗芸能もある。その一つが、北海道樺戸郡新十津川町に伝わる「新十津川獅子神楽」だ。新十津川町のホームページには、次のような解説文が記載されている。
明治41年、日露戦争後の人心退廃の風潮を憂う富山県出身者たちが青年たちに健全な娯楽を授けるとともに、併せて村祭りにも寄与しようと獅子神楽の普及を計画し、獅子神楽会を設立。以来、玉置神社(現新十津川神社)の例大祭などで舞いを奉納し、近隣市町に例のない伝統と特色ある郷土芸能として名声を博しました。
(新十津川町役場ホームページより)

新十津川町(北海道)
これ以上ないほどの明確な理由をもってスタートした民俗芸能であることがわかる。より詳しい来歴に関しては、新十津川町獅子神楽保存会が1982(昭和57)年に発行した『獅子神楽七十五年 記念誌』に書かれており、そこには獅子舞を新十津川の町に最初に持ち込んだメンバーの名前まで記載されている。
それだけに、「なぜ、祭りが必要とされたのか」、このテーマを検討する上で、新十津川獅子神楽は格好の題材とも言えそうだ。「青年たちに健全な娯楽を授ける」ために、富山県から移植された獅子舞が、120年近く経ったいま、どうなっているのか。その現場を見に、新十津川町に行ってみることにした。
大水害を機に北海道に大量入植した奈良県十津川村住民たち
内地に住む人間からの視点になってしまうが、北海道は開拓民たちによって拓かれた土地であることは多くの人に知られているところだと思う。では、移住者たちは本土のどういった地域からやってきたのだろうか。地理的に、北海道から近い東北からの移民が多いことは容易に想像できるが、北海道開拓の歴史を伝える施設「野外博物館 北海道開拓の村」ホームページによると、1882(明治15)年~1935(昭和10)年の移住戸数に関しては、1位青森県、2位秋田県に次ぎ、新潟県が3位につけている。以下、富山、石川、岩手、山形、福島、福井が上位を占め、北陸からの出身者も多いことがわかる。
北陸出身者の移住が多いことについては、さまざまな理由が考えられるだろうが、1963(昭和38)年に北海道史編集員を務めた篤志家の片山敬次は「地理的接近と、帆船時代に本道と内地間との交通が、夏季は濃霧、冬は風波の為太平洋岸の航路が開けず、松前との交通は殆んど日本海沿岸の諸港に限られ、従って北陸より商人漁夫等の出稼ぎが多く、自然本道との親しみが深い関係からであらう」と自著『北海道拓殖誌』の中で考察している。
では、新十津川町を開拓したのは誰であったのかというと、初期の開拓者は東北でも、北陸でもなく、その名の通り奈良県の十津川村出身者であった。

十津川村(奈良県)
十津川村というと、地理が好きな方なら名前を聞いたことがあるかもしれない。面積は672.38k㎡。「村」としては日本一の広さを誇る一方、紀伊山脈の只中にあることから、奥山の秘境といった様相を呈している。私も十年ほど前に十津川の盆踊りを体験しに現地を訪れたことがあるが、集落に至る道のりが崖っぷちの細道といった有様で、車が転げ落ちないかとヒヤヒヤしながら座席で硬直していた記憶がある。

山々に囲まれた奈良県十津川村武蔵地区。中央にあるのは盆踊りの櫓(2014)
外界から隔絶された土地ということもあり、十津川村の歩んできた歴史もまた独特である。壬申の乱の時代から朝廷に仕え、長らく「諸税勅免」(勅命によって税が免除されること)の地として優遇されてきた十津川村。豊臣秀吉時代、江戸幕府時代と、国の統治者が変わってもその特権は引き継がれた。また、古来より勤皇の意思が強いことから、明治維新前後には「十津川郷士(ごうし)」を輩出。後に郷士たちは、尊皇攘夷派浪士の一団である天誅組が幕府軍に壊滅させられた「天誅組の変」(1863年)にも関わった。
そんな「ご勅免の地」も、1873(明治6)年の地租改正によって「有租の地」となってから状況は一変。もとより山間部で平地が極めて少なく、農耕の成り立たない土地であった十津川村では、公共事業として杉檜の植栽事業を興そうとしたものの、その矢先となる1889(明治22)年8月に、死者168人、負傷者20人、全壊・流失家屋426戸、半壊家屋184戸という未曾有の大水害が発生。水田の50%、畑20%が流亡、山林被害も甚大な被害となり、生活の根幹も奪われたことから、600戸、2,489人が北海道に移住するに至り、1890(明治23)年には移住先となる「トック原野」(新十津川町役場ホームページによると、「トック」はアイヌ語で「凸起(物)・凸出(物)」の意)に、「新十津川村(1957年に新十津川町に改称)」が誕生した。
故郷との「死別」、開拓地に向かった人々の思い
新十津川獅子神楽が披露される「新十津川神社例大祭」は、毎年日付固定の9月4日に開催される。ネット上ではそれ以上の情報はないため、獅子神楽保存会の事務局となっている教育委員会事務局社会教育グループに電話で連絡を取り、ともかく9月4日の朝に新十津川神社に行けば、神輿の宮出しから祭りを見学できるという情報を得られた。いずれにせよ、東京から行くとなると現地への前乗りは必須らしい。

新千歳空港
3日の午後、成田国際空港から新千歳空港へ。そこから札幌駅を経由して、鈍行列車を乗り継ぎ、本日の目的地である滝川駅を目指す。滝川市は石狩川を挟んで新十津川町に隣接する都市。なぜ、新十津川町に直行しないのかというと、かつてあった札沼線の「新十津川駅」が2020(令和2)年に廃止となり(北海道医療大学~新十津川間)、札幌方面から鉄道で向かうルートが絶たれてしまったからだ。もしこの路線が生きていれば、よりスムーズに新十津川町に行けたはずで(もっとも末期には一日一発着のみで、最終列車が朝の9時台という状況だったようだが……)、いつかニュースで耳にした、北海道の鉄道路線が次々と廃止になっているという報道の現実を、今回の旅ではからずも実感することになった。

公園として整備されている新十津川駅跡地
新千歳空港の駅を発った時点ですでに夕刻となっていたので、滝川市に接近する頃には、車窓の向こうはすっかり闇となっていた。夜間、知らない土地を駆け抜ける鉄道旅というのは、なんとも心細い。寂しさから、ふと明治時代、陸の孤島と呼ばれる土地を出、汽車や船に揺られながら見果てぬ北海道を目指した十津川村の人々に心を寄せてみる。
資料を読むと、その様相はまず出立の状況からして壮絶だ。
いよいよ前夜、各自思い思いの出立祝いをなす。生別であり死別である。送別宴は歌う踊ると賑わう中にも、言いしれぬ異常の感に咽ぶは誰も同じ。自分は後にも家を残し、弟辰二郎も残って住むのでさまででもないが、家を失って移住する人々は感慨もいっそう深い。岡本の源七と辻の四平が佐古の家で、年寄りのことゆえこれが最後だから故郷への置土産にするとて踊ったのは、勇ましくもまた憐れであった。
(中略)
いよいよ伯母子峠一、三四二メートル。住み慣れたふる里との別れである。生涯もう見ることはないかも知れぬ。後にきけばこの時の二百人の中に、誰か頂上で郷里に尻を向けて捲り、ピシャピシャ叩いてみせた夫人がいたとか。そうせずにはおれぬほど切ない別れだったのであろう。泣くよりも辛いおどけである。
(森秀太郎 著ほか『十津川移民 : 懐旧録』より)
当時、水害で十津川村を離れ、新十津川に移住した、とある男性の記述である。ちなみに、十津川村からの移住は三回に分けて行われ、この男性は第一陣として先駆けで北海道に向かった。その旅程は、1889(明治22)年10月18日に故郷を出発。10月22日、大阪の八軒家に着。10月23日に梅田停留所から汽車で神戸へ。24日に神戸港から乗船し、出港。10月28日に小樽港に入港。10月31日に小樽から汽車で発ち、市来知(いちきしり、現・三笠市)からは歩いて移動。空地太(そらちぶと、現・滝川市)に到着したのは11月6日以降となった。
その労苦を思うと、午後に東京を出発して、その日中に新十津川町に到る現代の旅の心細さなど、比べるべくもない。おとなしく電車に揺られていると、夜の10時には滝川駅に到着した。予約していた旅館は駅から徒歩5分ほど。すみやかに投宿して、この日の旅程を終えた。
新十津川の水田開発に貢献した北陸出身者たち

滝川市街地から新十津川町に至る国道451号
例大祭当日はさわやかな、快晴の朝を迎えた。北海道まで来て、雨天に見舞われたらたまったものではない。今日は無事に祭りが開催されるだろうと安心して、新十津川町に向かった。車があればどうということのない道のりだが、滝川駅から歩いて新十津川の市街地まで向かうと40分近くはかかる。目的地の新十津川神社となると、1時間だ。
石狩川を徒歩で超える。石狩川橋の橋長は約630メートル。大自然の中をゆうゆうと流れる大河に、北海道らしいスケールの大きさを実感する。

石狩川。かつては暴れ川としても知られ、明治以来、さまざまな河川開発が行われてきた
橋を渡ると、道が二股に分かれる。Google Mapに従って右側に折れ、しばらく歩くと市街地を抜け、黄金色の稲穂が揺れる、広大な田園風景が眼前に広がった。

石狩川右岸に広がる、広大な水田地帯
農林水産省の統計データによると、米(水稲)の収穫量で、北海道は、新潟県に次ぐ全国2位となる(出典:『令和5年産水陸稲の収穫量』農林水産省)。さらに、新十津川町の米作付面積は、北海道内で5位の3,570ha(平成28年産)。まさに道内有数の米どころなのである。また新十津川における稲作推進の原動力となったのは、北陸の出身者であった。
先述の通り、十津川村民の移住は1890(明治23)年から始まったが、十津川村民の入植地である「トック原野」は、その名の通り、木の生い茂る「原野」であった。林業従事者の多かった十津川人にとって伐採はお手の物だったが、農業には不慣れな部分もあったようで、次第に耕作を放棄し離脱する住民も現れ始めた。
1896(明治29)年になると、十津川村以外の住民がトック原野に移住を開始した。その先駆者となったのが、富山県東砺波郡利賀村(現・富山県南砺市利賀村)から入植してきた高桑長吉である。長吉は四区高台(四区とは、新十津川の古い地域区分名で、現在の大和区と橋本区にまたがる地域)と呼ばれる、現在、新十津川神社(玉置神社)が位置する高台の辺りに入地したが、この土地の地質は排水が悪く、白樺の密生する一帯で耕作には適さないものとされていた。しかし、長吉はこの地質に着目し、水田として利用することを考える。

稲作に長けた北陸出身者らによって、水はけの悪い湿地帯だった土地が水田として開発された
1966(昭和41)年刊行の新十津川町 (北海道) 編『新十津川町史』によると、新十津川の米作は、1892(明治25)年頃から、試作が始まったという。その後、1897(明治30)年の夜盗虫(作物を荒らす害虫)大発生、1898(明治31)年の石狩川の大洪水で新十津川の農業は大きな打撃を受けたが、『獅子神楽七十五年 記念誌』の記述によれば、これらの災難に対しても水稲の被害は軽微だったようで、明治30年以降、水稲の作付けはますます盛んになった。
先述の高桑長吉も、明治36(1903)年に有志らと高台地区の造田を計画し、翌明治37(1904)年に完成。この工事の範囲は高台地区を含む上徳富(かみとっぷ)地域の一区画に過ぎなかったが、その後、徳富川(新十津川町を貫く石狩川の支流)の水量を調査したところ、既存の灌漑用水路を延長拡大することで、上徳富全域を灌漑(耕地に人工的・組織的に給水すること)できることが判明。長吉らは「上徳富土功組合」を結成し、ますます水田農業の進展に力を尽くした。後に長吉は新十津川町における水田開発の功労者として讃えられ、没後、1940(昭和15)年の開村五十年記念式では「特別功労者」として表彰を受けている。
ここまで読んで、「一体、高桑長吉という人物がなんだというんだ」と疑問に思われた方もいるかもしれないが、なにを隠そう、まさに今回のメインテーマである「新十津川獅子神楽」を四区高台という地でスタートさせたのが、長吉の同郷者たちなのである。
獅子と踊子の調和が生み出す視覚的な心地よさ

祭りの装いで華やぐ新十津川神社
新十津川神社に到着すると、境内では出店の準備が進み、はっぴを着た祭り関係者らしき人々も散見された。新十津川神社は十津川村民移住直後の1889(明治24)年に、母村である十津川村玉置神社の分社として建立された神社である。もとは上徳富シスン島(『新十津川町史』によると、島=トゥは「沼」の意)という低地に建てられていたが、1898(明治31)年の石狩川の氾濫を受け、翌年、現在の四区高台に遷宮されたという。
宮出しの儀式が終わると、トラックに載せられた神輿と、おそらく獅子舞のメンバーを載せたバスはどこかに走り去ってしまった。おそらく町内各地を門付けしてまわるのだろうが、いかんせんこちらは徒歩移動なので、ついていくことはままならない。というわけで、事前に事務局の人に教えていただいていた獅子舞披露場所の一つである、十津川町役場前に移動することにした。

神輿がトラックに乗せられ、町内を渡御する
来た道を引き返し、滝川と新十津川を結ぶ「滝新バイパス」を通って町を南進する。徳富川をわたってしばらく歩くと、左手に新十津川町役場が見えてきた。役場前には大きな広場があり、片隅の方には屋台が軒を並べて営業の準備を進めている。神社と並んで、ここも例大祭の会場となるらしい。
しばらくベンチに座って待っていると、大音量で祭囃子らしい音楽が聞こえてきた。

役場の広場に入場してきたトラック
神輿が到着するとともに、バスからはっぴを着た新十津川町獅子神楽保存会のメンバーらしき方々が続々と降りてくる。カメラを胸に構えてその光景を眺めていると、一人の男性が近づいてきた。どうやら数日前に電話で対応いただいた事務局の方らしい。「インタビューをしたいなら、あの人が会長さんだよ」と教えてくれたので、その方に駆け寄り直接取材の打診をする。空き時間に対応していただけるとのことで、ひとまず行き当たりばったりに近いこの取材も道筋がついたようで、安堵をするのであった。
さて、獅子舞である。冒頭で会長の挨拶があったあと、さっそく演舞が始まる。

カラフルな獅子舞の胴体にまず目を引かれた
勇壮な太鼓と、笛の音に合わせて獅子が舞う。新十津川獅子神楽は、いわゆる「百足(ムカデ)獅子」に分類されるもので、カヤ(胴幕)といわれる大きな布の中に五人ほどの人間が入って、中で獅子の胴体を動かす。また先頭の人間は、獅子舞の頭(カシラ)を操作する重要な役目を担う。
獅子の鼻先には常に「踊子(おどりこ)」といわれる役がいて、刀、薙刀(なぎなた)、鎌、棒などさまざまな道具を演目に合わせて持ち替えて、獅子とともに舞う。それは獅子と戦っている様を表していたり、獅子と戯れ遊んでいる様を表していたり、踊りによって意味はさまざまだ。

“サイハイ”と呼ばれる棒を持って舞う踊子
獅子と踊子、この対となる2つの身体が調和することで生み出される「快楽」のようなものがあるように思われる。獅子一体だけの単独の舞であったら、きっとこの心地よさは生まれなかっただろう。獅子と踊子は、あたかも目には見えない柔軟性のある糸で互いに結ばれているかのように、引かれあったり、反発しあったり、交差したり、まるで踊りを通じて会話をしているかのように振る舞う。しかも、一定のリズムに乗って動作は刻まれていくため、その動きは音楽的とも言える。バウンスするかのような踊子の躍動的な舞いは、グルーヴ感をも感じさせる。

獅子と踊子の演舞を支える太鼓と笛のお囃子
と、こんなふうに言葉で論評するのは容易いが、実際にこれを演じるとなると、相当な技術力が求められるに違いない。
短縮で行われたのか、役場前の獅子舞はわりあいあっけなく終わってしまった。このあとは、再び町内をまわって門付けを行いながら新十津川神社に戻って、たっぷりと獅子舞を披露するらしい。近隣にある「新十津川町開拓記念館」を見学したり、物産館で昼食をとったりして時間をつぶしたあと、新十津川神社へとまた歩いて向かった。
富山の山間地から海を越え獅子頭がやってきた
神社の拝殿前にある広場で、再び獅子舞が披露された。注目したいのは、獅子舞の衣装を身にまとった小さな子どもたちが現れたことだ。

小学生による獅子舞演舞
子どもたちは地元・新十津川小学校の小学校3年から6年までの児童で、クラブ活動として獅子舞を保存会から教わり、例大祭や学芸会で披露をしているらしい。オーディエンスは役場前の時よりもさらに膨れ上がり、新十津川獅子神楽が地域の伝統芸能として、しっかりと親しまれていることが感じられた。
それにしても、目の前で繰り広げられている獅子舞が、100年以上も前に遠く離れた富山県から持ち込まれ、その歴史が現在まで続いているということに不思議な感慨を覚える。これは、やはり特別な獅子舞なんだという実感がひしひしと湧き上がってくるのだ。

子どもの獅子舞を見たあとは、大人の演舞がより迫力を増して見える
記事の冒頭で新十津川獅子神楽の由緒に触れたが、この獅子舞が富山県から伝わったのは、1908(明治41)年のことである。その目的に関しては新十津川町役場ホームページでは「日露戦争後の人心退廃の風潮を憂う富山県出身者たちが青年たちに健全な娯楽を授けるとともに」とされているが、『獅子神楽七十五年 記念誌』には、もう少し詳しい状況が記されており、「明治三十七、八年戦役に勝利をおさめたわが国民は(中略)所謂戦争狂とも云うべき驕奢華美の風を好み殊に四区の青壮年は、畑を転じて水田となし、米を売り出すことにより金銭の浪費その止るところを知らず」とされている。
先人たちが苦労して開発した水田の恩恵を、下の世代が何の苦労もなく享受して、浪費を重ねていたのだとすれば、大人たちが苦々しく思うのも無理はない。また獅子舞導入の目的を考える上で、この時期「青年団」といわれる青年組織が全国的に数多く結成された時代でもあることにも留意しておきたい。その成立過程は一様でないが、教育の機会に恵まれない地方の若者たちが自主的に開催した勉強会が母体となったり、若者たちの風紀の乱れを懸念した地元尋常小学校の校長が設立を主導したり、いずれにせよ青年教育の必要性の高まりから生じたムーブメントであることは間違いない。新十津川でも、獅子舞に先立つ1905(明治38)年、四区の青年会長であった東 英治が発起人となって新十津川青年会が結成されており、こういった背景を考えると、「青年たちに健全な娯楽を」という発想の出どころも、なんとなくイメージしやすくなる。
現在、獅子舞の発起人として伝わっているのは中川三之丞、山本十吉、高桑伝次郎の3名だ。記録によると、3名は話し合いの末に同郷の先輩らに相談、「一部の反対有りたるも」多くの賛成を得て、獅子神楽会を結成。その初代会長として推されたのが、先にも触れた水田開発の功労者である高桑長吉であった。
獅子舞の技術は郷里の出身者たちが指導可能であったが、用具も揃えないと獅子舞ができない。そこで発起人の一人、高桑伝次郎が富山県まで出向き、地元で集めた寄付金を元手に、獅子頭、カヤ、カリサン(ハカマ)などの用具を買い揃えたという。

現在、使用されている獅子頭。定期的に新調しているそうだ
獅子舞活動の初期は、先ほどから何度も話題になっている四区高台が活動の中心地となり、メンバーも「高桑一族」のみで行われていた。しかし草創期を支えた若者たちも、やがては妻帯や分家をし、家業が忙しくなるにつれて、獅子舞も一時期よりは沈滞。打開策として新しい入植者にも声をかけメンバーの拡充をはかることになった。また、1920(大正9)年頃から、「新派」と呼ばれる新しい獅子舞の演目が加わったことで、さらなる人員の確保が必要となった。この際は、地域の第四区青年会に協力を要請し解決をはかった。

「新派」の演目では武器を持たず、「サイハイ」と呼ばれる棒や、手ぬぐいなどを手に、獅子と戯れるように踊る
大正期に入ると、獅子神楽は最盛期を迎えた。『獅子神楽七十五年 記念誌』から、この時代の証言を拾っていくと、練習の厳しさを訴える言葉が数多く見られる。練習中は休むことを許されず、棒で叩かれることもあった。絶対服従関係の先輩から厳しく指導され「思い出といえば練習のつらさ」と述懐する発言もある。しかし、そのひたむきさが若者たちの熱意と評価され、地元の祭りには獅子神楽を見に多くの人が詰めかけ、時には他地域の祭りに招待されることもあったという。
獅子舞の技術も極まり「生きている獅子が人間に襲いかかって来るようにすさまじい舞い」だったという証言も残る。地域の子どもたちも獅子舞の真似事をして遊ぶようになったといい、まさに獅子神楽の歴史の中でも、充実した時期だったことがうかがい知れる。

時折、獰猛な表情を見せる獅子
1931(昭和6)年の満州事変を機に、日本全体に戦争の足音が再び忍び寄ってくる。戦時色が濃くなるにつれ、獅子舞の練習も軍隊式の厳しさにエスカレートしていった。第四区の若者たちは、それでも地域の獅子舞を受け継ぐという強い意志で、厳しい練習にも耐えた。しかし、戦局が深まると担い手となる若者たちは戦場にとられ、大戦末期は年寄りも参加し、獅子舞を支えた。終戦の年にも獅子舞は行われたという。
戦後の衰退と保存会の結成、そして高校生も参加
120年近くの歴史を持つ新十津川獅子神楽だが、活動初期の時点ですでに地元青年会に協力を求めていたことからも、「継承問題」とは常に向き合ってきた民俗芸能ともいえる。特に第二次世界大戦は大きな転機となった。
戦争が終わり、やっとにぎやかに祭りを開催できる状況が訪れたが、娯楽文化の多様化や、民主主義という新思潮の影響で、かつての「獅子舞に入らないような者は一人前の青年として認められない」というほどの強制力は薄れ、獅子舞はかつてのような勢いを取り戻すことはなかった。また1960(昭和35)年前後をピークとする若者の村外流出も重なり、担い手はますます減った。この時期は練習会に参加する人数もまばらで、祭り当日も役員が人をかき集めて、ようやく獅子舞が実施できるような状況であったという。かつ獅子舞の用具も古びてきていて修理が必要だったが、そのための予算も不足していた。
一時は獅子舞をやめるかという話し合いも持たれたが、とあるメンバーの「(獅子舞をやめたら)先輩に何と申しひらきする。この年は何とかやり抜こう」という声を受けて再び奮起。人手不足や、財政難といった課題を打開するために、獅子舞を旧四区のみならず、新十津川町全体のものに発展させること、また後継者を地元高校(新十津川農業高等学校)の生徒に求めることが発案され、当時の町長に相談。その結果、1965(昭和40)年8月に、現在まで続く新十津川町獅子神楽保存会が結成されるに至った。
地元高校への働きかけは、保存会設立と同時に始まった。ここで中心的な役割を果たしたのが、現・新十津川町獅子神楽保存会 相談役の高桑政章さん(1946年生)である。

新十津川町獅子神楽保存会 相談役の高桑政章さん
「それこそね、うちの大叔父(高桑伝次郎)が獅子舞を(新十津川に)持ってきたのさ。(その関係で)獅子舞の道具を保管するのもうちでしていて。練習ったら、うちに来て練習して、お祭りの当日も、朝、うちから獅子舞が出発して、神社までの道をみんなで歩いていったんさ」
そう話す政章さんは、獅子舞発祥の旧四区の出身で、子どもの頃から獅子神楽に触れてきた。物心ついた頃は獅子舞に恐怖心を覚えていたが、中学生になると興味を持つようになり、祭りの日は獅子舞についていき、練習会にも参加するようになった。例大祭は日付固定なので、平日に開催されることもあったが、そんな時は学校を休んで獅子舞について歩いた。「無断欠勤みたいなことをね、ははは」と政章さんは笑う。
高校に入った頃から、獅子舞の人手不足が一層深刻化していく。政章さんも、役員と一緒に人集めに参加するうちに、担い手の一人として継承の危機を肌身で感じることになった。定時制4年生になると、保存会が設立。高校生で獅子舞をやってくれる人がいないかという相談を受けた政章さんは、同級生や下級生に声をかけ、学校の協力も経て、校内で「獅子神楽同好会」を結成した。
「たまたまね、同級生で2〜3人獅子舞をやっていたやつがいたんさ。それらを引っ張って同好会を立ち上げた。そして、女の子にも入りたいっていう人がおったからさ、その時までは女の人が獅子神楽に参加することはなかったんだけど、人がいなければ獅子舞が続かないと思って、笛ならいいべって(入ってもらって)、譜面を作って笛を教えて」

獅子舞の演舞で笛を吹く政章さん(右)
地域の伝統的な芸能を継承するために、地元高校生が奮起、というトピックは当時地域のビッグニュースだったようで新聞などで報道されたほか、1970(昭和45)年頃をピークとして校外への出演機会にも数多く恵まれた。一方で、せっかく教えても高校生には町外の子もいるので卒業したあとに担い手として定着しない、踊り手の主体が成人から高校生になったことで獅子舞に勇壮さが失われた、といった新たな課題も現れ、継承問題の難しさがあらためて浮き彫りとなる形となった。
政章さんによると、その後、獅子神楽同好会は学校の方針で解散することになったそうだが、現在の保存会メンバーにも同好会のOBがおり、獅子舞を未来につなぐことには、一定の役割は果たしたものと思われる。
小学校の協力を得て、継承活動を実施
地元高校との連携はなくなったが、並行して行われてきた小学生たちへの獅子舞指導は形を変えながらも現在まで続いている。
「うちらの地区は大和っていうところなんだ。最初、大和地区の子どもたちに獅子舞を教えとったんさ。そしたら大和小学校の先生が練習しているところに来て、獅子神楽を文化祭で子どもたちに踊らせたいから道具を貸してくれないかって言われた。それで(小学生のために)、カヤを作って、頭(かしら)のレプリカを作って先生に貸して。そうやって、小学校として獅子舞をやり出すようになったのが45年くらい前かな」
大和小学校は、2009(平成21)年に廃校。現在は、統合先となった新十津川小学校で立ち上がった「獅子神楽クラブ」で、小学校4年から6年生のメンバーに獅子舞を指導している。小学校が協力してくれることに話が及ぶと、政章さんも「ありがたい話だよねえ」と目を細める。
メンバーの高齢化、担い手不足など、依然として新十津川獅子神楽は、継承の諸問題に直面している。「とにかく人が集まってくれれば……それだけだね」と、政章さん。獅子舞を演じる前にメンバー募集の呼びかけが行われるほか、獅子神楽に関する概略を記したプリントを配布するなど、ささやかな採用活動も行われている。
今年(2024年)はうれしいことに、2名の新規メンバーが加入している。うち一人は早くも踊子として例大祭に参加。話を聞くと年齢は50歳を超えるものの、元気なうちに獅子舞に挑戦してみたいという思いを胸に、保存会の門を叩いたのだとか。こういう話を聞くと、民俗芸能に挑戦するのに、年齢は言い訳にできないなと思う。

最後の役場前での出番に備えて控室で練習を重ねるメンバーたち
また明るいニュースとして、数年前に「七五三」という演目が20年ぶりに復活したというトピックがあった。たまたまメンバーの中に踊りを覚えている人間がいて、おぼろげな記憶をもとにアレンジを加えながら再現したらしい。他にも縁起が悪いという理由で大昔に廃止された「獅子殺し」という30分近くかかる演目がかつてあったそうだが、叶わぬ夢としても、もしいつか復活することがあれば、いち祭りファンとしてはうれしいところだ。

滝川駅前のバスロータリー
滞在3日目の朝。旅館を出て、滝川駅まで向かう。今日は東京に帰る日だ。
1908(明治41)年、獅子舞立ち上げの話がまとまると、発起人の一人である高桑伝次郎は獅子頭などの用具を調達しに、郷里である富山県へと向かった。港のある函館までは汽車で行き来したというが、新十津川駅(旧・中徳富駅)を含む、村内の駅はすべて1931(昭和6)年に開業しているので、おそらく伝次郎は滝川駅(1898年開業)を利用したはずだ。約120年前、獅子舞の道具を携えこの駅に降りた伝次郎には、獅子舞がその後100年以上以上も続くことになるという発想は、頭の片隅にもなかったろう。待ちかねている仲間たちの喜ぶ姿と、何かが始まるというという期待だけで、胸がいっぱいだったに違いない。
町の開拓と発展の歴史の中で受け継がれてきた獅子舞。そこに託された人々の思いに考えを巡らせながら北海道をあとにした。(了)
Text:小野和哉
プロフィール

小野和哉
東京在住のライター/編集者。千葉県船橋市出身。2012年に佃島の盆踊りに参加して衝撃を受け、盆踊りにハマる。盆踊りをはじめ、祭り、郷土芸能、民謡、民俗学、地域などに興味があります。共著に『今日も盆踊り』(タバブックス)。
連絡先:kazuono85@gmail.com
X:hhttps://x.com/koi_dou
https://note.com/kazuono
この記事を読んだ人におすすめの商品