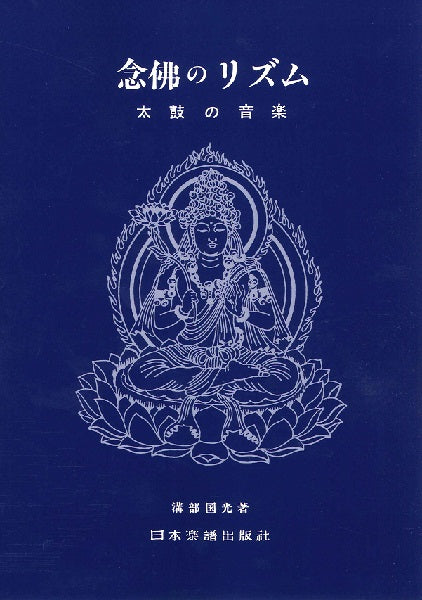日本には数え切れないほど多くの祭り、民俗芸能が存在する。しかし、さまざまな要因から、その存続がいま危ぶまれている。生活様式の変化、少子高齢化、娯楽の多様化、近年ではコロナ禍も祭りの継承に大きな打撃を与えた。不可逆ともいえるこの衰退の流れの中で、ある祭りは歴史に幕を下ろし、ある祭りは継続の道を模索し、またある祭りはこの機に数十年ぶりの復活を遂げた。
なぜ人々はそれでも祭りを必要とするのか。祭りのある場に出向き、土地の歴史を紐解き、地域の人々の声に耳を傾けることで、祭りの意味を明らかにしたいと思った。
田畑を荒らす虫を送り、五穀豊穣を祈願する行事
「虫送り」という行事をご存知だろうか。農薬や殺虫剤のない時代、田畑を荒らす害虫を集落から追い出し、五穀豊穣や無病息災を祈願する風習で、かつては全国各地で行われていた。開催される時期は主に春から夏にかけてで、形式は地域によって少しずつ異なるが、さまざまな資料を見ていくと、藁(わら)でできた人形や松明を手に持ち、笛や太鼓を鳴らしながら人々が行列となって田んぼの畦道などを練り歩くというのが基本形となるようだ。

江戸時代に著された『養蚕秘録』という本の挿絵として描かれた虫送りの様子 出典:『養蚕秘録 上』(国立国会図書館ウェブサイト)
また、地域によっては、歩きながら子どもたちが「虫送りの歌」を歌う。例えば、次のような歌だ。
こりゃ何の踊りじゃい/虫供養の踊りじゃい/村中の者が/観音様に願掛けて/田の虫を送るぞい/畑の虫も送るぞい(滋賀県高島郡マキノ町石庭)
(滋賀県教育委員会『滋賀県の民謡』CDより)
ナームショ/オクンドン/イネムショ/サキンナッテ/ヨロズノムショ/オクンドン(千葉県東金市)
(東金市「東金市デジタル歴史館」より)
いずれも、わらべうたのような単純な旋律であり、歩きながら何度も唱えることに特化したような歌となっている。歌の印象からしてお遊戯的なものを想像するかもしれないが、先人たちは虫送りの効力を信じて、この行事に熱心に取り組んできた。例えば、明治期の農業技術者・古市与一郎(1828~1898)は、その著書『稲作改良法』で、害虫を天災とみなして「舊習」(きゅうしゅう:古くからの風習)である虫送りに頼る人間が多いあまり、人々が科学的な害虫駆除対策に一致団結して取り組めないことを嘆いている。
『稲作改良法』が出版されたのは明治28(1895)年。この時期、すでに学ある人の中では、虫送りが実用性の欠いた悪風であると捉えられていたという事実は興味深い。しかし庶民の間では少し様子が違ったようだ。1990年刊の新十津川町教育委員会 編『新十津川の昔話』によると、明治30(1897)年頃、北海道の新十津川村で、移民たちによって開墾された耕作地が夜盗虫という害虫の大量発生で全滅してしまう事件があった。新十津川住民たちはどうしたかというと、「虫送り」の実施を決定。松明を焚いて、石油缶をガンガン叩きながら、道の四辻にまじないの書かれた棒を立てて歩いたという。
少なくとも明治時代頃までは、庶民の間では虫送りの祈祷が、ただの願掛け以上の意味を持っていたことを示すエピソードだ。
千葉県袖ヶ浦市に伝わる虫送り「野田の虫送り」
多くの地域では虫送りの行事は廃れてしまっているが、いまも全国各地に伝統行事として残ってはいる。私も、関東近郊で3カ所ほど見学したことがあるが、特に印象に残っているのは、千葉県袖ケ浦市で毎年7月31日頃に実施されている「野田の虫送り」(袖ケ浦市指定無形民俗文化財)だ。虫送りがどのような行事かイメージしてもらうために、その様子を少し紹介したい。(2024年7月31日に見学)
虫送りは、地域の子どもたちが主体となるケースが多い。野田の虫送りもそうで、子どもたちがお札の入った神輿を担いで町内を練り歩く。この自然素材だけで作られた神輿が非常にユニークで、竹で作った骨組みにヒノキの枝葉を重ねて胴体とし(かつては杉の葉で作っていたと地元の方は語っておられた)、神輿のてっぺんには乾燥した竹の皮で作られた鳳凰が載せられる。鳳凰は稲穂をくわえており、さながら本物の神輿のようなビジュアルだ。しかし、葉っぱに覆われて見た目がふわふわしているので、どこかゆるキャラのようなかわいさがある。

神輿づくりは大人の仕事ということで、虫送りの当日や前日に制作される
神輿は地域の氏神である野田神社を出発し、集落の50軒ほどの家々を巡る。子どもたちが神輿を担ぐときの掛け声は「ワッショイ、ホーネン」だ。「虫を送るぞ」ではなく、豊作祈願の言葉を唱えているのが面白い。

神輿は軽トラで家の近くまで運ばれ、玄関までの数メートルは子どもたちが担いで歩く
神輿が家の前に着くと「ワー」という掛け声とともに、上下に激しく揉まれる。本来ならこの神輿を地面に落とすという工程が加わるのだが、神輿の損壊を危惧してかこの日は最後の1~2軒でのみでそれが行われた。地元の人に話によると、落とした時の音で虫を追い払うという意味があるらしい

神輿を上げ下げするタイミングを合わせるのが難しいようで、子どもたちも四苦八苦している
神輿を揉むと、家の人がおひねりとしていくらかお金を包んでくれる。このおひねりはあとで、子どもたち同士で分配するらしい。その分配方法も子どもたちにゆだねられているというので、やはり虫送りが子どもたち中心の行事であるということが実感させられる。

訪問した家の人からおひねりを受け取る子ども
野田の集落は田畑が広がる自然豊かな地域だが、耕作放棄されているのか、荒れた土地もチラホラと見かける。少し切ない気持ちで歩いていると、虫送りの行列が止まって、男性が畑の脇に注連(しめ)のついた細い竹を刺す。

虫送りについて調べると、田畑に札を立てるというのも、この行事の一つの典型らしい
すべての家を訪問し終わると、神輿は野田堰という場所まで運ばれる。何をするのか見守っていると、大人たちが神輿を持って石段を降りて行き、そのまま堰の中に神輿を放り投げてしまった。名残惜しむ間もなく「それじゃあお疲れ様でした」と、各自が車に乗って、そそくさとその場を去っていく。水面に裏返って浮かぶ神輿を、私はフェンス越しからしばらくぼんやりと眺めていた。

堰に投げ込まれた神輿
虫籠は、地域の個性が爆発する農村アート作品
袖ヶ浦市では、かつて野田地区以外でも虫送りの行事が行われていたらしいが、時代の流れとともに次々となくなっているという。少子高齢化や娯楽の多様化などの要因で、全国各地のさまざまなお祭りが廃絶の危機に瀕しているが、子どもたち主体の行事ともなれば、少子化のもたらす影響はなお深刻だろう。

会津美里町の田園風景
福島県会津美里町。福島県の西部に位置する自然豊かなこの町にも、一度その歴史にピリオドを打った虫送りがある。福島県会津美里町尾岐(おまた)地区に伝わる「高橋の虫送り」(町指定重要無形民俗文化財)は江戸時代からの歴史を持ち、1966(昭和41)に戦後に保存会が結成されてからはコロナ禍での2年の休止を挟みながらも、毎年7月19日に実施されてきた。
ところが、2024年6月27日に福島民報社のWebサイトに掲載されたニュースによると、虫籠の製作者の高齢化、後継者不足、地域の少子化、農薬の普及などの理由から同年4月に高橋の虫送りを担ってきた保存会が解散。しかし、「地域文化の灯を消すまい」と、地区内外の有志が集まって新団体「高橋の虫送りをつなぐ会」を結成。継承のための活動を始めたというのだ。初年となる2024(令和6)年は虫送り自体の実施は見送るものの、技術継承のために地元小学生たちと虫籠(虫送りで子どもたちが担ぐ用具)づくりは行い、郷土資料館で展示をするそうだ。
高橋の虫送りについては、この報道をもって知ったのであるが、担い手となる組織が解散してもなお、新しい継承団体が立ち上がって伝統を引き継いでいくという話に興味が湧いた。一度、地元の方々が「終わらせる」と決めた祭りを引き受けて復活させるということは、決して容易なことではないだろうし、難しい問題もいろいろとあるのではないかと思う。新団体を立ち上げた真意は何なのか。代表者に話を聞きに行ってみることにした。
東京を早朝に立って、およそ5時間。新幹線とバスを乗り継ぎ、正午ごろに会津美里町にたどり着いた。隣接する会津若松市には、盆踊りや獅子舞を見物するために何度か訪れたことがあるのだが、会津美里町は初めての訪問である。虫籠の展示が行われているのは、新鶴庁舎内にある「会津美里町郷土資料館 さとりあ」という施設だ。2023(令和5)年のオープンということで、まだできて日が浅い。

虫籠の展示が行われた会津美里町の新鶴庁舎
連絡先がわからなかったため「高橋の虫送りをつなぐ会」の代表者とはアポを取れていなかったが、展示会の初日ということもあり、もしかしたら会場で会えるかもしれないという期待があった。果たして、郷土資料館の受付で入場料を払いながら「虫送りの代表の方はいらっしゃいますか?」と聞いてみると、さっきまでいたが今は外に出ている、しばらくしたら戻ってくるはず、ということだったので、虫籠の展示を見ながら待つことにした。
虫籠は、郷土資料館の奥に展示されていた。まず、その造形の独創性に度肝を抜かれる。竹や木の枝を組んで作ったような四角い籠があり、その上に籠全体を覆うように、大きな屋根のような構造物がかぶさっている。屋根からはアジサイの花が無数にぶら下がっており、可憐な雰囲気が漂っている。さらに屋根の上には幣束(へいそく)や、「萬虫送り」「虫おくり」など書かれた紙が刺さっていて、実ににぎやかだ。

かつてはこの籠の中に本物の虫を納めていたという

虫籠は美しく花で装飾され、この地に生きてきた人々の美的センスを感じることができる

取り付けられた紙の一枚には「よろづ虫おくり おまたくぼ」と書かれている
虫籠の本体のデザインからは「虫を追い払ってやろう」という気概はあまり感じられないが、籠の下に目をやると竹槍のような物騒な道具が展示されていて驚く。会場に展示されていた説明書きによると、虫籠を担ぐ際、従者のようにこの槍を持った子どもたちが籠の周りを囲むらしい。それではまるで、殿様の乗った籠を護衛しているようではないか。

槍の先端には、細く割った竹が曲げられた状態で取り付けられている。竹が両側に飛び出している「両槍」と、片方だけ飛び出している「片槍」があるが、その意味はわかっていないらしい
虫籠は一基だけではない。いま紹介した虫籠は尾岐窪(おまたくぼ)地区のもので、高橋の虫送りでは、もう一つ、冑(かぶと)地区という集落からも虫籠が出される。そのデザインがまた尾岐窪とまったく違うもので驚いた。

尾岐窪の虫籠と比べると、野生的な色彩の強い冑の虫籠。もはやアートの域である
冑の虫籠は全面が木の葉に覆われていて、プリミティブな迫力を放っている。尾岐窪地区よりもいくぶんシンプルにも見えるが、虫の乗り物としては、この野趣あふれるデザインがふさわしいようにも思われる。虫籠の上に、「萬虫送り」「虫おくり」と書かれた旗が刺さっているのは、尾岐窪地区の虫籠と変わらない。尾岐窪と冑は隣接する集落ということだが、なぜここまでデザインが変わるのだろうか。虫送りの多様性を、こんな限定的な地域の中でも感じることができるとは。
ところで、2つの虫籠はそれぞれの地区から出発し、最終的に会津美里町を貫く宮川の橋の上で合流する。かつて冑地区では袴を着た各区長が、冑~小山~仁王と虫籠を引き継ぎ宮川まで運んだようだが、時代とともにそういった作法も少しずつ省略され、運搬にもリヤカーや自動車が用いられるようになったらしい。尾岐窪地区では、虫籠のまわりに槍を持った子どもたちが随伴するというのが特徴だ。虫籠のデザインだけでなく、虫送りの形態や作法も地区によって異なるのが面白い。また、虫送りの際は「稲の虫も、タバコの虫も、おくんゾウ」という歌が子どもたちによって歌われる。

尾岐窪地区の虫送りの行列(2023) 提供:片山紀彦

冑地区の虫送りの行列(2023) 提供:片山紀彦
宮川にかかる橋の上で合流した尾岐窪地区と冑地区の虫籠は、近隣寺院の住職による虫供養が行われたあと、橋の上から川に落とされる。この劇的なクライマックスは、堰に投げ入れられる野田の虫送りと共通するところがある。

虫籠を橋から川に投げ入れる瞬間(2016) 提供:片山紀彦
展示会場にあった資料を見ると、橋の周辺では屋台も出て、虫送りの日は多くの人出があったらしい。式典のあとに太鼓や踊りが披露された時期もあったそうで、想像するだけでもそのにぎやかさが伝わってくる。高橋の虫送りは、ただの宗教儀礼としてのみならず、地域住民の楽しみの場として親しまれてきた、詰まるところ、虫送りがなくなるということは、楽しみの場そのものが失われるのに等しい、ということにつながる。

虫送りの日、橋の近くの川岸には灯籠が並べられる(2016) 提供:片山紀彦
虫送りは先人の自然への畏敬の念を想起させてくれる行事
虫籠もたっぷりと堪能し、館内でしばらく待っていると、スタッフの方がやってきて「高橋の虫送りをつなぐ会」の方が戻ってきたと知らせてくれた。さっそく取材の打診をしてみると「もちろん」と快諾いただき、新団体発足の経緯について、詳しくお話を伺うことができた。

高橋の虫送りをつなぐ会 代表の片山紀彦さん(右)と、妻の玲子さん(左)
「いまは夫婦でこっちに住んでいるんですけど、元々僕は神奈川県の出身なんです」。高橋の虫送りをつなぐ会の代表を務める、片山紀彦さんはそのように切り出す。「かみさんの本家がこちらの方にあって、そんな縁から尾岐地区の冑というところに、もう終の住処ということで骨を埋める覚悟で古い家を買いまして。それが17年前くらいのことですね」
移住してきた当初は「無職だったし、やりたいことがはっきりしていなかった」という片山さん。そんな最中に、高橋の虫送りと出合ったことで、その後の人生が一変する。「初めて見たのは、冑に引っ越してから5年目くらいのことですね。それまで、虫送りのこと、最初は耳にも入ってこなかったんですよ。本当に地元の関係者だけでやっている感じで。実際に見たら結構、面白いじゃん!ってなったんですけど、僕は地区の役員でもなかったので、(行事に関わることもなく)その頃はお客さんとして外から見に行くという感じでした」
そんな片山さんが虫送りに関わるようになったきっかけは、“虫送りの歌”だ。
「高橋の虫送りには、子どもたちが合唱する虫送りの歌というものが伝わっているんですけど、歌を覚えている大人がいるうちにCDとして残しておきたいということになったそうです。僕、音楽をやっていた関係で録音機材なんかを持っていたんですけど、そのことを地域の人が聞きつけたようで、協力してくれないかとお声がけがあったんです。それをきっかけに虫送りに深入りするというか、アドバイザーみたいな形で関わるようになったんですね」
高橋の虫送り
高橋虫送り保存会の会長は、毎回各地区の区長が持ち回りで務めることになっている。移住者である片山さんも、いつしか冑地区の区長となり、2023(令和5)年、保存会の会長に就任。いままで以上に深く虫送りに関わることになった。
「実際にやってみると、それまで以上に(虫送りに)のめりこんじゃいましたね」と片山さん。果たして、何が魅力だったのだろうか。「話があっちこっち行って申し訳ないんだけど、僕、もう一つライフワークとして日本自然保護協会※というという団体に所属しているんです。要は自然の大切さを多くの人に知ってもらうための活動をしている団体ですね。そこで自然観察指導員という肩書きをいただいて、学校の森林体験学習の講師なんかをしているんですけど、活動を通じて最近強く感じていることがあって。それは、今年あたりの異常気象時にしてもそうですけど、地球が抱えている環境問題の大元は、人の気持ちがどんどん自然と離れてきちゃっていることに関係あるんじゃないかなと。人間以外の多種多様な生命の調和が地球環境を整えてくれているというのは、これはもう生物学の世界でも常識になっているところではあります。いまある自然を大切にしていかない限り、人間社会の持続なんていうのはもう無理だと思いますし、だからこそ私たちは、もっと自然を身近に感じて、自然を大切に思う感覚をもう一度取り戻さないといけないんじゃないかって」
※ 現在は「国立公園」に指定されている尾瀬(群馬、福島、栃木、新潟の4県にまたがる地域)を、ダム開発から守るため、1949(昭和24)年に結成された尾瀬保存期成同盟を前身とする団体
虫送りは、まさに片山さんにとって、自然を大切に思う気持ちを喚起し、また先人たちの自然に対する畏敬の念を想起させてくれる行事であった。「虫送りという名前もすごいですよね。“虫殺し”とか“殺虫”という言葉で片付けられてしまうようなものを、なぜ“虫送り”としたのか。それって、すごく優しい言い方じゃないですか。しかも虫を駆除するどころか、最後は“供養”までしてしまうんですよ。なぜ送るという表現になり、虫の魂の供養まで行うようになったかというと、それは多分ですけど、古来、日本に暮らしてきた人たちが自然崇拝を基とした宗教観を大切にしてきたからなんじゃないかと思うんですよね」

虫籠が川に流される前に、尾岐窪の龍門寺住職による虫供養の祈祷が行われる(2023) 提供:片山紀彦
地域の技術継承者や地元小学生も巻き込んで、虫送りの再生に挑戦
少子高齢化による後継者不足、担い手のモチベーション低下など、さまざまな要因から、片山さんが保存会会長を務めた2023(令和5)年で保存会は解散、虫送りの伝統もここで途絶える予定だった。しかし、江戸時代から続くという伝統行事を自分たちの代で終わらせていいものか、片山さんの中には葛藤があったという。
「会長の権限を使って保存会の継続を無理強いするということもしたくなかったし、これまで行事を担ってきた地元の方々も、苦渋の決断ではあったのですが、保存会としてはここでひと区切りをつけたいということはおっしゃっていたので、それとはまったく別の話として、保存会の解散が決まった段階で『実は……』と、新たな継承団体を立ち上げる話をさせていただきました」
伝統の行事を仕切り直しという形で再スタートさせることは、決して容易なことではない。まず、新団体結成の初年となる2024(令和6)年は従来通りの開催は見送り、虫籠を作る技術の記録や、協力者を増やしていくことなど、今後虫送りを継承していくためのベースづくりに注力していくことになった。
「実際に動き出したら、うれしい出会いが重なりました。例えば今回、昭和57年に撮影した高橋の虫送りの貴重な映像データが見つかったんですけど、もとは公民館でカビだらけになっていたVHSを、原田虎雄さんという尾岐窪在住の版画家が人知れずデジタル化してくれていたことで残った資料です。僕もいろいろなツテをたどっていったら、この原田さんにたどりつき、結果この映像資料を引き継ぐことになりました。また、これも偶然のタイミングだったんですけど、地区にある宮川小学校という学校の校長先生から、その方は去年赴任してきたばかりの方で、元はこの地域の出身なんですけど、教育として子どもたちに地域に伝統文化に触れさせたいということで、小学4年生の体験学習の場として虫送りに関わらせてもらえないかというご相談をいただきました」

原田虎雄さんは、地元の方に聞き取り調査を行い、虫送り行事のことや、虫籠の作り方などを記録として残している
依頼を受けて、今年(2024年)は小学校の体験学習として、尾岐窪地区の虫籠づくりをここ20年近く一人で担ってきた星 清伍さんに、小学生たちがインタビューを実施。さらに、虫籠づくりに必要な藁ない体験も行われた。

尾岐窪地区の虫籠の制作技術を継承している星 清伍さん(右から二人目) 提供:片山紀彦

藁ない体験の様子(2024) 提供:片山紀彦

龍門寺の山門にたどり着く虫籠(2024) 提供:片山紀彦
完成した虫籠は、川へ流すまでは至らなかったものの、本来祭りが実施されるはずの土用入りの前日7月19日に、子どもたちが龍門寺の参道を、虫籠を担いで運ぶデモンストレーションが行われたほか、住職による虫供養の祈祷も実施された。「地元の人も顔出しをしてくれて、今年もやったんかいとうれしそうにおっしゃっていただきました」と、片山さんの顔もほころぶ。
尾岐地区の行事から、宮川流域の行事として発展させていきたい
最後に、片山さんに今後の展望について聞いてみると、「もう一度、地域の子どもたちを主体とした行事に戻していきたいですね」と答える。「本来は、虫籠も担ぐだけじゃなくて、作ること自体も子どもたちが担っていたんですよ。その狙いとしては、おそらく(虫送りの行事を通じて)責任感を養うとか、農耕をする上での知恵を授かるとか、いわゆる大人になるための通過儀礼の場として、虫送りが位置付けられていたんじゃないかと、私は思うんですよね」

冑地区の虫籠の制作風景(2023) 提供:片山紀彦
とはいえ、その肝心の子どもたちの数も年々減少しているというのが現実だ。事実、片山さんの住んでいる集落も、小学生が1人、中学生が4人という厳しい状況に置かれているとか。
「尾岐地区だけでは子どもたちもいないし、大人たちも『もうやめちまうべ』と思っている人の方が多いくらい。だから、これからは残った有志の人たちと一緒に、少しずつ地域を広げていきたいなと考えています。宮川小学校の名前の由来にもなっている“宮川”という川があるんですけど、この川の流域には虫送り以外にもさまざまな行事やお祭りがあります。永井野という地域でも祭りを復興させようと頑張っている若い人たちがいますし、そういった人たちともジョイントしながら、伝統文化を守っていくようなプロジェクトを構築し、いずれは高橋の虫送りを会津美里町の宝として認めてもらえるような形にできたらと思いますね」
2025(令和7)年の虫送りは、従来通り虫籠の川流しまで実施される想定である。一方で「はっきり言って、これからどうなっていくかわからないところもあるんですよ」と片山さんは本音も漏らす。どれだけ継承活動に力を注いだとしても、やはり少子高齢化・担い手不足という課題をクリアし、一度途絶えかけた伝統行事を復興させるのは、並大抵の仕事ではない。「だからといっても、このまま誰も何もしなかったらそれまでだと思っているので、これから活動していくうちに、いろいろと意見も出てくるでしょうが、ちょっといまが踏ん張りどころだと思って、やれる限り、できうる限りのことはしたいなと思っています」
祭りや伝統行事の廃絶、継承団体の解散、そのようなニュースをたびたび耳にする時代である。しかし、高橋の虫送りのように、思いのある新たな担い手が外部から現れるケースも出てきている。かつては、害虫を駆除し、豊作を祈願する行事として実施されていた虫送り。片山さんはそんな虫送りと出合い、魅了され、過去の歴史を踏まえながらも、「伝統」に新しい解釈と価値を見出し、行動を起こした。そのような継承の形も、今後は主流になってくるかもしれない。
取材のあと、帰りのバスの中で私は片山さんの言葉を思い返していた。
「僕自身やっぱりね、虫送りの活動をやり出してから、すごく楽しいんですよ、本当に。多分、見ていてわかると思うんですけど(笑)」。そこに必要する人がいる限り、きっと祭りはなくなることはないのだろうと、私は思う。
バスが宮川に差し掛かった時、「これがあの……」と思い、急いでスマートフォンを構えた。先ほどまで空を覆っていた雲は晴れ、ファインダーの先には美しい会津美里町の田園風景が広がっていた。(了)

会津美里町を北東から南西にかけて流れる宮川(一級河川)
Text:小野和哉
プロフィール

小野和哉
東京在住のライター/編集者。千葉県船橋市出身。2012年に佃島の盆踊りに参加して衝撃を受け、盆踊りにハマる。盆踊りをはじめ、祭り、郷土芸能、民謡、民俗学、地域などに興味があります。共著に『今日も盆踊り』(タバブックス)。
連絡先:kazuono85@gmail.com
X:hhttps://x.com/koi_dou
https://note.com/kazuono
この記事を読んだ人におすすめの商品