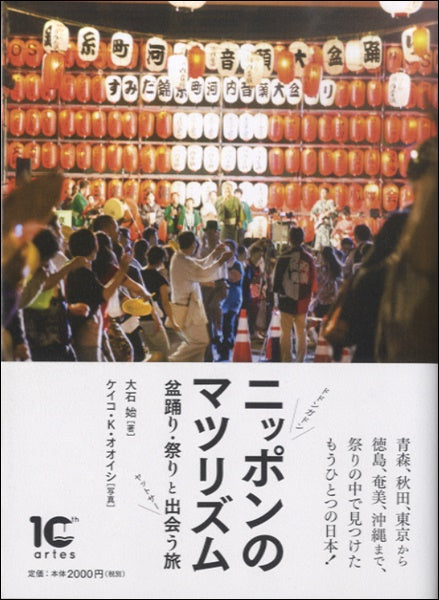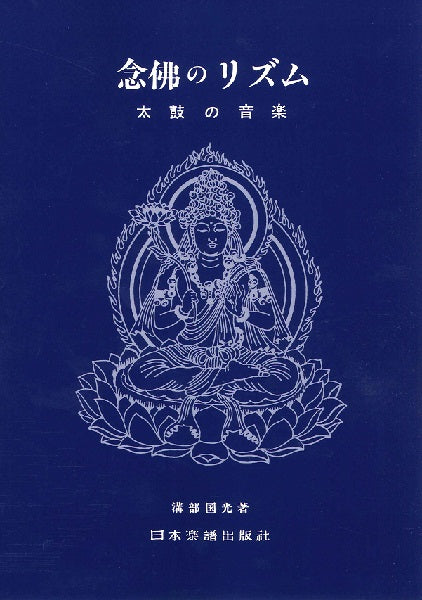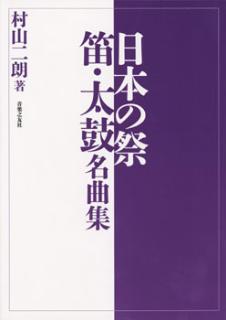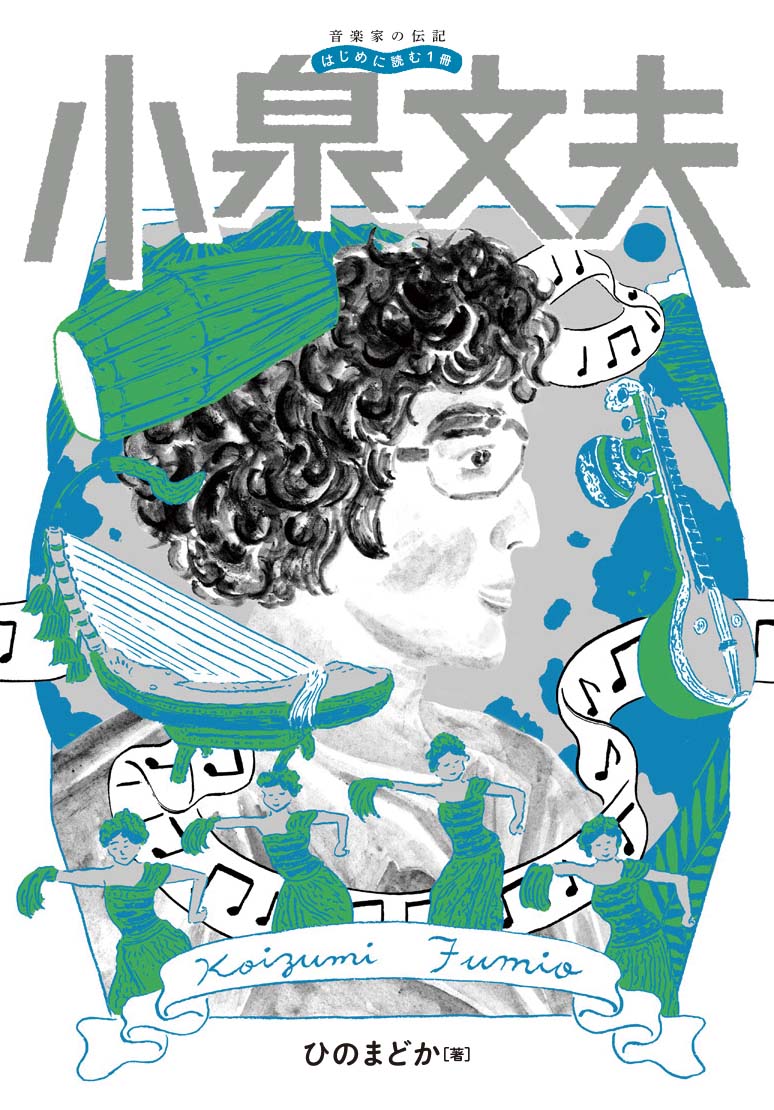日本には数え切れないほど多くの祭り、民俗芸能が存在する。しかし、さまざまな要因から、その存続がいま危ぶまれている。生活様式の変化、少子高齢化、娯楽の多様化、近年ではコロナ禍も祭りの継承に大きな打撃を与えた。不可逆ともいえるこの衰退の流れの中で、ある祭りは歴史に幕を下ろし、ある祭りは継続の道を模索し、またある祭りはこの機に数十年ぶりの復活を遂げた。
なぜ人々はそれでも祭りを必要とするのか。祭りのある場に出向き、土地の歴史を紐解き、地域の人々の声に耳を傾けることで、祭りの意味を明らかにしたいと思った。
「ルーツ」となる祭りを求めて
郷土芸能を追いかけていると、さて自分のルーツとなる祭りとはなんだろう?という疑問に思い至ることがある。自分が生まれ育った土地に根ざした祭りは何だろうか?と考えると、私の地元千葉県には数えの7年目ごとに開催される、周辺市町村をも巻き込んだ大規模な神輿祭りがあるのだが、地域の氏子が中心となる祭りなので、祖父の代から移り住んできた身としては、町内の祭りとはいえ、いつも内側というよりは、外側から鑑賞しているような他人事感があって、無邪気に“ルーツ”とまで呼んでいいか躊躇する部分がある。
ところで厳密にいうと私は、育ちは千葉だが、生まれは岩手だ。母の出身地が三陸地方沿岸の下閉伊郡普代村(しもへいぐんふだいむら)というところで、下閉伊郡と北で接する久慈市内の病院で生まれた。普代村は朝ドラ「あまちゃん」で有名になった三陸鉄道沿線の漁村であり、昆布や鮭、ウニなどの海産物を特産品としてうたっている。子どもの頃は、毎年夏になると家族で帰省して、兄弟で虫かごいっぱいトンボを捕まえたり、従姉妹とテレビゲームで遊んだり、近くの海岸へ浜遊びに行ったり、美しい思い出ばかりの場所だが、思春期を迎えてからは足が遠ざかってしまった(慶弔の機会に何度か訪れてはいる)。
しかし年齢を重ねるにつれて、なぜか自分が生まれた場所に対する郷愁の思いは募っていく。もしかしたら、そこに自分のルーツとなる祭りがあるのかもしれない。そういえば母から、普代村には「鵜鳥(うのとり)神楽」という郷土芸能があることを何度か聞いていた。「自分探しの旅」というわけでもないが、神楽を見に2024年2月、普代村を再び訪れた。
明治三陸大津波を機に「三陸」の地域名が浸透
2月4日の夕方、久慈駅に着く。神楽が行われるのは午前帯なので、前日に前乗りする形となった。駅を出ると、バスロータリーを挟んで「駅前デパート」と呼ばれる老朽化の目立つビルがまず視界に入ってくる。外壁には“潮騒のメモリーズ”と書かれた朝ドラ『あまちゃん』の看板が掲げられている。劇中、久慈駅は「北三陸駅」という名称で登場しており、ドラマの第一話、母に連れられてやってきた主人公の「アキ」が降り立った場所でもある。

久慈駅前にある1965(昭和40)年竣工の「駅前デパート」。『あまちゃん』の劇中にも登場した看板が掲げられている(写真は2019年撮影時のもの)

駅周辺のいたるところに『あまちゃん』の案内板やシャッターアートなどが設置されている(写真は2019年撮影時のもの)
駅前デパートだけではない。駅周辺を散策すると『あまちゃん』関連の看板やら、観光案内板やらがいろいろと目に付く。ドラマの放映は2013(平成25)年のことだが、いまだ根強く愛される作品のようで、10年以上たっても三陸沿岸地域の強力な地域振興、または震災復興のシンボルとして君臨している。
久慈駅前のロータリーにたたずんでいると、停車した車の横で手を振る女性がいた。その顔を認め、急いで近寄って「ご無沙汰しています」と挨拶する。運転席から出てきた男性にも「どうもお願いします」と会釈をした。このご夫妻とは2年前に、東京で毎年開催されている「ふるさと普代会の集い」(上京した普代村の出身者同士で親睦を深める郷友会)で知り合った。

2023年の「ふるさと普代会の集い」の様子。学校の校歌を合唱している一幕
夫のSさんが普代村の出身者で、若くして上京され「ふるさと普代会」の運営にも長く関わっていたが、最近になってご夫婦で普代村にUターンして新生活をスタート。普代と東京をつなぐ架け橋となっている。今回も「鵜鳥神楽を見たい」という私の要望に応えていただき、車での移動から、神楽が公演される地域との交渉まで(後にも説明するが、通常、鵜鳥神楽はイベントや神社の例大祭以外では、地域の人のみしか観覧ができない)、いろいろと旅のコーディネートをしていただいた。本当に感謝に堪えない。
「さあ、乗って」というお言葉に甘えて、乗車する。車は勢いよく走り出し、市街地を抜けると東日本大震災からの復興を目的に整備された真新しい自動車専用道路「野田久慈道路」(2021年開通)に乗り、普代への道を一気に駆け抜けた。
「サケはドル箱」サケ漁で栄えた普代村
普代村は人口2,000人ほどの、岩手県北部海岸に位置する漁業や観光業を主産業とした町である。祖父母も、ともに漁業に従事しており、私が物心つく前に亡くなった祖父は漁師であったし、数年前に亡くなった祖母も、家で畑をやりながら、浜でウニの身を殻から取り出す作業を行っていた姿が、私の記憶の中にも残っている。

生まれて間もない私を抱える祖父(写真右)
生ウニと並んで、普代を代表する海の特産品に挙げられるのが、サケとイクラだ。普代村との接点として個人的に印象深かったのが、毎年秋頃に送られてくる、木製のケースにたっぷりと詰められた冷凍イクラだ。実家にいた頃は、解凍したばかりのイクラをスプーンでざっくりとすくって、ほかほかのご飯に乗せてかき込むのが本当に楽しみだった。
吉村健司・青山潤によると、江戸時代、普代村を治める盛岡藩の財政にとって、漁業生産は重要な位置を占めており、なかでもサケは他領移出を許された七品目のうちの一つでもあった。種々の記録からも、当時からサケはすでに三陸の名産品として認知されていたことがうかがい知れるという。またその年に初めて獲られたサケは「初鮭」として珍重され、藩を通じて江戸に献上、献上者には褒美として米一駄(約120kg)が与えられたそうだ。

普代駅前に設置されていた、魚を持ち上げる猫たちの像(2019)
戦後、普代村では漁港整備の進捗とともに、水産養殖業も盛んとなった。サケ漁は昭和末期から平成初期にかけて最盛期を迎え、1984(昭和59)年発行の『普代村史』(普代村)に掲載された普代村漁協太田部市場扱いのサケの漁獲量データは以下の通りになっている。
51年 149.7トン/48,327匹
52年 297.3トン/794,23匹
53年 523.5トン/14,1626匹
54年 1754.3トン/513,540匹
55年 1091.2トン/338,343匹
※前者は漁獲量、後者は漁獲数
「普代村の場合、サケは普代村水産業のドル箱ともいい得るようになった」という、ちょっと露骨過ぎる普代村史の説明もあながち間違いではなかったようで、景気の良い時期にはサケ御殿とも呼べるような豪邸が建ったとか、村内を外車が走り回っていたとか、海上に大漁を告げる「富来旗(ふらいき)」という大漁旗がいつもはためいていたと、太田部漁港の近くに住む伯母も証言している。
鵜鳥神楽を理解する上で、漁業や漁民という要素は切っても切り離すことはできない。そこで次に、鵜鳥神楽の概要について大まかに解説してみたい。
三陸沿岸地域の漁民の信仰心に支えられた「鵜鳥神楽」
普代村の発行する『観光ガイドブック「青の国」』(2020)には、鵜鳥神楽は次のように説明されている。
鵜鳥神社の神霊を移した獅子頭を権現様とする山伏神楽の一種。毎月1月から3月にかけて、隔年で岩手県久慈市までの「北廻り」、釜石市までの「南廻り」で巡行する神楽です。巡行は各地の神楽宿や公民館などで行われ、全53演目の中から舞が披露され、祈祷が行われます。
(普代村 発行『観光ガイドブック「青の国」』より)
神楽衆たちは1月はじめの「舞立ち」の日に、鵜鳥神社で「権現様」と称する獅子頭に神様を下ろす。その霊験あらたかな権現様をたずさえて、三陸沿岸地域を、神楽をしながら回るのだ(昔は何ヵ月も歩きながら泊まりがけで巡行したようだが、いまは車移動で日帰りが一般的となっている)。
その特異な形態から「廻り神楽」とも呼ばれ、同じく三陸沿岸地域を巡行して回る宮古市の「黒森神楽」とともに、「陸中沿岸地方の廻り神楽」として記録作成等の措置を必要とする無形民俗文化財に選定されている。

鎌倉市建長寺での黒森神楽の公演(2017)
件の鵜鳥神社は、普代村の中心部からやや離れた卯子酉山(うねとりやま)という高台に鎮座している。卯子酉山は山岳信仰の拠点として古くから栄えた霊場で、鵜鳥神楽もまた山間部に居住する修験者(修験道の行者で、山伏ともいう)たちによって始められたらしい。修験者に率いられた神楽衆は、「霞場(かすみば)」という自分たちの縄張りを活動範囲とし、かつては「春祈祷」と称して権現様をたずさえ、家々を一軒ずつ門打ち(人家や商店の門口で祈祷をして廻ること)し、夜は「神楽宿」という神楽を受け入れる家で、夜神楽を演じたという。

鵜鳥神社の本殿は、麓から800メートルほどの山道を歩いた先にある
民俗学者の神田より子は、このような東北における神楽の巡行を指し「獅子をまわし、神楽を演じて霞場をまわって歩くのは、霞主である修験者にとっては重要な仕事であり収入だった」と指摘する。実際、神楽衆は巡行によって、門打ちに対するお布施、その際に供えられる「お散米(さご)」という米、神楽の見物人から供えられる「お花」というお金、神楽宿からの礼金など、さまざまな報酬を得ることができたという。
神楽の巡行が、神楽衆にとってかつては純然たる宗教活動であり、経済活動であったと考えると、他の神楽団体との縄張り争いは相当に熾烈だったのではないかと想像される。では、鵜鳥神楽が昔から三陸地域の広範で活動を行えているのはなぜであろうか。それを可能にしているのが、「うねどりさま」に対する三陸の人々の信仰心である。
鵜鳥神社、別名「うねどりさま」は昔より漁民の信仰が厚く、北は久慈市から、南は釜石市に至る三陸沿岸の漁業関係者が大漁祈願や海上安全を願って参拝に訪れる地である。実際、今回の取材のあとに、毎年旧例4月8日に行われる鵜鳥神社例大祭を訪れた際も、漁業関係者らしき参拝者たちの姿を多く見ることができた。

例大祭の日、遥拝殿に参拝に訪れる人々(2024)
鵜鳥神楽は、そういった三陸沿岸の漁民たちによる信仰心によって支えられてきた。
村を津波から守った二つの防潮堤
話を戻す。普代村には午後5時頃に到着。この日は、先ほども少し話題に出した太田部地区に住む伯母の家に泊まらせてもらい、翌朝の神楽に備えて早めに就寝した。
朝。出発まで時間があったので、漁港のあたりを散歩してみる。

太田名部防潮堤
港に向かって歩いていくと、まず目に入ってくるのが、漁港と集落を隔てる大きな堤防だ。太田名部防潮堤は、1967(昭和42)年に竣工した高さ15.5メートルの堤防である。実は東北地方で甚大な被害を出した2011(平成23)年の東日本大震災の際、普代村ではこの太田名部防潮堤と、普代川に設置された普代水門が機能したために、漁港はすべて破壊されたものの、村内の人的被害を死者0、行方不明者1に抑えることができた。なので普代に住む私の親戚も幸い全員無事だったのだが、大学の卒業旅行で沖縄に出かけていた従姉妹は混乱下の普代村に帰ることもままならず、千葉の私の実家に数日間滞在するという出来事があった。

防潮堤には、津波の到達高が生々しく刻まれている
水門と堤防は、10期40年(1947〜1987)という長きにわたり普代村の村長を務めた和村幸得(わむらこうとく)の尽力で建設された。震災伝承ネットワーク協議会事務局のWebサイトには次のような建設の経緯が書かれている。
昭和8年の津波を経験した元村長は、明治29年の津波で記録された15.2メートルの高さにこだわった。財源や土地の活用に国からも村民からも反対の声が上がったが「二度あったことは、三度あってはならない」と反対の声を説得し、高さ15.5メートルの普代水門と太田名部防潮堤を実現させた。
(「震災伝承ネットワーク協議会事務局」ホームページより)

東日本大震災時に、集落の人々を守った普代水門
1896(明治29)年の津波については先にも触れたが(明治三陸大津波)、それ以降にも普代村では記録に残る大津波があった。それが、和村が体験したという昭和8(1933)年3月3日に発生した「昭和三陸大津波」だ。太田名部地区だけで196名の死者を出した明治三陸大津波から37年、復興の途上にあった集落を再び津波が飲み込んだ。
伯母の夫(つまり私の伯父)である亡き太田茂美が編纂に関わった郷土誌『太田名部物語 この地に生きたすべての人に』には、「津波の音はただの音ではなく、飛行機が低空で飛んだ時のような、うなるような音で、津波の速さは百五十キロ、あっというまに集落は波にのまれた」「瓦礫の下から『助けでくれ』と女の人たちの叫ぶ声が恐ろしかった」など、当時震災を体験した当事者の生々しい証言が記録されている。

『太田部物語』の中でも震災の歴史については大きなトピックとして取り上げられている
東日本大震災が起こった際、私は子どもの頃に普代村で津波の記念碑(大海嘯〔だいかいしょう〕記念)を見させてもらったことを思い出した。1933(昭和8)年に建てられたその碑には「大地震の後には津波が来る」「津波に追はれたら何処でもここくらいの高い所へ」などの警鐘が刻まれている。当時はピンと来ていなかったが、その碑に先人たちの切実な思いが込められていたことを、大人になってから知ることになった。

太田名部漁港から沖に出る一艘の漁船

子どもの頃に遊んだ普代浜。かつて海岸林が生い茂っていたが、大津波でさらわれ、いまは「普代浜園地キラウミ海水浴場」として整備されている
震災があったあとも、私は普代の土を数年間踏むことがなかった。震災で変わってしまった思い出の地を直視するのが怖かったという気持ちも、どこかにあったと思う。しかし40歳も間近になってから、鵜鳥神楽という芸能が私を再びこの地へと誘った。郷土芸能がつながりを取り戻すきっかけをつくってくれた、といっても過言ではない。
門打ちから舞込み、そして神楽が始まる
Sさんの運転で、普代村の堀内という集落に向かう。同じ村内でも、自分にとってはおそらく初めて訪れる場所だ。会場となる村の集会所に入ると、すでに神楽衆が到着して、着替えなどの準備を進めてくれていた。Sさんが地区の方と話されている。基本的には村の人にしか公開していない催しだが、今回は部外者の私が見学できるようにSさんが便宜を図ってくれた。「じゃあ、2時間後くらいに戻ってくるね」と、Sさんは車で去っていく。
巡行の前に、まず神楽の一行は集落内で門打ちを行う。今回は車で高台まで移動し、2件の家を訪問した。

門打ちの様子
家主にうながされて神楽衆が家の中に入ると、獅子頭、つまり権現様を手にした男性二人が、手平鉦(てびらがね)と笛、や太鼓の音に合わせて舞い始めた。いや、舞いというより、全身を使った「祈り」という言葉がふさわしいかもしれない。舞いが終わると、獅子頭で家の人たちの頭を順番に噛んでいく。それが終わると神楽衆は家を辞して、次の家へと門打ちに向かう。

海を臨みながら、集落を歩く神楽衆一行

集落の氏神の元へ行って、ここでもまた舞いを行う
再び一行は神楽宿となる集会所まで戻る。会場に入る前に、まずは建物の入り口で「舞込み」を行う。これは神楽宿に入る際に必ず行われる儀礼らしい。

錫杖(しゃくじょう)や扇を手に舞われる「ショシャ舞」

ショシャ舞のあとには「権現舞」が舞われる

権現前の最中に玄関の前に火を用意する。権現様をかぶったままこの火を踏むことで、火伏せ(火災を防ぐこと)になるという
神楽のプログラムは、昔からの仕来りに則って構成されている。すべてに手順に意味があり、すべての動作に意味がある、神楽衆の一挙手一投足を観察していると、自ずとそのことがわかってくる。

宿に入ると権現様を会場の隅に安置して、全員で拝む

権現様には供物として「しっとぎ」という米で作られた餅をくわえさせる
神楽を通じて、観客は「神」と出会う
いよいよ神楽衆が座に揃い、本格的な舞いがスタートする。鵜鳥神楽には53の演目が伝わっており、そこから選ばれた10種ほどを組み合わせて2~3時間にわたり神楽が披露される。なかでも「役舞(やくまい)」と呼ばれる演目に関しては、必ず神楽で演じられることになっている(一部、演じられていないものもある)。

会場の様子
さまざまな面や装束で神話上の人物に扮した神楽衆が次々と舞台に現れ、舞いを披露していく。舞いの最中は絶え間なく、笛、鉦、太鼓の伴奏が鳴り響き、独特の旋律にともなわれ観衆は神楽の世界へと誘われていく。

最初に登場し、場を清める「清祓(きよはらい)」

「岩長姫」。素戔嗚尊(すさのおのみこと)に退治されたヤマタノオロチの霊が形を変えた姿

「鞍馬」。牛若丸と弁慶の戦いが演じられる
最初は神聖な儀式に立ち会っているような緊張感も漂っていたが、神楽が進行するにつれ、まるで演劇や大衆演芸を見ているようなワクワクした気持ちでステージを見つめている自分に気づく。今風の言い方をすれば、神話上の人気キャラクターが活躍する「2.5次元ミュージカル」(アニメや漫画を原作・原案とした舞台のこと。3次元と2次元の間をとって「2.5次元」と称している)を観ているような感覚だろうか。
コミカル要素もふんだんに盛り込まれた鵜鳥神楽。この日、最も観客の笑いを誘ったのは「日本武尊(やまとたける)」の演目だろう。岩長姫が鬼の面をした大蛇へと姿を変え、ヤマトタケルと戦いを演じる。何度斬られてもめげない大蛇はついに客席へと逃走し、観客と戯れたり、子どもをさらおうとしたり、供物の日本酒を勝手に飲もうとしたりと、縦横無尽に暴れ回る。その間、とにかく客席では笑いが絶えない。

襲いかかった子どもに返り討ちにあう大蛇

恵比寿が鯛を釣るまでの所作を演じる「恵比寿舞」。舞台に子どもを上げて、一緒に釣りを楽しんでいる微笑ましい光景
神田より子は、神楽が演じられる場において最も大切なコミュニケーションは、演者と観客との間のものであると指摘する。
神楽衆が演じる超自然界や神話世界の存在が、我々に直接語りかけてきてくれる場が神楽宿である。神楽を見にゆくという行為を通して、我々は居ながらにして神と出会うことができるのである。そうした心や気持ちを安定させ、満足させ、豊かにさせてもらうために、人々は報謝の気持ちをあらわすのであろう。
(「宮古市史 民俗編 下巻」より)

「山の神」。山の神が降りてきて厄災を祓う。鵜鳥神楽において最も重要な舞いであるという
地域の人々の信仰心に深く根付きながら、娯楽としての側面も強い鵜鳥神楽。神楽衆を、人々を楽しませるプロフェッショナルととらえれば、「昔は、神楽衆は行く先々の女性にモテた」という逸話もうなずけるものがある。娯楽の少ない時代、三陸沿岸の人々は一年に一度訪れる神楽をどれくらい心待ちにしただろうか。春を待ちながら、神楽衆たちの到来に熱い期待を膨らませたに違いない。
子どもの頃から憧れた鵜鳥神楽
気になることがあった。鵜鳥神楽を演じているのは、どういう人たちなんだろうか。この神懸かり的な舞いを継承している人たちとは? 2024年度の「ふるさと普代会の集い」に、はるばる普代から鵜鳥神楽が来ることになり、そのタイミングで神楽衆の若手筆頭と噂される、鵜鳥神楽保存会の笹山英幸(29)さんにお話を聞くことにした。

笹山英幸さん
「もう本当に(メンバーの出身地や住まいは)バラバラですよ。大槌、釜石、盛岡……もちろん普代出身のメンバーもいます」
鵜鳥神楽が特殊であるのは、普代村の芸能だからといって、普代の人が演じているというわけではないということだ。
鵜鳥神社の権現様をご神体として奉じていながらも、神楽衆は直接鵜鳥神社に所属してはいない。普代村出身者でなければいけないという縛りは元よりなく、かつて構成員の多くが隣村の田野畑村の人々であったというし、なんなら神楽の巡行先でメンバーをスカウトすることもあるくらいだという。かくいう笹山さんも、出身は普代ではなく、南廻り巡行の最南端に位置する釜石市の箱崎白浜だ。

現メンバーの中にも巡行先でスカウトされた中学生がいる
「子どもの頃は、妹とずっと門打ちについて回っていました。普通の子どもは30分ぐらいで飽きちゃうんですけど、僕らは夜までずっとくっついていって。夜の神楽も二晩とも見にいってましたね。(当時を振り返って)異常だったって言われますよ(笑)」
子ども心に鵜鳥神楽のどこに惹かれたのかと聞くと、笹山さんは「神楽そのものですね」と答える。
「当時のメンバーがすごかったんですよ。舞いも、仕組み(セリフのある劇仕立ての演目)も、何やってもとんでもなく凄まじい。いまのメンバーはもう全然、足元にも及ばないです」
5歳から神楽に魅了され、小学生の時には神楽衆に手平鉦を貸してもらって、正式メンバーではないながらも巡行にも参加。また10歳になる頃には、箱崎白浜の神楽宿が宿主の高齢化によって廃止、神楽衆からの依頼を受け、笹山さんの実家が神楽宿を引き継ぐという、まさに神楽に導かれるような出来事もあった。
神楽デビューは高校2年生のときのこと。2012年、東日本大震災の被災地支援の一環として、鵜鳥神楽は関西に遠征公演をする機会があった。当時かわいがってくれていた「師匠」に誘われ、笹山さんも現地に出向くことになったが、急遽、花巻空港のトイレで舞いのレクチャーを受けたあと、現地でステージに放り出され、電撃的な神楽デビューを飾ることになった。
「まあまあの、いじめですよね(笑)。(舞台では)頭真っ白で恥ずかしかったし、ストレスもありましたけど、やっぱり憧れていた人たちと同じ着物を着て、同じ舞台に立つということにはすごく喜びを感じましたね」

2024年の鵜鳥神楽例大祭で「山の神」を演じる笹山さん
神楽の正式メンバーとして認められた笹山さんは、高校卒業後に普代村役場に就職、普代で働きながら、神楽衆を務めることになった。順風満帆とも言えそうだが、神楽衆としてデビューしてからわずか一年後、師匠として慕っていた人が若くして急逝してしまうという不幸にも見舞われた。
「その方は、職場の上司でもあったので、本当に公私ともにお世話になりました。6、7歳くらいの頃から毎年年賀状をもらっていましたし、亡くなった年の年賀状にも『今年こそは榊葉(という演目)覚えようね』と手書きでメッセージをいただいていたんですけど……。亡くなった時はどうしたらいいかわからなくて、正直(神楽を)やめようとも思いました。でも奥様から葬儀で弔辞をやってほしいと頼まれ、その文面を考えているときに、『神楽を引き継ぐ』という言葉がたまたま自分の中から出てきたんです。それ以前にも神楽で悩んでいた時期があったんですけど、その際には師匠から『俺は75まで神楽やりたいから手伝ってくれ』という言葉をいただきました。葬儀までの数日間に、自然とその言葉を思い出して『せめて自分も75歳まではやろう』となったんだと思います」
「神楽をやっている光景」を保存していきたい
鵜鳥神楽も、全国の祭りや民俗芸能の例に漏れず、継承問題に直面している。切実なのは神楽を上演する「宿」の数が年々減っていることだ。
「いまは、北廻りは5箇所、南廻りは11箇所ですね。昔は、南だけでも、いまの2倍も3倍も宿があったそうです。震災が関係しているか? もちろん、被災してしまった宿はあるんですけど、一番の大きな要因は宿主の高齢化ですね。うちの実家も神楽宿なんですけど、宿ってすごい負担がかかるんですよ。神楽衆にご飯を用意したり、観に来るお客さんにお茶菓子を用意したり、経済的にも体力的にも負担が大きい中で、跡取りのいないおじいちゃんおばあちゃんだけで暮らす家で神楽衆を受け入れられるかとなると、相当難しいですよね。神様を満足に迎えられないということで、今年で最後に、というお宅も近年いくつかありました」
現在の神楽衆は笹山さんを含め、実際の巡行で神楽を見て憧れを抱き、加入を志願したメンバーがほとんどだ。つまり巡行は人材発掘をする上で重要な機会ともなっているのだが、宿が減ってしまっては神楽を「見る」機会も失われ、人材獲得も困難になっていく。近年、鵜鳥神楽では高齢化に起因するベテラン勢の引退が相次いでいることもあり、神楽衆の拡充と育成を目指す笹山さんらにとって、この状況は一層大きな死活問題となっている。
それならば、ネットなどで広く新規メンバーを募ればいいのではないかという声も聞こえてきそうだが、2~3時間も舞い続ける過酷さを知らないまま加入してしまうと「こんなはずではなかった」というミスマッチが起こりやすく、やはり一度は巡行などで神楽のリアルな現場を見ていることが望ましいと笹山さんは言う。
また、神楽宿の価値というのは、もちろん単に神楽衆リクルートの場であるというだけではない。
「保存会という言葉の“保存”の意味について自分なりに考えた時に、神楽の演目や、しきたりや儀式の保存というのはもう大前提だと思っていて、じゃあ一番の保存って何かというと、“神楽をやっている光景の保存”だと思っているんですよね。神楽を見る人がいなければ、もうそれは神楽をやっていることにならないんです。だから神楽をやる側だけじゃなくて、見る側の保存も大事というか」

笑顔で神楽を鑑賞する、堀内集落の人々
神楽をやっている景色を保存していくためには、もちろん神楽を上演できる場を増やしていくことも大事であるし、より多くの人に神楽を見に来てもらえるように、自分たちの技術をより磨いていくことも必要になってくると笹山さんは言う。
「芸がすべてではないと言いつつ、レベルの高い芸を追求していかないと、見る人は減っていってしまうと思うんですよ。民俗芸能にますます目が向けられているいまの時代だからこそ、こんな言い方したらあれですけど、他の団体と比べても明らかに光っていなければ、これからは多分生き残れません。埋もれてしまわないよう、自分自身成長しなければいけないし、後輩も育てなければいけない。技術の研鑽をして、名前を聞いたら“あれね”と、すぐイメージしてもらえるくらい、鵜鳥神楽の存在を広めていきたいと思っています」

堀内巡行の舞込みで太鼓を打つ笹山さん
笹山さんとの会話の中で、印象的な瞬間があった。少子高齢化やコロナ禍などの影響で、祭りを続けることが困難な世の中において、それでもなぜ人は祭りを続けていこうとするのだろうか。そのような話を聞こうと思って、「祭りを終わらせるという地元の人たちの判断も、それはそれで尊重すべきだと思うんですが……」と切り出すと、笹山さん「自分は尊重すべきだとは思わないですね」と言葉をさえぎるように言い放った。
「形を変えててでも残した方がいいと、自分は思うんですよ。本来のやり方は、伝えていけばいい。例えば、鵜鳥神社の例大祭は毎年旧暦4月8日にやっているんですけど、いまのお祭りって基本的に土日に日をずらしてやるじゃないですか。鵜鳥神社はまだそうなっていないですけど、平日に実施するのが負担であるとなったら、土日にやればいい。日にちを変えたとしても、旧暦4月8日にやるのが本来の形なんだよということを伝えていけば、それでいいと思うんです」
もちろん何から何まで変えていいという話ではない。「時代錯誤かもしれませんが」と笹山さんは前置きしながら、鵜鳥神楽の巡行では昔のやり方の通り、神楽衆に女性メンバーは参加させていないと言う(巡行期間以外のイベントなどでは女性メンバーも参加している)。しかし神楽を続けていくためにも、時代に合わせて変えるべきものは、柔軟に変えていいというのが笹山さんの意見だ。
「先人たちが長い年月をかけて紡いできた歴史を、自分たちの代で終わらせてしまうのは、めちゃくちゃダサいと思っていて。自分たちの役割は、何世代にもわたる歴史の“分厚いノート”にほんの数行を書き加える程度の短い期間に過ぎないんですよ。その歴史が自分たちの代で途切れ、そこから先が白紙になってしまうなんて、これほど悲しいことはありません。もったいないじゃないですか、こんないい文化があるのに(なくしてしまうのは)」

「ふるさと普代会の集い」での恵比寿舞の様子(2024)
インタビューを終えたあとも、笹山さんの言葉の一つ一つが頭の中をぐるぐると回って離れなかった。
神楽を見つめる祖父の姿に自分を重ねる
印象的な写真がある。先ほどの引用した『太田名部物語』に掲載されていてた、普代村太田名部での神楽の様子を写した写真だ。撮影年は1974(昭和49)年とクレジットされているが、さまざまな供物を手にした人々が恵比寿を囲む様子から、当時の興奮と熱気が伝わってくる。

「神楽に酔いしれる人々」とキャプションの入った写真
この写真を見た母が「左側の白い帽子で後ろ向きの痩せた人、多分おじいちゃんだよ」と教えてくれた。「じいちゃんは、本当は神楽をやりたかったけど、ずっと船乗りだったからやることができなかった。だから恵比寿舞になると、鯛を持つ役を嬉しそうにやってたよ」
写真の中で神楽を見つめるその男性の姿は、祭りの当事者でないながらも、祭りを追いかけ続ける自分そのもののようにも思えた。この光景をなくしたくない、そのために自分ができることはなんだろうか。(了)
Text:小野和哉
プロフィール

小野和哉
東京在住のライター/編集者。千葉県船橋市出身。2012年に佃島の盆踊りに参加して衝撃を受け、盆踊りにハマる。盆踊りをはじめ、祭り、郷土芸能、民謡、民俗学、地域などに興味があります。共著に『今日も盆踊り』(タバブックス)。
連絡先:kazuono85@gmail.com
X:hhttps://x.com/koi_dou
https://note.com/kazuono
この記事を読んだ人におすすめの商品