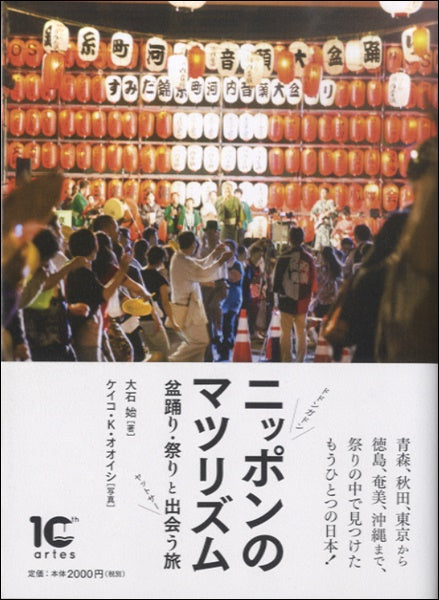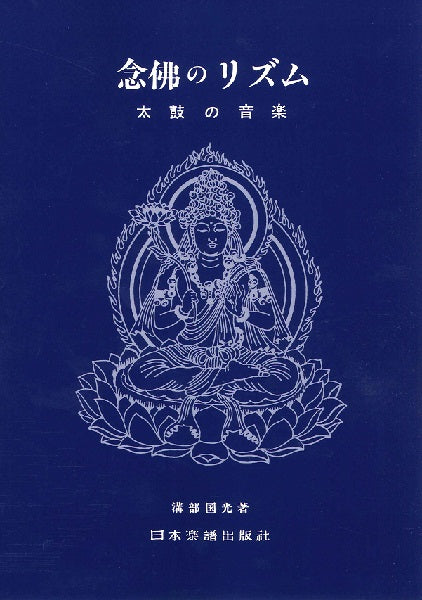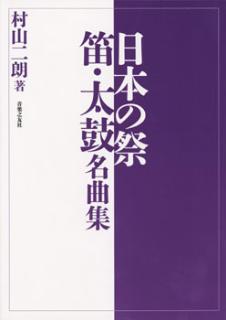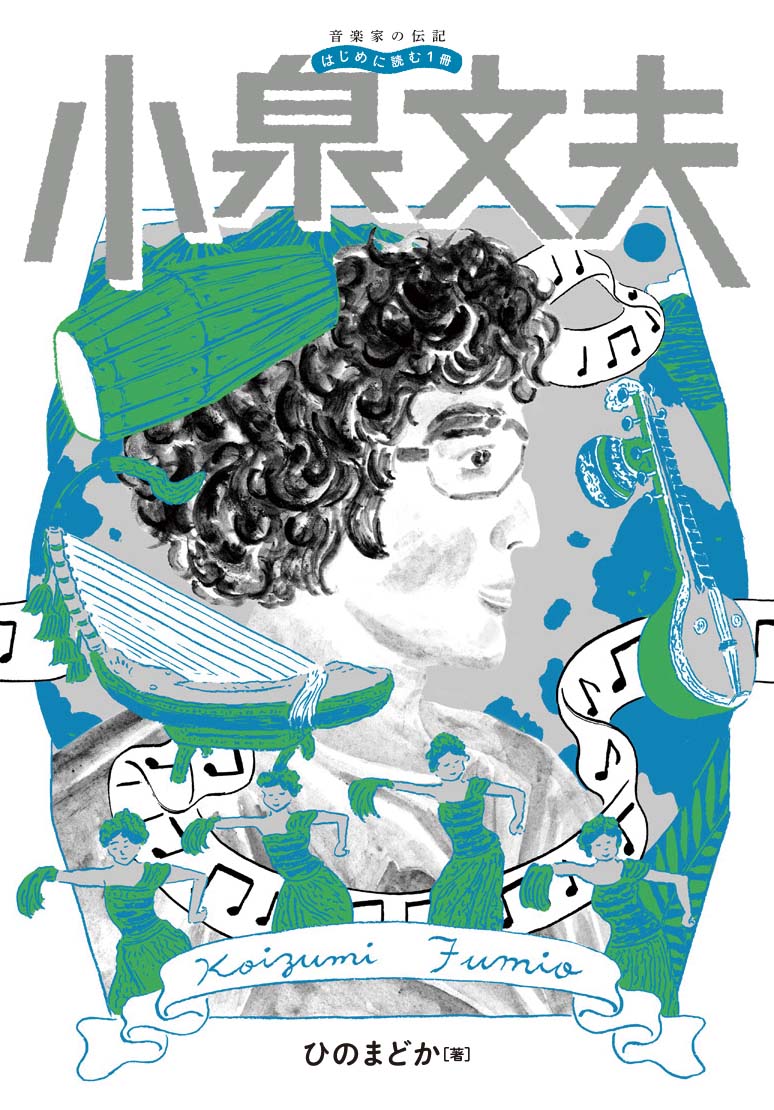日本には数え切れないほど多くの祭り、民俗芸能が存在する。しかし、さまざまな要因から、その存続がいま危ぶまれている。生活様式の変化、少子高齢化、娯楽の多様化、近年ではコロナ禍も祭りの継承に大きな打撃を与えた。不可逆ともいえるこの衰退の流れの中で、ある祭りは歴史に幕を下ろし、ある祭りは継続の道を模索し、またある祭りはこの機に数十年ぶりの復活を遂げた。
なぜ人々はそれでも祭りを必要とするのか。祭りのある場に出向き、土地の歴史を紐解き、地域の人々の声に耳を傾けることで、祭りの意味を明らかにしたいと思った。
徹夜で踊る山里の盆踊り
「昔は朝まで踊り明かしたもんだよ」
全国に盆踊り行脚を重ねていると、地元の人からそんな話をよく聞かされる。その昔は、むしろ徹夜で踊るのが盆踊りのデフォルトであったらしい。しかし、いまでも徹夜おどりを実施している「伝統的」な盆踊りを、私は4例しか知らない。その一つが、長野県下伊那郡阿南町新野(にいの)地区に伝わる「新野の盆踊り」だ。開催時期は毎年8月の14日〜16日で、現在でも毎晩夜9時から翌朝6〜7時頃まで踊られている。
新野は長野県の南端、標高1000〜1100メートルの山々に囲まれた高原の盆地に位置する山間の集落だ。そんな奥山の山村に、昔ながらの形を残しながら朝まで踊られる盆踊りがあると聞けば、誰だって興味を抱かずにはいられないだろう。

冬の新野高原 提供:金原渚
私が初めて新野の盆踊りを体験したのは、2015(平成27)年の夏である。当時は盆踊りにハマってまだ間もない時期で、知的好奇心に突き動かされるまま、全国の面白そうな盆踊りに積極的に足を運んでいた。新野の盆踊りに惹かれたのは、「徹夜で踊る」という点に興味を引かれたからだ。実際に訪れてみると、それは非常に衝撃的で、忘れがたい体験となった。一度きりでは、この祭りのすべてを理解できたとは到底思えず、「一体、あれは何だったのだろうか」と考え、翌年も再び足を運んだ。いまでは、年に一度でも参加しないと気がすまないほど好きな盆踊りとなっている。

筆者が初めて新野の盆踊りに参加した際の写真。一晩中雨に降られた
10年通う中で、個人的に最も大きな「事件」だったのは、コロナ禍によって2020年(令和2年)と2021年(令和3年)の盆踊りが中止になったことだ。台風が来ても決行され、終戦の年ですら踊られたという新野の盆踊りが、止まった。一ファンである私にとっても大きな出来事だったが、地元の人々にとっては、さらに深い喪失感をともなうものだったに違いない。
ネガティブな話題だけではない。2022(令和4)年にはユネスコ無形文化遺産に「風流踊」の一つとして登録された。さらに2023(令和5)年には、4年ぶりに制限なし(前年の2022年はマスク着用、手指消毒、踊り中の2mの距離確保、また一部行事内容の変更など、さまざまな制限を設けた上で盆踊りが開催された)で盆踊りが開催されることになった。この祭りはこれからどこへ向かうことになるのか。私にとっては10年目の節目となるいま、新野の盆踊りの現在地を確認してみたいと思った。
音頭取りと踊り子の掛け合いで生まれる一体感
まず「新野の盆踊り」とはどのような盆踊りなのだろうか。地元では「500年の歴史がある」と伝えられているが、その存在が全国的に認知されるようになったのは大正時代になってからのことである。決して交通の便がいいとは言えない信州の山奥の村で盆踊りが盛大に開催されている。そんな話を耳にした民俗学者の柳田國男が、1926(大正15)年、舞踊研究家の小寺融吉とともに新野を訪れ、盆踊りを見学した。早速その体験談を「信州随筆」として東京朝日新聞に発表。古くからの形式を残す価値ある盆踊りとして評価したことで、新野の盆踊りは全国に知れ渡ることになった。

宿場町の面影が残る町並みの中で新野の盆踊りが行われる 撮影:金田誠
「信州随筆」の中で柳田が着目した点で、現代まで受け継がれている新野の盆踊りの特徴を挙げていこう。まず一つは、扇を盛んに用いて踊ること。新野には7種類の歌と踊りが伝えられていて、そのうち、「すくいさ」「音頭」「おさま甚句」「おやま」では扇を手に持ち、優雅に操って踊る。扇を使った盆踊りは全国的に見られるが、南信州や東三河地方では特にポピュラーな形態である。

扇を用いることで、踊りにしなやかさと優雅さが生まれる 撮影:金田誠
また、太鼓や三味線といった鳴り物がなく、音頭取り(盆踊りで歌を出す役目の人)の生歌だけで踊る点も大きな特徴だ。伴奏がないため、音頭取りと踊り手が調子を合わせる必要があり、自然と歌の「コール&レスポンス」が生まれる。たとえば、音頭取りの歌の合間に踊り手が「ソレッ」と掛け声をかけたり、七七七五の歌を音頭取りが歌った後に、踊り手が下の句(七五)だけを繰り返して歌ったり、こうした相互のやりとりによって、盆踊りの場がともに作り上げられていく。

ヤグラの上の音頭取りの歌に、踊り子たちがまた歌で返す
死者と共に踊り、生を思う
また、柳田が「佛法以前からの亡霊祭却の古式」だといって評したのが、踊り最終日の16日の晩から17日の明け方に行われる「踊り神送り」の神事だ。これは盆に迎えた新盆の精霊を、踊りながら送るという儀式である。
こまかい作法や行事の次第については、柳田の時代と多少の相違はあるようだが、大まかな形は変わらない。新盆の家から持ち寄られた「切子灯籠」という美しく装飾された灯籠を手に人々が行列をなし、市神様や御太子様といった場所で祈りを捧げたのち、最後は村の境に位置する場所で切子灯籠を焼却するというのが一連の流れだ。

新盆の家の数だけ切子灯籠が作られ、最終日の16日にはヤグラから吊るされる

切子灯籠には緻密で美しい装飾がほどこされている。すべて手作り

17日早朝、空が白んでくると、ヤグラから切子灯籠が下される
踊り神送りの神事で最も盛り上がるのが、切子灯籠を手にした行列と踊り子たちの輪が衝突する場面だ。御太子様から戻ってきた行列は、「ナンマイダンボ」と唱えながら、踊り会場を経由して、瑞光院というお寺まで向かう。

切子灯籠を持った行列が踊り会場に戻ってくる
一方で踊りの会場で待ち受けている踊り子たちは、「切子灯籠の列が通り過ぎたら踊りを終えなければならない」という決まりがあるため、肩を組んで踊りの輪を強固にし、行列の進行を阻止しようとする。踊りの輪が崩れると、すぐに先回りして新しい輪をつくり、再び阻止。切子灯籠を運ぶ人たちにとっては「いつになったら終わるんだ」と難儀なことかもしれないが、この攻防戦こそが、新野の盆踊りの醍醐味のひとつだ。踊りはこの時だけの特別な「能登」という威勢のいい踊りに変わり、踊り子たちのテンションも最高潮となる。

踊り子たちが肩を組んで、行列の進行を阻もうとする 撮影:金田誠

踊りの輪が崩れても、すぐさま新しい踊りの輪ができる
時間をかけて、ようやく行列が瑞光院の広場に到着すると、踊り子たちは観念したように静かとなり、厳かな雰囲気を持ったまま最後の儀式を見守る。運ばれてきた切子灯籠を一カ所に積み上げる。続いて袴姿の「御嶽行者」が現れ、切子灯籠の前で呪文を唱える。

切子灯籠の前に立つのが御嶽行者。この儀式の進行を取り仕切る
呪文の後に九字を切り、最後に刀を抜いて「道切りの式」を行うと、花火が一発上げられ、参加者たちが「ワー」と声をあげる。これで新盆の精霊たちが送られたことになるのだ。切子灯籠の山に火がつけられると、人々は後ろを振り向かずにその場を去っていく。この時に振り返ってしまうと、踊り神の霊に一年中取り憑かれてしまうという言い伝えがあるからだ。
帰り道、音頭取りたちが歩きながら「秋唄」という歌を口ずさむ。

切子灯籠に火が放たれ、勢いよく燃え盛る
秋が来たそで鹿さえ鳴くに なぜか紅葉が色づかぬ
稲は穂に出てちょいと花かけて さらり乱れて秋の空
盆よ盆よと楽しむうちに いつか身に沁む秋の風
神妙な気持ちになりながら歩いていると、この歌がどこからともなく聞こえてくる。すると、ふと空の色が変わって、空気が冷たくなってくるような、本当に秋がやってきたような気持ちになるのだ。季節の変わり目を歌で知った精霊たちは、再びいずこの世界へと還っていく。そして、来年の盆になると、またこの地に戻ってくるのだ。

祭りを終え、三々五々に散っていく参加者たち
御太子様の前で唱えられる和讃(仏教の讃歌)は、次の文句で締められる「来年七月はよおいで おいとま申していざ帰る ナンマイダンボ」。親しい人の霊を迎え、ある種の葛藤(まだ帰ってほしくない)を経ながら(切子灯籠の行列と踊り子の衝突)、最後には潔く霊を送り出す。心に一つの区切りを打ちながらも、来年の盆での再会を心に願う。
新野の盆踊りを通して、先祖たちがどれほど巧みに死者と向き合ってきたかを知らしめられる。もちろん、現代の葬送のあり方を否定するつもりはないが、楽しく踊りながら霊を送り出す光景を見ていると、もっと私たちは「死」や「死者」についてより深く考える必要があるのではないか、「死」に向き合いながら、もっと「生」を豊かにする方法を探究すべきではないか、そんな思いも湧いてくるのだ。
祖父に連れられて参加した「弔い」の原体験
では、地元の人たちは新野の盆踊りにどういった魅力を感じているのだろうか。音頭取りとして活躍する2人の親子に話を聞いてみた。
金田信夫(かなだ・しのぶ)さんは1961(昭和39)年生まれ。出身は新野で、社会人になってから地元を離れた時期はあるものの(1999年から2001年にかけてはペルーの日本人学校に勤務)、2002(平成14)年頃には再び新野に戻ってきて、地元小中学校の教員として働きながら(2025年4月より非常勤講師)、長年、地域の祭りや伝統行事に関わり続けている。

金田信夫さん。盆踊りの音頭取りは30歳ごろから務めているという
盆踊りでは、2024年(令和6年)3月に亡くなった父親、そして娘の渚(なぎさ)さんを含め、親子代々、音頭取りを務めてきた。そんな信夫さんにとっても、新野の盆踊りの価値は、「弔い」という側面にあるという。
「とくに17日の朝の『送り』の場面が印象的です。16日の夕方から灯籠が飾られ、翌朝にはそれを担いで瑞光院まで運び、故人を送り出す。それでなんだろう、癒されるというか。やっぱり身内が亡くなると寂しいじゃないですか。でも、新盆でみんなと一緒に踊り、歌うことで、なんとなく心が吹っ切れるというか、『無事にあの世に旅立ったな』と安心できる、そんな気がします。お葬式をやったからって終わらない。私の場合は(父親が)3月に亡くなりましたが、半年後の8月に新盆があって、ようやく『終わったな』と思えました」
実は現在、新野の盆踊りで使用される切子灯籠は、制作者の担い手不足という課題に直面している。毎年、20数基ほどの数が制作される切子灯籠。完成させるまでには約三週間を要し、しかも高い技術が求められるため、習得には数年の修練が必要とされる。しかし、その制作を担うのは、地区で現在1名のみだ。そのため、2024年(令和6年)の新盆で使用した父親分の切子灯籠は、信夫さん自身が継承者から作り方を教わりながら制作を行うことになった。新盆の霊の依代とも言うべき切子灯籠を自分自身の手で作ったということで、より一層、信夫さんの父への思いや、踊り神送りの儀式に込める気持ちは深まったのではないだろうか。

信夫さんがご自身で作られた父親の新盆の切子灯籠 提供:金田信夫
新野の盆踊りの魅力や特殊性について、ことさら「先祖供養」の面だけを強調するつもりはない。他にも歌や踊りの楽しさなど、取り上げたいポイントはたくさんある。しかし、自分自身の実感としても、金田さん親子の話を聞いてみても、やはり盆踊りと、「生きて死ぬ」という営みとの深い関連性を無視することはできないと感じる。
娘の渚さん(1991年生まれ)さんにとっても、新野の盆踊りの原体験は、「弔い」そのものだったという。
「盆踊りには、2歳くらいの歩けるようになった頃から、祖父に連れられて参加していました。祖父は音頭取りで歌も上手く、私はいつもその後ろについて踊っていた記憶があります。自分では覚えていないのですが、私が初めて盆踊りに触れたのも、2歳の時に祖父に連れられて参加した“物故者供養”だったそうです」

親子3代音頭取り。左が渚さん。中央は祖父(信夫さんの父)の栄二(えいじ)さん 撮影:金田誠
物故者供養とは、夏の本番とは別に、亡くなった音頭取りを供養するために、そのお宅の前に集まって踊るという新野特有の風習だ。そして、渚さんはこう続ける。「盆踊りは気づいたらもう好きでずっと踊っていたのですが、そこが私のスタートだったんだなと、後から家族に教えられて思いました」

亡き祖父(写真左)と並んで踊る渚さん(写真中央) 撮影:金田誠
音頭取りに誘われるも、大きかった不安
実は信夫さんとは、私が新野の盆踊りに参加した初年から交流があったが、娘の渚さんとは踊り会場でお見かけするだけで、今回の取材に至るまで、しっかりと会話をしたことがなかった。音頭取りの中でも若手の部類に入るであろう彼女。なぜ、音頭取りになろうと思ったのか、その経緯を聞いてみた。
渚さんは、父である信夫さんの仕事の関係で、地元を離れ各地を転々とするも、小学5年生の時に再び新野に戻ってきた。新野では1994年(平成6年)から、盆踊りの後継者を育てる取り組みとして「子ども音頭取り」を募集し、夜の早い時間帯に中学生たちがヤグラの上で音頭を取る機会を設けている。さらに、渚さんが新野に越してきたタイミングで、祖父が発起人となり「郷土芸能子ども教室」という取り組みも始まった。この教室では、新野に住む小学3年生から中学3年生までの子どもたちを対象に、盆踊りだけでなく、新野に伝わるお祭りや風習、昔話などを教えている。

郷土芸能子ども教室で盆踊りを教わる子どもたち 提供:金田信夫
こういった機会を通じて、盆踊りの意味を知り、音頭への興味も深まってきた渚さん。中学を卒業してからは、小諸市の高校へ進学するために再び地元を離れ、卒業後は長野市で就職した。しかし、その間も毎年お盆は地元に帰って、盆踊りには参加し続けた。渚さんが正式に新野の盆踊りの音頭取りになったのは2018(平成30)年のこと。音頭取りの先輩から「そろそろ、音頭取りにならないか」と声をかけられたことが、そのきっかけだ。
「最初は心配だった」と当時を振り返る渚さん。「ずっと音頭を覚えて出したいとは思っていましたが、いざ誘っていただくと、盆踊りに参加するのが自分の中で義務みたいな感じてしまわないかな、という。今まで気楽に楽しんでいた盆踊りが、やらなきゃいけないものみたいになって、嫌いにならないかなとは心配になりました。とても悩んだのですが、お盆の時期だけ(音頭取りとして)関わることになると義務みたいになってしまうので、せっかく音頭取りになるのであれば、自分ができることを最大限やっていこう、むしろ音頭取りになることを利用しようと、そう考えたら、前向きに捉えられるようになりました」

ヤグラの上で音頭を取る渚さん 撮影:金田誠
その後、渚さんは父・信夫さんとともに、新野の盆踊りの継承に積極的に取り組むようになった。たとえば、「新野高原盆踊りの会」(新野の盆踊りの主催団体、以下「盆踊りの会」)の有志とともに、長野県内で毎年ワークショップを開催し、新野の盆踊りを広く伝えている。また、盆踊りをはじめ、新野の文化や自然、移住者支援の情報などを紹介するウェブサイト「DeepJapan 新野高原」の運営も担っている。そして、コロナ禍で勤務先がリモートワークを認めたことをきっかけに、次第に新野へと生活の軸足を移し、現在では住民票も新野に置き、フルリモートで働きながら地域を盛り上げる活動に励んでいる。

2019年、銀座にある長野県のアンテナショップ「銀座NAGANO」で行われた盆踊りワークショップ 提供:金原渚
地域の人にこそ、その魅力を知ってもらいたい
信夫さんが子どもの頃、盆踊りの輪は現在よりもはるかに大きく、会場も人の通行が困難になるほどにぎわっていたという。現在でも、最終日の「踊り神送り」の時間帯には人出が増えるが、かつての盛況ぶりには及ばないそうだ。
地域の少子高齢化がその要因の一つであることは言うまでもなく、実際、2020(令和2)年に策定された『第6次阿南町総合計画』(阿南町)でも、新野地区の弱み(弱点)として「少子高齢化、人口減少が進んでおり地域の後継者(若者)がいないこと。」が報告されている。しかし渚さんは、地元の人々が郷土芸能の魅力に触れる機会が限られていることも、祭りのにぎわいが減じている一因ではないかと言う。
「私が子どもの頃は『郷土芸能子ども教室』の取り組みで、新野の文化を教えていただく機会がありましたが、少し上の世代の人たちはそうした活動を経験しておらず、盆踊りや雪祭りの面白さ、地元の魅力をあまり知らないということに、大人になってから気づきました。ヤグラの上で中学生が歌うのも、私にとっては当たり前のことだったのですが、その取り組みがはじまったのも平成に入ってからのこと。その前の世代の方は経験してないんですよね」

渚さん自身は、子どもの頃から新野の踊りと歌に親しんできた 撮影:金田誠
県外の人に新野の盆踊りについて知ってもらうことも大切だが、それ以上に渚さんは、地元・阿南町の人たちにもっと盆踊りの面白さを感じてもらいたいと考えている。阿南町には新野のほかに、大下條、富草、和合といった地区があるが、同じ町内でも地域が違えば新野の盆踊りへの関心は薄れがちだ。特に、お祭りがあまり盛んでない地区では、「郷土芸能=面倒なもの」というイメージが根強く、興味を持ってもらうのが難しい。そうした人たちにどうすれば魅力を伝えられるのか。
「学校教材のように一方的に押し付ける形では受け入れてもらえないと思うんです。そこで思いついたのが演劇でした。盆歌の面白さですとか、生と死がうまく組み込まれている祭りであることとか、そんな新野の盆踊りの魅力を演劇作品のストーリーを通じて知ってもらうのはどうかと思ったんです」
渚さんは短大に入学してから、再び新野に戻ってくるまで、長野市に12年ほど居住しており、その頃に地元の劇団などとの交流があった。その流れで、長野県の信州アーツカウンシルという団体から声をかけてもらったことが、演劇を作るきっかけになった。アーティスト・イン・レジデンスの形式で、劇作家・演出家・俳優の山田百次さんが新野に滞在。渚さんと一緒に作品作りを行い、信夫さんも、作品制作のためのアテンドとして協力した。そうして完成した短編劇『新野物語』は2021(令和3)年、阿南町新野で初演。それを皮切りに、これまでに下伊那郡売木(うるぎ)村、長野市、諏訪市など、長野県内各地で公演を行い、好評を博している。

舞台『新野の物語』の一幕 撮影:安徳希仁
どんな形でもやらなければ
信夫さんと渚さんが、盆踊りの存続について強く意識する出来事が近年あった。それが、2020(令和2)年から全国で広がった新型コロナウィルス感染症だ。コロナ禍の影響で、新野の盆踊りも2年間の中止が余儀なくされた。何百年も続いてきた新野の盆踊りを中止にしてもいいものか。当時、関係者の中でもさまざまな葛藤があっただろう。信夫さんも、中止が決まった際には「これはいかん、どんな形でもやらなければ」と思ったと言う。
「新野の盆踊りはあと数年で、500年目を迎えます。今を生きている私たちが、500年という長い流れの一番最先端にいる、そう考えるとオリンピックの聖火リレーみたいな感覚になることがあるんです。前の人からもらって次の人に渡していく、途中でその火を消しちゃいけないじゃないですか。だからコロナで盆踊りを中止にするとなった時も、なんか変な気持ちになりました」
そこで2020(令和2)年は、有志数名だけで場所に集まり、踊り会場の通りにある駐車場で小さく踊りが行われた。渚さんは、当時を次のように振り返る。

盆踊りは公式では中止となったが、有志のメンバーのみで自主的に踊りが行われた 提供:金原渚
「盆踊りが中止になる前、97歳の元音頭取りの方から、終戦の日にも若い衆が集まり、亡くなった方の魂を送るために踊ったという話を聞く機会がありました。公式行事としては中止になったものの、盆踊りの歌詞に『踊り踊るなら3人でも踊れ』とあるように、踊りたい人が数人で小さく踊るだけでも、十分に盆踊りになると思い、実際にやってみたんです。ヤグラもスピーカーもない中での踊りは、昔の盆踊りってこんな感じだったのかなと、かえって新鮮に感じられました。さらに、新盆のお宅のおばあさんが見に来てくださり、『これで、やっと送った気持ちになれた』と話してくれたこともうれしくて、新野の盆踊りはやっぱり、地元の人のための祭りなんだと改めて実感しました」
翌年も盆踊りは中止となったが、信夫さんと渚さんはZoomを使ってオンライン上で歌と踊りを実施。先人から受け継がれてきた思いをつないだ形となった。

2021年はオンラインで歌と踊りをつないだ 提供:金原渚
ただ急いで付け加えないといけないのは、信夫さんとにとっても、渚さんにとっても、郷土芸能を継承する、地域を盛り上げるという活動が「義務」や「責任」といった重しにはなっていないということだ。あくまでベースにあるのは「この祭りが好きだから残したい」や「楽しいから継承したい」という感情である。5年ほど前から仲間たちと新野への移住者支援活動も行なっているという信夫さんが、その心情を次のように話してくれた。

移住支援活動の一環で空き家の片付けをしている様子 提供:金田信夫
「移住者支援の活動は、人口減少への危機感から始まったものですが、義務感というよりは、新たに訪ねてきてくれた人に新野の魅力を伝え、その反応を一緒に楽しむという素朴な気持ちが原動力です。驚いたり楽しそうに話を聞いてくれたりする様子がうれしくて、無理なく続けられているんですよね。年間の数値目標を立てて、絶対に達成しなければならないというような取り組み方では、きっと長続きしません。気負いすぎると苦しくなる。少し疲れたら休めばいい。郷土芸能の継承も、自然体で向き合うことが持続につながると思います」
高校の先輩に誘われ「新野の盆踊り」の世界に
最後に、2024年に「新野高原盆踊りの会」に加入し、音頭取りデビューを飾った松下恵吾(まつした・けいご)さんという男性について紹介しておきたい。
松下さんは長野県飯田市の出身で、現在23歳(2025年4月時点)。高校生の頃に新野の盆踊りにハマり、新野出身ではないながらも音頭取りを志願し、認められるというその特異な経歴が、これからの盆踊りを担う若手のロールモデルになり得るのではなだろうか。新野に限らず、今後、郷土芸能に興味のある10代〜20代をスカウトする上でのヒントになるのではないかと思い、その一例として、今回お話を聞かせていただくことにした。YOUはなぜ新野に?

現在は三重県伊勢市の大学に通っている松下恵吾さん
「僕という人間は、祭りがベースでできてるんですよね(笑)」そう話す松下さんの原点となったのが、小学3年生の時に、テレビで見た「遠山の霜月祭り」の映像だ。遠山の霜月祭りとは、長野県飯田市南部の遠山郷(旧・上村、旧・南信濃村)で毎年12月に行われる、冬の湯立て神事だ。理由もわからずに、松下さんは映像を見た瞬間に「これは行かなければ」と思ったそうだ。翌年、親に頼み込んで霜月祭りに連れて行ってもらう。
「当時はほとんど何も調べずに行ったのですが、もう本当にすべてが新鮮で、ずっと楽しかったです」
夜通し行われる神楽だが、仮眠を取りながら最後まで見物した。以来、毎年欠かさず参加するようになった。中学一年生のときには、たまたま学校の先生の教え子に霜月神楽の関係者がいたことから、先生の紹介で神楽のメンバーに加わることに。こうして松下さんは、ディープな祭りの世界に足を踏み入れることになった。

霜月神楽での松下さん 撮影:岡庭圭祐
以来、長野県の郷土芸能に関しても知識を深めるようになり、その過程で新野の盆踊りの存在も知ることになった。しかし、最初は一般的な盆踊り大会と同じようなものをイメージしており、興味が湧かなかったという。転機となったのは2017(平成29)年、高校の新野出身の先輩に誘われて初めて参加したことだ。「あの時の楽しさは忘れられないですよね」と松下さん。特に17日明け方の「能登」に感動した。盆踊りにも急速にハマっていき、歌詞もスポンジのように吸収。音頭の返しを積極的に歌っていたので、踊り会場でも目立った存在となった。
「彼を音頭取りにスカウトしよう」という話は盆踊りの会の中でも早々に出てきたが、コロナ禍に入ってしまい話は一時停滞。盆踊りが3年ぶりに制限なしで開催された2024(令和6)年に、晴れて保存会に認められて正式に音頭取りになることができた。

音頭取りデビューを飾った松下さんの勇姿
実は、これまでも新野出身者でない者が音頭取りになったというケースはある。いまよりもずっと敷居が高かった時代に音頭取りになろうと飛び込んだ、そういう道を開いてくれた先駆者がいなければ、そもそも音頭取りになりたいとすら思わなかっただろうと松下さんは話す。

地区外出身者ながら20年ほど新野の盆踊りの音頭取りを務める松岡麻美さん(写真右)。松下さんにとっても彼女がロールモデルの1人になったという 撮影:中島次郎
また、遠山の霜月祭りに参加した時の経験談も踏まえて、一般論として祭り団体が外部の人を迎える際のアドバイスを尋ねると、松下さんは「密にコミュニケーションが取れる仲介役を立てることが重要」と教えてくれた。内部のしきたりに精通し、根回しができる一方で、外部にも開かれた人。そういう人物が橋渡し役となることで、外部の人も参加しやすくなるという。また、保存会などの団体と新規参入者が定期的に交流する機会を設けることも大切だと語る。
もちろん、橋渡しという役は簡単な仕事ではない。それも踏まえた上で、松下さんは次のように意気込みを語る。「自分は純粋に中の人間ではない。だからこそ、その立場を生かし、たとえば霜月祭りでも新規参入者の学びになるような冊子を作るなど、橋渡しとなるような活動をしていきたいです」
その土地に暮らす人が幸せになることが祭りの目的
2019(令和元)年、渚さんは音頭取りになって、初めて先輩音頭取りを弔う物故者供養に参加した。初めて新野の盆踊りに触れたのも、小さい頃に祖父に連れられて参加したこの物故者供養だった。当日は30名ばかりの音頭取りが集まり、故人の家の庭で踊ったが、参加した面々の中で、明らかに自分が一番の若手。その時、渚さんは「この先輩方をみんな私が送るんだな」と実感したという。バトンを渡されたんだなと。そして、「自分もこうやって送ってもらいたい」とも。

故人の家の庭で踊りながら音頭取りを供養する「物故者供養」 撮影:中島次郎
人の生き様、死の様は、さまざまだ。しかし、誰かに踊られながら、あの世に送られるという最期は、とても「納得感」のある終わり方のように感じる。信夫さんは「祭りや伝統行事というものは、必然性や目的があって生まれたものだと思っている」と話す。
「その目的というは、土地に暮らす人が幸せになることですよね。たとえば新野の盆踊りであれば、昔は男女の出会いの場という性格がすごく強かったと聞くし、踊り神送りの神事は、亡くなった人を送るだけでなく、送り手の心を癒す場にもなっている。つまり、出会いや別れ、生と死といった人生のすべてが詰まっているんです。で、それ(祭りという場)ってお金じゃ買えないものじゃないですか。みんなで協力して何年もかかって作り出してきたものだから。だからこそ、一旦絶えたらもう二度と復活できない。他の地域の例を見れば、それは明らかです。だからこそ、絶やさず残していくべきだと、私は思うんです」

亡くなったご主人の切子灯籠を見上る女性「おじいちゃん。いい場所にかざってもらえてよかったに」 撮影:金田誠
信夫さんの話を聞いていると、祭りは「地域のインフラ」のようなものであるように感じられてくる。インフラはいつか老朽化し、新しいシステムやサービスに取って代わられる。それは時代の必然なのかもしれない。しかし「祭り」という仕組みの中でしか得られない、幸福もあるのではないだろうか。祭りがなくなっていくいまの時代だからこそ、あらためてその価値を検討してみたいと私は思った。(了)
Text:小野和哉
プロフィール

小野和哉
東京在住のライター/編集者。千葉県船橋市出身。2012年に佃島の盆踊りに参加して衝撃を受け、盆踊りにハマる。盆踊りをはじめ、祭り、郷土芸能、民謡、民俗学、地域などに興味があります。共著に『今日も盆踊り』(タバブックス)。
連絡先:kazuono85@gmail.com
X:hhttps://x.com/koi_dou
https://note.com/kazuono
この記事を読んだ人におすすめの商品