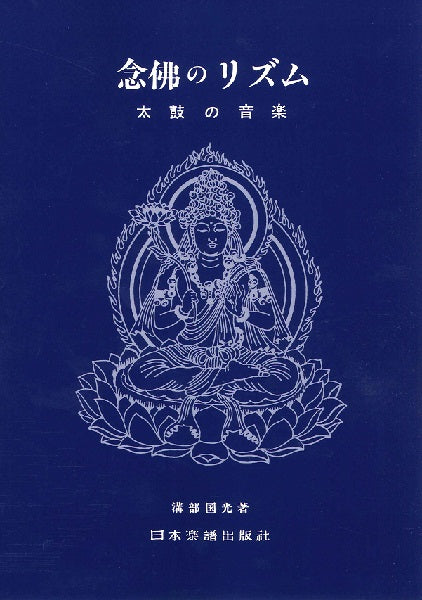日本には数え切れないほど多くの祭り、民俗芸能が存在する。しかし、さまざまな要因から、その存続がいま危ぶまれている。生活様式の変化、少子高齢化、娯楽の多様化、近年ではコロナ禍も祭りの継承に大きな打撃を与えた。不可逆ともいえるこの衰退の流れの中で、ある祭りは歴史に幕を下ろし、ある祭りは継続の道を模索し、またある祭りはこの機に数十年ぶりの復活を遂げた。
なぜ人々はそれでも祭りを必要とするのか。祭りのある場に出向き、土地の歴史を紐解き、地域の人々の声に耳を傾けることで、祭りの意味を明らかにしたいと思った。
火山の島に伝わる祭りと太鼓
2000(平成12)年。東京都の伊豆諸島南部に位置する三宅島で大規模な噴火が発生した。6月末の海底噴火からはじまり、7月には山頂陥没を伴う噴火が発生。噴火の規模は8月からさらに拡大し、8月18日には噴煙が高さ14,000mに到達。9月からは有害な火山ガス放出もはじまり、結果として約4,000人の島民が全島避難を余儀なくされた。避難指示が解除されたのは、2005年2月のこと。島民が再び島に戻るまでに、実に4年半もの歳月が流れていた。
噴火当時、私は中学3年生で、テレビで連日報道される噴火の経過をただ呆然と見守っていた。自然の力になすすべもなく故郷を追われる人々が味わったであろう無力感は、未熟な中学生の自分でも容易に想像することができる。地域の人はいつ帰島できるのか。何の約束もない永遠の別れがそこに横たわっているようで、深い絶望を感じた。
それから20年以上の歳月が経った2023年11月のこと、私はとある仕事の取材で、はじめて三宅島を訪れた。東京の調布飛行場から乗客定員19名の小型旅客機に乗り、わずか45分間のフライト。災害をテーマとした取材ではなかったため、正直に言えば、島に着くまで噴火のことは、ほとんど意識していなかった。しかし、撮影のために地元の方の運転するタクシーで島内を回るうちに、否応なく、あの未曾有の災害の爪痕を目の当たりにすることになった。

旅客機から見下ろす三宅島
溶岩によって焼かれた建物、泥流(火山灰や溶岩のかけらが水と混ざり合って谷を流れ下る現象)によって埋まった鳥居、島の施設に設置された小型脱硫装置(火山ガスに含まれる二酸化硫黄を除去するための機械)など、その島で見たさまざまな遺物や器具は、文字や数字よりも雄弁に2000年噴火の規模の大きさと、活火山とともにある生活のリアルを如実に物語っていた。動揺とともに、何かいたたまれないような気持ちに襲われた。
撮影をしている最中、運転手さんが三宅島に関するさまざまなことを教えてくれた。三宅島の歴史のこと、観光スポットのこと、そしてご自身の来歴。
「僕も全島避難の際は内地(島しょ地域からみた本土のこと)に住んでいました。ここだけの話、本当はずっと内地に住んでいたかったんですけど、長男なので実家を継ぐために島に戻ってきたんです」
2000年の噴火前、三宅島の人口は約3,800人近くあったが、長期避難は人口を大きく減少させ(2005年には1995年比で約36%減)、高齢化率を加速させた(1995年の24%から2005年には37%へ上昇)。つまり避難指示が解除された後も、島外にとどまった人は少なくなかった。被災後に若者の就労の場を確保できなかったことから、特に若年層の島外流出が顕著だった。2025(令和7)年5月31日時点で、三宅島の人口は2,165人。「昔は新島よりも人口が多かったんですけどね」と、男性は海を見ながら寂しそうに語る。
三宅島での滞在体験は、私の心に深く重い印象を残した。そして、この島についてもっと知りたいという気持ちが芽生えた。調べていくうちに、毎年7月に島の神着(かみつき)という地区で行われている「牛頭(ごず)天王祭」のことを知った。
読売新聞オンラインの記事(「三宅島の災害生き延びた太鼓、次世代へ…『木遣太鼓』の伝統受け継ぐ」2021年7月16日掲載)によれば、祭りで神輿の先導役を務める「木遣太鼓」は、東京都の無形民俗文化財に指定され、島の人々によって大切に受け継がれてきたという。全島避難の際には、島民たちが協力して太鼓を島外に運び出し、避難先でも、住民が集う場で演奏されることがあったそうだ。
未曾有の災害を経ても守られ続けてきた「木遣太鼓」とは、いったいどのようなものなのか。それを確かめるため、実際に祭りに参加してみることにした。
破壊的な自然現象に「神」を見た古代の人々
三宅島へは、調布飛行場から飛行機で向かう空路のほか、東京・竹芝埠頭から出る船便も利用できる。伊豆諸島行きの大型客船は夜に出発し、一晩かけて航行したのち、早朝5時に三宅島へ到着する。今回の旅では船便を利用して三宅島へと向かった。

三宅島・御蔵島を経由して八丈島に向かう大型客船の橘丸
祭りは朝から行われるとは聞いていたが、さすがに時間が早すぎるので少し島内を散策してみることにした。特に今回、足を運んで確認してきたいとおきたいと思ったのは、島の南西部に位置する「阿古(あこ)地区」の被災状況だ。
三宅島が噴火の災害に見舞われたのは2000年だけではない。島の中央に位置する「雄山(おやま)」は、有史以来いくども噴火現象を繰り返してきた。20世紀以降では、1940(昭和15)年、1962(昭和37)年、1983(昭和58)年、2000(平成12)年の4回。またそれ以前にも、1085(応徳2)年から1835年(天保6年)にかけて、13回の噴火が記録として残されている(池田信道『三宅島の歴史と民俗』)。噴火の多さから、「御焼島(おんやけのしま)」という名称から転じて「三宅島」になったのではないかという説すらある。
1983(昭和58)年の噴火は、人的被害もなく、全島避難までは至らしめなかったが、火口から流れ出した溶岩流は阿古地区の400棟を超える住家、そして集落の小学校や中学校を埋没させ・焼き尽くした。現在、溶岩流の流れた場所には遊歩道(火山体験遊歩道)が設置されていて、噴火の恐ろしさを体感できるようになっている。前回、島を訪れた際、道路の脇に朽ち果てた建物を見かけ、それが溶岩で焼けたものだと例のタクシー運転者の男性に教えられ、気になっていたのだ。

火山体験遊歩道から見た光景

溶岩流で焼けた建造物

写真に残るかつての阿古地区の姿
緑に包まれた山の裾野に、黒く無機質な溶岩原が広がっている。その風景に、思わず息を飲む。あとどれほどの年月が経てば、この地に再び緑が戻り、人々が居住できるようになるのだろうか。地殻変動による破壊と再生の繰り返しで、いま私たちが住むこの美しい世界が形成されている。そういった道理は理解できても、いざ「破壊」そのものを目の当たりにしてしまうと、ただただ途方に暮れてしまう。
古くから、人々は圧倒的な自然現象に神の存在を感じてきた。三宅島をはじめとした伊豆諸島でも同様に、火山の噴火や島の生成といった自然の営みに神の力「神威(しんい)」が見出され、「三嶋信仰(みしましんこう)」と呼ばれる信仰が発展してきた。三嶋信仰では、伊豆諸島の島々を生み出し、開拓した神として「三嶋大明神(みしまだいみょうじん、または三嶋神)」が崇敬されている。三嶋大明神は、日本神話に登場する事代主命(ことしろぬしのみこと)と同一視される神で、三宅島の阿古地区にある富賀山(とみがやま)の「富賀神社」には、この事代主命が三宅島に渡り、阿古の地に最初の拠点を築いて島を開いたという伝承が残されている。
現在の三宅島は、数万年にわたる火山活動の積み重ねによって形成されたとされている。火山と島の歴史は不可分であり、人と火山の関係もまた単純なものではない。ただ、これだけは言えるだろう。どうすることもできない自然の脅威にさらされながら、島の人々が神や、その神をもてなす神事や祭りに託してきた祈りや願いには、並々ならぬ思いが込められていたはずである。
海を目指す子どもたちの神輿
島内を巡回するバスに乗って、島の北側に位置する神着地区に向かう。バスを降りると、祭りの拠点となる御笏(おしゃく)神社には早朝8時ながら、すでに多くの人々が集まっていた。

神社に続々と詰め掛ける人々
「牛頭天王祭」は、伝承によると江戸時代末期、神着村の百姓、藤助、八三郎、又八の3名が伊勢参りの帰路に京都の八坂神社を詣で、祇園祭を見学。当時、神着では伝染病が流行っており、祇園祭が悪疫除けを目的としたことを知った3人が、帰島後、神着に牛頭天王社を勧請(地元の守り神として他の土地から神様を招いて祀ること)。これが牛頭天王祭のはじまりであるとされている。なお牛頭天王社はのちに、御笏神社に合祀(複数の神様を一つの神社にまとめてまつること)された。
境内に足を踏み入れると、社殿の前に大小2基の神輿が並んでいる。小さい方は、これから担がれる子ども用の神輿らしい。そして神社に集まった人々の喧騒をかき消すように、太鼓の音が辺りに鳴り響いている。太鼓のスタイルは素人目から見ても非常にユニークだ。大太鼓(長胴太鼓)を横向きに地面に置き、2人が太鼓の両側から同時に叩く。太鼓の位置が低いので、当然打ち手の姿勢も腰を低く落とした形となる。このシルエットがとにかくカッコいい。

太鼓の両面から異なるリズムで叩く
打ち込み太鼓では、2つのリズムが奏でられる。一方では「ドドン・ドドン・ドドン・ドドン」と、常に一定のリズムが刻まれる(裏打ち)。もう一方では「ドンツク・ドンツク・ドンドン」と緩急をつけた打ち方がされる(表打ち)。まるで2つの心臓が脈打つように、この太鼓が祭り全体に血を巡らせ、生き生きと躍動させるのだろう。
しばらくすると子ども太鼓の時間がはじまる。小さな神輿を子どもたちが担ぎ、神社の境内を出発する。

神社の境内で神輿を揉む子どもたち
太鼓と榊が先頭に立ち、神輿を先導する。巡行の際に、太鼓は「打ち込み太鼓」から「神楽太鼓」に切り替わる。

神輿が巡行する時に演奏される「神楽太鼓」

巨大な榊を持った子どもが、神輿を先導する
途中休憩を挟みながら、子どもたちに担がれた神輿は集落の中を進んでいく。どこに向かっているのかわからないが、誘われて行く感じが楽しい。

島の高台から海を臨む
坂道を下っていくと、ほどなくして海が見えてきた。大人も子どもも、連れ立って歩きながら、引き寄せられるように海に向かっていく。大袈裟な表現かもしれないが、その光景には神話的な美しさがあった。「神着(かみつき)」という地名は、事代主命とその眷属たちが三宅島に渡御した際、最初に上陸した地であることに由来するとする説がある。

海上渡御の様子
「ワッショイ、ワッショイ」という掛け声とともに子ども神輿が海の中へと入っていく。押し寄せる波に「キャー」という声も飛び交うが、大人たちのサポートを受けながら、勇壮に神輿が揉まれる。

神輿が海に降りている間、浜では打ち込み太鼓が演奏される
海上渡御が終わると、子どもたちは神社へと戻っていく。途中、神輿を担ぎながら坂道を駆け上がったり、神輿を激しく揉んだり、最後まで見せ場は多い。神輿を揉む際は、木遣り唄が歌われる。大きな榊(さかき)を持った子が「イェ〜エ〜エ〜ェ……」と高らかに唄い、それに応える形で、神輿を担ぐ子たちが「コ〜レワァ〜イセェ〜エ〜……」と伊勢音頭風の唄を返す。そして飛び上がるような動作で神輿を激しく揉む。

子どもたちの神輿もなかなかすさまじい
太鼓と木遣り唄、神輿を担ぐ声が飛び交う空間
子ども神輿の時間が終わると、いよいよ祭りの本番が始まる。神社の境内に寄せ太鼓が鳴り響くと、宮司・禰宜・役員・来賓・氏子らが拝殿に上がり、式典が行われる。直会の行われる間、境内では打ち込み太鼓が叩かれる。直会がひと段落すると、木遣り唄が、声高らかに歌われる。宮出の時間になると、境内に置かれた神輿に人々が殺到。太鼓の打ち込み、木遣りの唄とともに、神輿が持ち上げられ、「オイサ、オイサ」の熱い叫びとともに上下左右に激しく揺さぶられる。

神輿を壊さんばかりに揉む大人たち
境内を出た神輿は、まず神社の近くにある茅葺屋根の民家に向かう。この建物は「三宅島役所」と呼ばれ、かつて島内の神社を統括し、島の最高権力者である島方取締役(後に地役人)として幕末まで島務を執行してきた壬生(みぶ)氏の館である。座敷に神輿を上げ、祭りの責任者らが盃を交わす。

三宅島役所
神事が終わると、神輿は日暮れまで集落内を巡行する。途中、地区内の要所に立ち寄り、そのたびに木遣り唄が歌われ、激しい揉み合いが行われる。神輿を先導するのは太鼓であり、絶え間なく音を響かせながら行列を導いていく。太鼓の音、木遣り唄、担ぎ手たちの掛け声――それらが渾然一体となって、独特のサウンドスケープを形成する。祭りの熱気のせいなのか、それともこの蒸し暑さのせいなのか、次第に頭がとろけていくような感覚に襲われる。

地区内を巡行する神輿の一団

血気あふれる太鼓の演奏に痺れる

神輿を担ぐ者たちの必死の形相

榊を持つ係は、選ばれた者しか担当できない
夕方を迎えるころ、神輿とともに動いていた太鼓は神社の鳥居前に据え置かれ、その場で宮入(神輿が神社に戻ること)の時間までひたすら打ち鳴らされる。階段に叩き手が並び、己の技量を試すように次々と太鼓に挑みかかる様は圧巻である。太鼓を打ち込む人々の真剣な表情を見ていると、この島の太鼓はただものではない――そんな確信が、否応なく迫ってくる。

鳥居の下で、ひたすら太鼓を叩き続ける
日が暮れる頃に、神輿は鳥居の前で太鼓と合流する。すぐには宮入せず、太鼓の躍動的な演奏に合わせて、神輿は何度も激しく揉まれる。観衆はクライマックスの瞬間を待ちわびながら、その様子を見守る。

ふらふらになりながらも、神輿にしがみつき必死に担ぐ

宮入の様子を見守る島の人々

宮入の瞬間。歓声があがる
すっかり辺りが暗くなった頃、神輿がついに一の鳥居をくぐると、拍手喝采がわきおこった。牛頭天王祭はまもなく終わりを迎える。
神輿の御霊抜きが終わると、境内に建てられたヤグラを囲んで奉納踊りが開催される。神輿を担いだり、太鼓を叩いていた時の緊迫感あふれる雰囲気とはまた打って変わって、大人も子どもも、みんなニコニコと輪になって踊りを楽しんでいるさまが、まさに「大団円」という感じがして美しい。
祭り会場を離れ、民宿まで徒歩で帰る。暗く静かな道のりであったが、しばらく頭の中では、あの打ち込み太鼓の音が鳴り響いていた。いったい、島の人、神着地区の人たちにとって、木遣太鼓とはどういった存在なのだろうか。
祭りの継承に必要なのは太鼓の技術だけではない
牛頭天王祭に参加した時からおよそ1年後の2025年6月、私は再び三宅島の地を訪れた。あの熱気はなんだったのか、地元の人から直接話を聞いてみたかったのだ。SNSを通じて神着郷土芸能保存会に問い合わせをすると、島の小学校の体育館で毎週開催されているという太鼓の練習会にお誘いいただいた。
保存会会長・前田 誠さん(昭和47年生まれ)によると、この練習会は年末年始や、学校行事などで体育館が使用できない時など以外は、毎週行われているという。祭りの直前だけでなく、通年で練習をしているというのがすごい。前田さん曰く、数週間ブランクが空いただけでも感覚が鈍ってしまうのだという。

練習会には子どもたちも多く参加している
参加者の年齢層は幅広く、下は保育園児から、上は72歳まで。女性の参加も多く、「いま太鼓って、全国的にも女性プレイヤーが多いんですよ」と前田さんは教えてくれた。島出身に限らず、希望すれば誰でも参加できるようで、実際に島外のイベントで神着木遣太鼓を知り、魅了され、自ら志願して練習に通うようになった人もいるという。

太鼓を叩く女性たち

大人にレクチャーしてもらいながら練習する子どもたち
また、都の職員や学校の先生など、仕事で三宅島に移り住んだ人たちも多く参加している。「昔は、本当に島の人だけで祭りをやってました。俺が高校生の頃は、6人か7人だけで太鼓を打ってたんですよ」と、前田さんは当時を振り返る。
変化のきっかけとなったのは、2000年の噴火だった。全島避難で内地に移り住むことになった際、神着の人々は東京都と交渉し、太鼓を島外へ持ち出した。避難中には太鼓の公演依頼も多く、それに応えるかたちで、内地の太鼓団体に稽古場を借り、練習を続けるようになった。その過程で生まれた太鼓団体との交流がきっかけとなり、帰島後には、彼らが祭りの復興を支えてくれるようになった。太鼓を叩くことや、重い神輿を担いで歩くことなど、祭りの実行には多くの人手が必要となる。しかし、全島避難を機に若い担い手が減ってしまったため、祭りの継続には外部の支援を受け入れる体制が必要になったのである。
牛頭天王祭に参加してみると、神着の木遣太鼓に憧れて、自分もやってみたいという思う人の気持ちは理解できる。それだけ魅力的な太鼓だ。実際、過去にこの太鼓にインスピレーションを受けて「三宅太鼓」「木遣太鼓」などの名称で演目を創作した団体がいる。そして、いまや日本全国の和太鼓グループで演奏されるまでに広がっているという。しかし、島の人々はそういった舞台演目と牛頭天王祭で叩かれている太鼓はまったくの別物であると捉えている。牛頭天王祭の太鼓はあくまで、神輿や榊とともに祭りを構成する一つの要素に過ぎず、本来は舞台演目としてそれ単独で成立するものではない。
「祭りのなかに“木遣太鼓”っていうものはないんですよ。私たちもステージに立つことはあるので、そういった時は(便宜的に)“木遣太鼓”という名称を使っていますけど。太鼓はお祭りのBGMであって、メインは神輿。BGMがしっかりしてないと、神輿も担げないし、唄も歌えないでしょ。輿係(こしがかり――神輿を担ぐ係)が気持ちよく神輿を担げるように叩くこと、それがこの太鼓の真髄だと思います」

伊豆諸島・小笠原諸島をPRするイベント「島じまん」での演奏
祭りを続けていくために必要なことは、太鼓の技術継承だけではない。例えば、前田さんらが噴火以降、力を入れているのが、祭りに使用する榊の栽培だ。榊は牛頭天王祭で重要な役割を果たしており、神輿を先導するだけでなく、榊を持つ「榊持ち係」は木遣り唄を歌う役目を務めることになる。かつて榊は祭りの前日に山から形の良いものを切り出して使用していたが、噴火で木が枯れ、植生が変化してしまったため、島内で手に入れることができなくなってしまった。そこで保存会では購入した苗木を山に移植し、将来に向けて育てることを始めた。祭りに使えるようになるまでには10年以上かかるため、地道で根気のいる取り組みではあったが、近年にやってようやく島で育てた榊が使えるようになってきた。
また、祭りの全体像を後世に伝えていくために、2024(令和6)年には、コロナ禍の中断を挟んで4年振りに開催された牛頭天王祭を記録したドキュメンタリーを制作し、YouTubeで公開した。
「昔はさ、(祭りのしきたりや準備、技術などを)全部口伝えで教えてもらっていたけど、次の時代に伝えていくためにも、いまの牛頭天王祭を映像に残しておきたいと思ったんだよね」
『継承』三宅島神着地区牛頭天王祭 2023年の記録 / 神着郷土芸能保存会
前田さんは神着の出身で、牛頭天王祭には子どもの頃から参加していた。太鼓を叩いていた父親の影響で、自身も太鼓は3歳から叩いていた。「お祭りの思い出は……とにかく楽しかったね」と前田さんは回想する。祭りは一年のなかでも最大の楽しみだった。
「内地と違ってさ、島って娯楽がないじゃん。変な話ね、内地なら日曜日に映画に行けるじゃん、ディズニーランドにも行けるじゃん。いまの時代ならスマホがあるけど、俺らの時代は何もないから。ファミコンが出たのも中学生の時だし。だから祭りが一番の楽しみ。正月みたいなもんよ」

練習会で太鼓を叩く前田さん
神輿を担ぐ大人たちの姿がかっこよく、その姿に憧れを抱いたともいう。2000年の噴火の際は、前田さんは28歳。10年間ほど内地で暮らしたが、再び島に戻ってきて、今度は自分が子どもたちに背中を見せる立場となり、祭りの継承に取り組んでいる。
帰島から20年、いまだ鳴り続ける木遣太鼓の音
取材を終え、帰路の船上から島の全景を眺める。実は三宅島を再訪する数日前、気象庁から噴火警戒レベルの引き上げが発表されていた。島では2013年以来、噴火は起きていない(2025年7月現在)。しかし、火山島としての力が完全に失われたわけではないことを、忘れてはならない。それでも、船から見る緑に包まれた島の姿は、噴火の歴史を忘れてしまうほど穏やかで美しい。

三宅島の勇姿
2004(平成16)年から2012年(平成24)年まで三宅島村長を務めた平野祐康は、2011年に開催された講演会の中で、噴火当時のことを次のように振り返っている。
思い起こしますと、私自身の当時の感触でいきますと、三宅島はこれで終わったなという気分でございました。(中略)これでもう三宅島は終わって、駄目なんだ、島民もすべて終わりだなというような気持ちでおりました。
(災害復興まちづくり支援機構「災害復興まちづくり支援機構記念講演会 三宅島は今 〜噴火・全島避難・帰島そして復興〜」より)
2025年は帰島から20週年を迎える年。島の人々は最悪の状況からも粘り強く歩みを進め、島の暮らしを復興させた。木遣太鼓の力強い音は、そのまま三宅島住民のうちに秘める力強さに通ずるものと思う。素人の私は、太鼓の細かな技巧についてあれこれ語る言葉を持たない。しかし、牛頭天王祭で聞こえる太鼓こそ、島が生きていること、そして人々がこの地で確かに暮らしていることを、全身で伝えてくれる音だと感じた。その響きは過去と現在、そして未来をつなぎ、この島で歩んできた人々の記憶を呼び覚ましている。(了)
Text:小野和哉
プロフィール

小野和哉
東京在住のライター/編集者。千葉県船橋市出身。2012年に佃島の盆踊りに参加して衝撃を受け、盆踊りにハマる。盆踊りをはじめ、祭り、郷土芸能、民謡、民俗学、地域などに興味があります。共著に『今日も盆踊り』(タバブックス)。
連絡先:kazuono85@gmail.com
X:hhttps://x.com/koi_dou
https://note.com/kazuono
この記事を読んだ人におすすめの商品