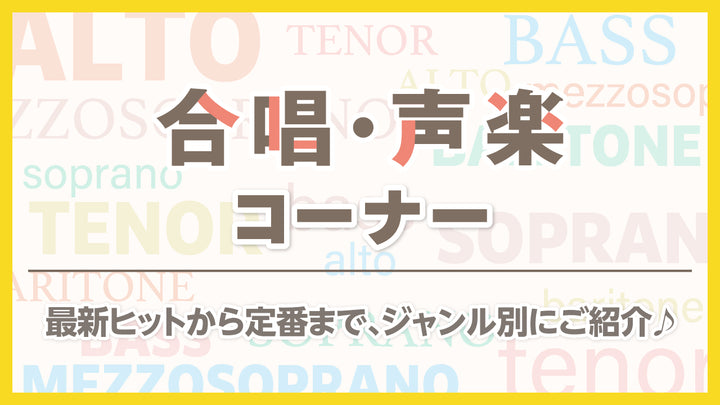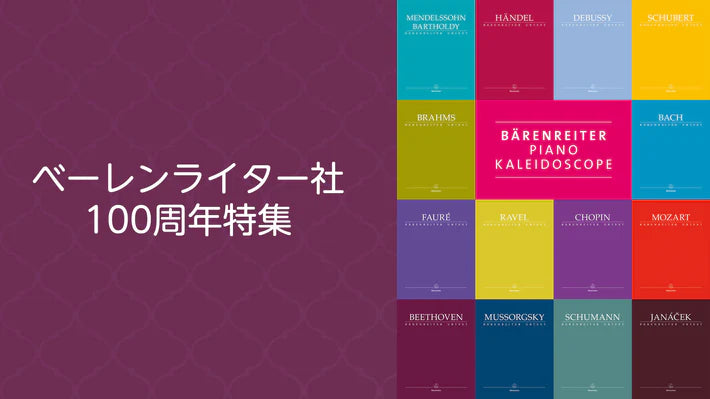あなたのご家族に、音楽をされている方がいるとしましょう。「〇〇が作曲した△△という曲の楽譜を買ってきて!」と、おつかいを頼まれて、ヤマハ銀座店のような大きな楽器店に足を運んでみると、きっと驚くはずです。多様な出版社から同じ楽曲の楽譜が出版されており、値段も内容も様々なのですから。きっと何も分からなければ、日本の出版社から発売している(輸入の経費がかかっていないために)比較的安価な楽譜を選んでしまいそうなところですが……。今回は何故、同じ楽曲の楽譜がたくさん出版されているのかという理由を、ドイツの音楽出版社 ベーレンライターを軸にして探っていきましょう!
楽譜が出版されるまで
最初におさえておくべき点は「楽譜」と一口にいっても、その形態は様々なのだということです。

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番
第1楽章の「自筆譜」
まず作曲者自身による手書きの譜面のことを「自筆譜 autograph」などと呼びます。自筆譜を「manuscript」と表記することも頻繁にありますが、これはより正確には「手稿譜」のことで、自筆譜だけでなく、手書きで別の人物が書き写した楽譜のことも含む場合があり、「holograph manuscript」と書くと自筆の手稿譜という意味になります。

J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲 第1番 第1曲〈前奏曲〉の「筆写譜」
バッハ自身の自筆譜が残されていないため、
このアンナ・マクダレーナ・バッハ(妻)の筆写譜が最重要な資料となる。
そして現在であれば、この自筆譜をコピー機にかけたり、スキャナーで取り込んだりしたり出来るわけですが、そうした技術が出来なかった時代はまず、手で書き写すのが基本でした。そうした譜面のことを「筆写譜 copy」と呼びます。「筆写師 copyist」を務めたのは、家族だったり、弟子だったり、筆写を仕事にしている職人であったりしました。

J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲 第1番 第1曲〈前奏曲〉の「初版譜」
バッハの死後、かなり経ってからパリで出版された楽譜。
このあとすぐにドイツなどでも出版されているようだ。
印刷による出版をしようという段階になると、作曲家の自筆譜(場合によっては丁寧に清書された筆写譜)をもとに「ゲラ刷り」が作られ、作曲者本人が存命中かつ出版に携わっている場合は直接、校正作業をおこないました。そうした過程を経て、最初に出版されたバージョンが「初版 first edition」となります。
こうして順番にみていくと、初版で作曲者自身がチェックしている楽譜なら、それだけあれば問題なさそうなものです。たとえ、その初版が古いために見づらかったり、絶版になってしまったりしたとしても、それを元に新しい楽譜を作ればいいだけなのでは……?

J.S.バッハ:管弦楽組曲第3番 第3曲〈エアー〉
(※いわゆる「G線上のアリア」)の「パート譜」
バッハの生前に、バッハの次男らによって書かれたもの。
……そう思いたいところなのですが、しかしながら現実はそんなに甘くはないのです。例えば、管弦楽曲や室内楽曲などの場合は、すべての楽器の音符が書かれた「総譜 score」と、楽器ごとに分かれた「パート譜 parts」が存在しますが、この総譜とパート譜で違いがあったり、さらに実際の演奏の場で使われたパート譜にだけ、作曲家がリハーサルで指示した変更点・修正点が書かれたりすることもあります。
売れ行きの良い人気楽曲の場合は権利を得て、他の出版社からも同じ楽曲の楽譜が出版されることがあり、時にそのタイミングで作曲者自身が改訂を加えることもあったのです。なので、どのタイミングの資料に作曲家の最終的な意思・判断が残されているのか、実に判断が難しく、意見が分かれてしまうのです。ここに様々な出版社から同じ楽曲の楽譜がだされる根本的な要因があります。
正しさとは何か?
様々な資料が残された楽譜のなかで、どれが最も“正しい”のか?……という問題意識に対しては、19世紀の初頭から「批判校訂版 critical edition」という形で、応えるようになります。ここでいう批判(クリティカル)とは「検討した結果をもとに評価する」ということ。つまりは残された資料を検討し、それがどのようなものであるか、ひとつひとつを評価していくのです。

J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲 第1番 第1曲〈前奏曲〉バッハ旧全集のバージョン
ですが、19世紀半ばから出版のはじまった「バッハ全集」(※現在でいうところの旧全集)では、自筆譜が残っている楽曲については、“無批判”で自筆譜だけをもとに出版譜をつくってしまいます(それが適切な判断ではないことは、ここまでの説明で理解できるはずですね!)。

J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲 第1番 第1曲〈前奏曲〉バッハ新全集のバージョン
(※2016年には「新バッハ全集,改訂版」も出版されている)
残された資料と網羅的に向き合うべきであるという考え方が広まったのは、ベーレンライター社から出版された「バッハ新全集」以降のことになります。1950年に新全集のプロジェクトが始まり、最終巻が出版されたのが2007年(!?)という60年近い大プロジェクトは、その後の音楽研究に多大な影響を与えました。
しかし、この全集さえも完璧なものとはいえず、一部の楽譜には多数の批判が寄せられています。その筆頭といえるのが、音楽学者フリートリヒ・スメントが「校訂 edit」をおこなった《ミサ曲 ロ短調》BWV 232です。スメントの主張は《ミサ曲 ロ短調》という完成された作品は存在しない(!?)という非常に過激なもの(そのくらいドラスティックに既存の考えをぶち壊そうとしていたことが窺えますが……)。楽譜の出版から5年後には、スメントの主張を真っ向から批判する論文が出されるなど、その問題性が長らく指摘されながら、あくまで新全集を完成させることが優先されてしまいます。

2007年の新全集完結後になってやっと、問題のある一部の作品については「新バッハ全集,改訂版」が出されることになり、2010年、遂に《ミサ曲 ロ短調》の新しい楽譜がベーレンライターから出版されました。この新しい版では、蛍光X線の技術を用いて、これまで読み取れなかった部分を解析するなど、50年前には不可能だった科学技術も活用することで、バッハの創作過程までもを明らかにしつつあるのです。
ベーレンライター社の掲げる「原典版」とは?
このように、ベーレンライター社は自らの過去に胡座をかくことなく、最新技術も投入することで、その時点で出来得る限りのことをおこない、その作品の作曲者の最終的な意図がどこにあるのかを探求しているのです。バッハ新全集で培われたこの方針は、他の作曲家の楽譜を出版する際にも徹底されており、「ベーレンライター原典版 Bärenreiter Urtext」というブランドは現在、クラシック音楽業界に広く周知されています。
ドイツ語「Urtext(ウアテクスト)」を英語に訳すと「original text」――つまり、伝統という手垢にまみれた楽譜を一から洗い直すことで、作曲者が意図したオリジナルに近づきたい。原典版には、そのような思いが込められているのです。
この方針は出版社に務める編集者だけで実現されるわけではなく、最終的な責任を受け持つ「校訂者 editor」として誰を起用するのかというという点が非常に重要になります。ベーレンライターの歴史を語る上で、1996年から出版されていったベートーヴェンの交響曲新全集にジョナサン・デル・マーを起用し、大成功を収めたことは事件だったといえるでしょう。
しっかりとしたバックグラウンドがあったとはいえ、本職は指揮者であり、著名なベートーヴェン研究者ではなかったデル・マーが校訂をおこなった楽譜に対し、当初こそ懐疑的な声があがったものの、彼が巻き起こした議論は音楽学者のみならず、指揮者にも刺激を与えることで、21世紀のベートーヴェン像に巨大な影響を及ぼすまでになりました。

例えば、日本でお馴染みの第九(ベートーヴェン:交響曲第9番《合唱付き》)の総譜を作成するために、デル・マーは15種類の楽譜にあたりつつ、これまでは自筆譜の誤りとされて、出版の際に直されていた部分にも正当性があると主張することで、それまで多くの演奏家が使用していた19世紀に作られたバージョンに疑問を呈することに成功。ここまで語ってきたような問題を、それまで意識してこなかった演奏家やリスナー(!)に興味をもたせたのです。

デル・マーは現在、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集などの編集を継続していますが、すべてのベートーヴェン作品をデル・マーひとりで校訂しているわけではありません。例えば、まもなく出版予定の《ディアベリ変奏曲》では、マリオ・アシャウアがその責を担っています。彼は博士号を取得した研究者でありつつ、ピアノ奏者、チェンバロ奏者としても自身の研究成果をもとに演奏活動をおこなうフロントランナー。その分野の大御所ではなく、今まさに最先端で走っている人物を起用するという方針は、ベーレンライター社にしっかりと根づいていることがお分かりいただけるでしょう。
(本記事は、2019年11月に執筆した記事を再掲載しています。)
Text:小室敬幸
プロフィール

小室 敬幸
音楽ライター/大学教員/ラジオDJ
東京音楽大学と大学院で作曲と音楽学を学ぶ(研究テーマはマイルス・デイヴィス)。現在は音楽ライターとして曲目解説(都響、N響、新日本フィル等)や、アーティストのインタビュー記事(レコード芸術、intoxicate等)を執筆する他、和洋女子大学で非常勤講師、東京音楽大学 ACT Projectのアドバイザー、インターネットラジオOTTAVAでラジオDJ(月曜18時から4時間生放送)、カルチャースクールの講師などを務めている。
X(旧Twitter): https://x.com/TakayukiKomuro
この記事を読んだ方におすすめの特集