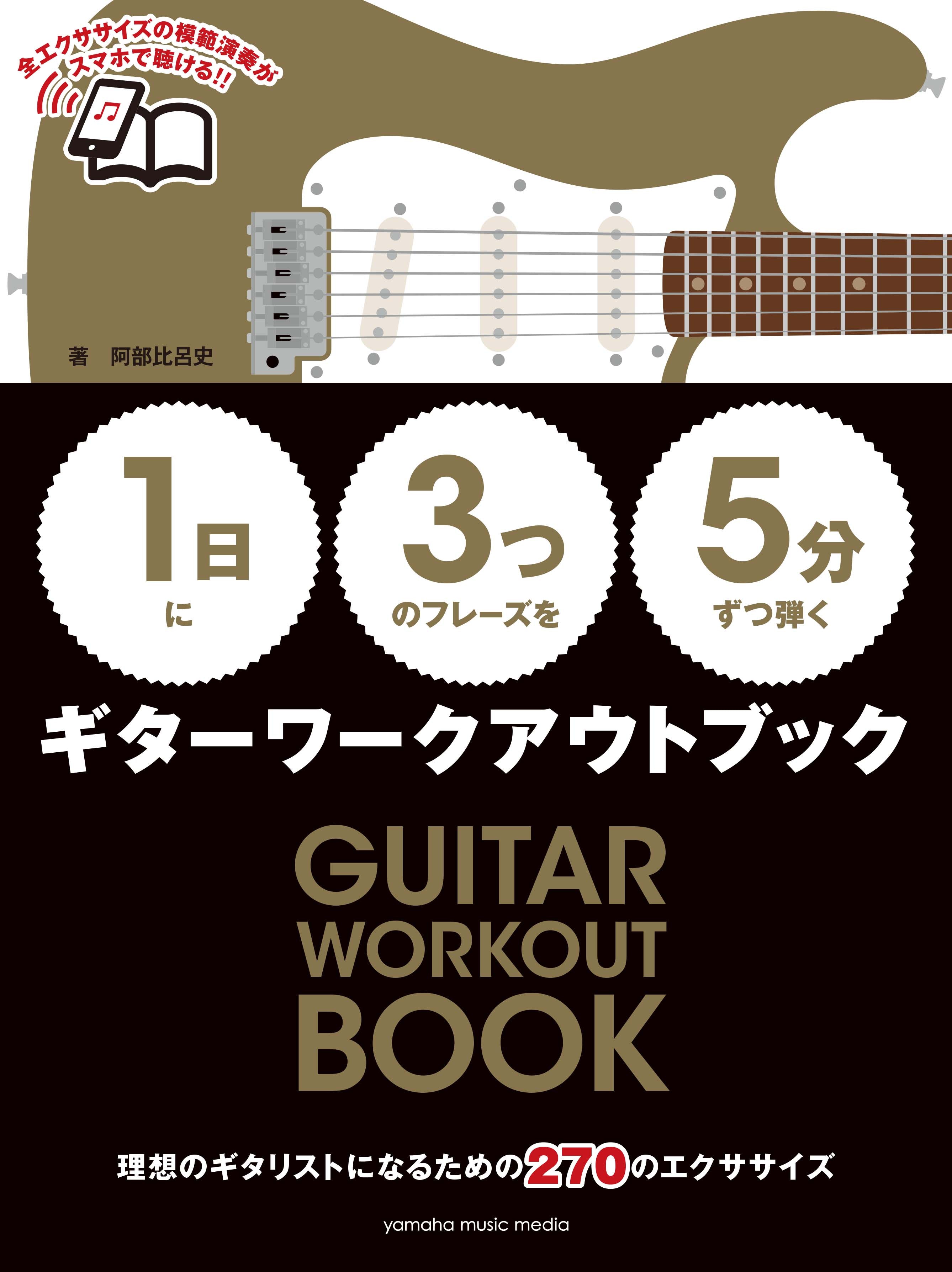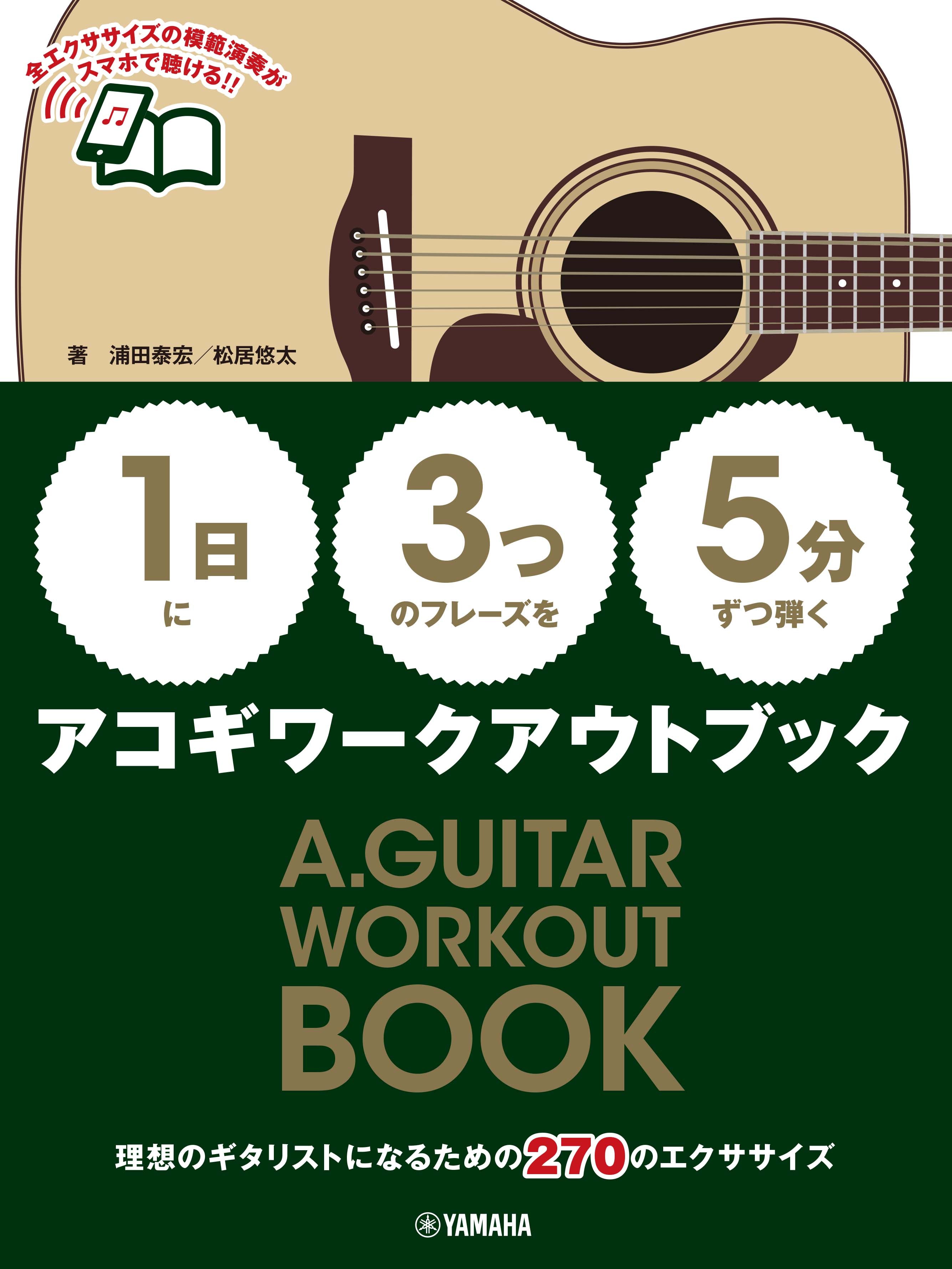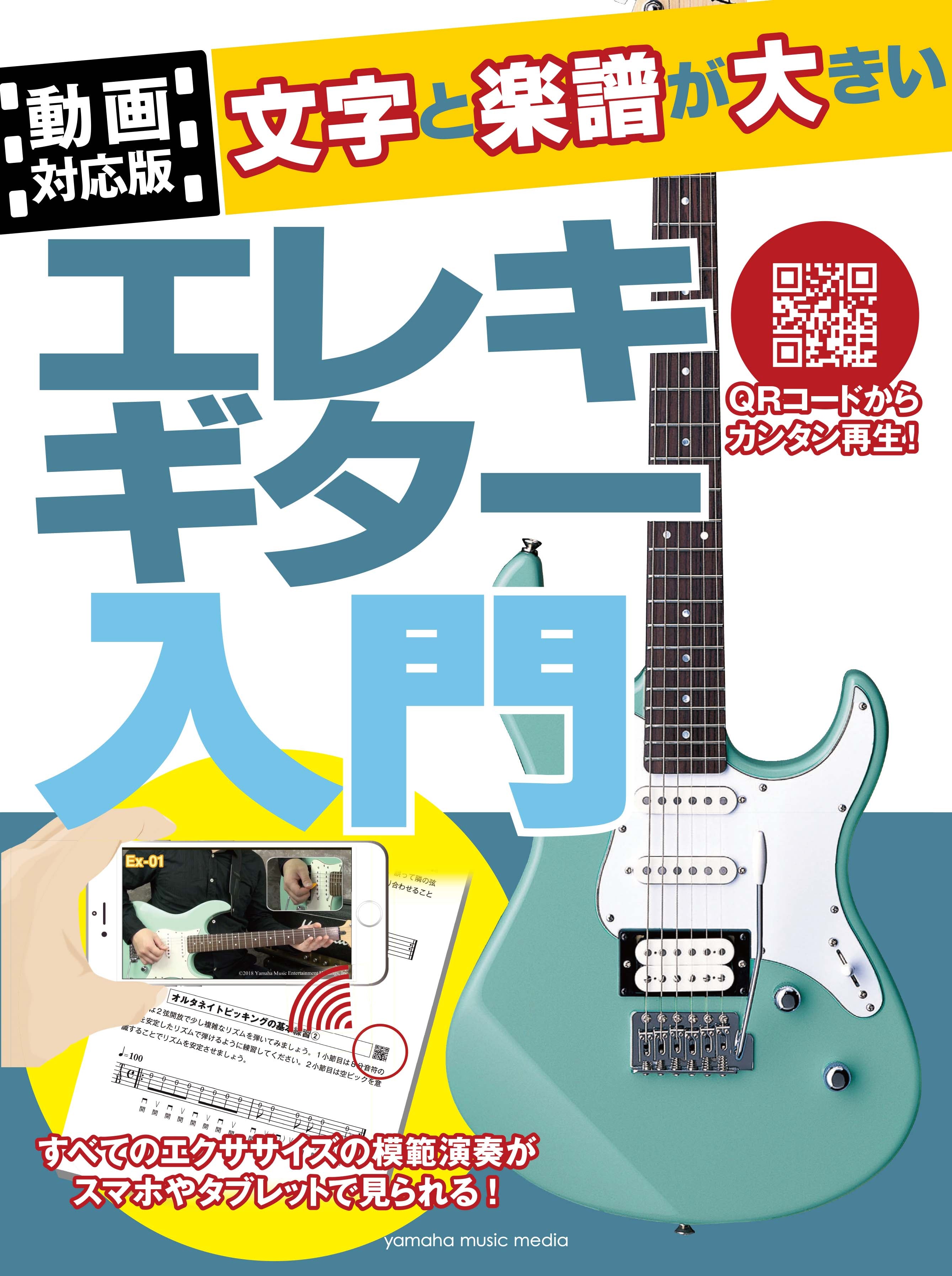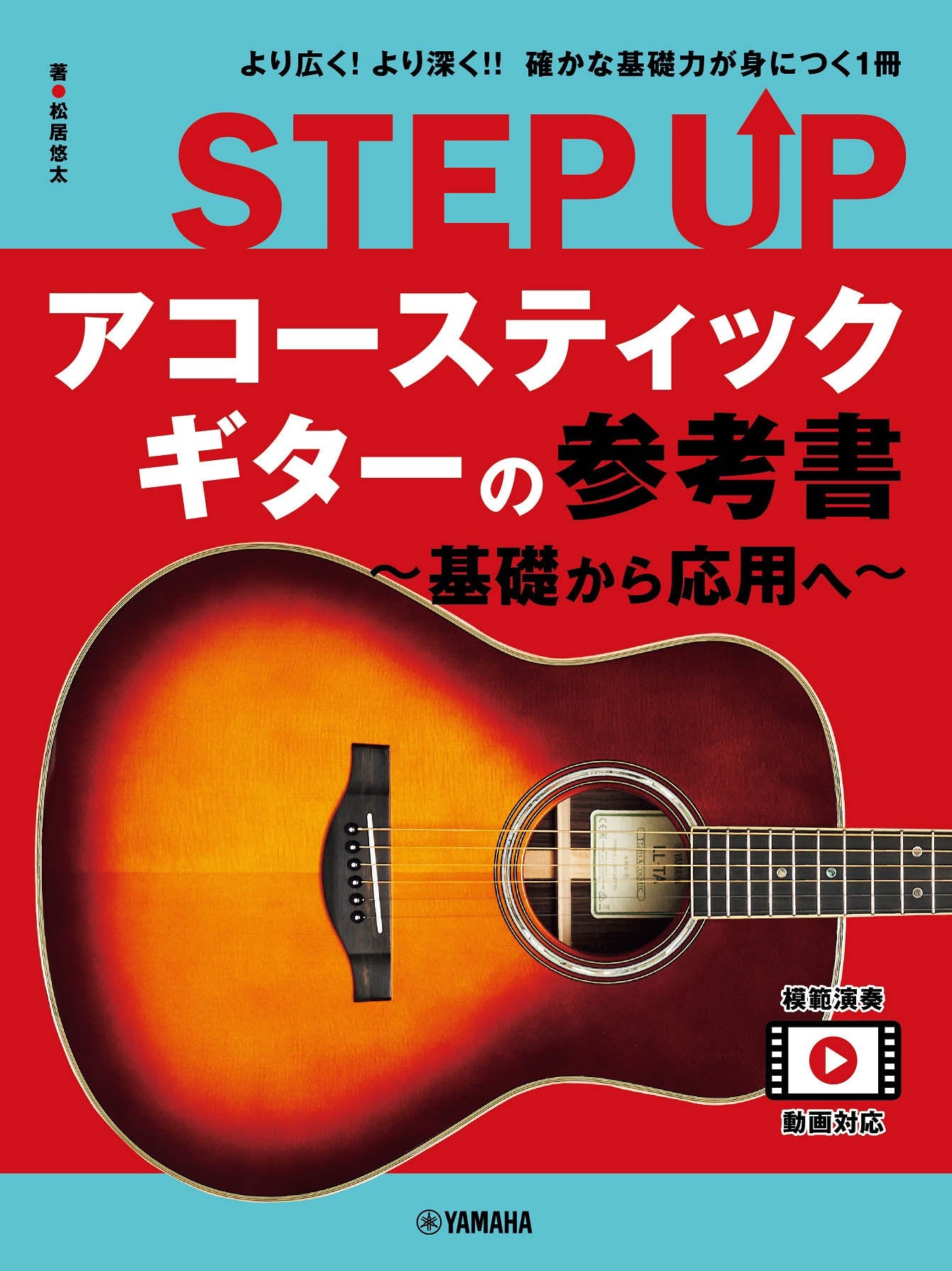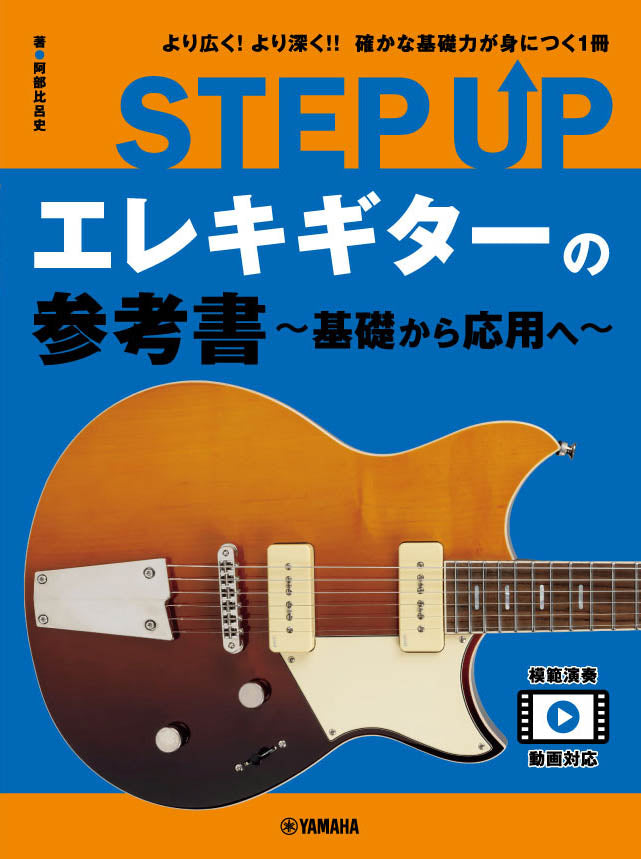1人でギターの練習をしていると、知らぬ間に間違ったやり方をしているなんてことがある。言葉は知っていても、実際にどうやるか分からなくて、「変なクセがついちゃった!」な~んて結果にもなりかねない。方向を間違うことはあっても努力だけは怠らないザセツ君と、ギター奏法の基礎を一緒に学んでいこう!

【プロフィール】
左:ザセツ君 (本名: 財園寺せつ夫)
近所の幼稚園の節分イベントに鬼役でお手伝い。鬼のお面は得意の工作でかなりのクオリティ(≧▽≦)! この格好でディストーションギターを弾いたら、ちびっ子たち驚くだろうなぁΨ(`∀´)Ψ
右:ジミ先生
物理の先生で科学部の顧問。エフェクター作りが趣味で、エレキのことはこの人に訊け!と評判。老けてみられるが実は27歳。日サロ通いが欠かせない。
解説/竹内一弘 マンガ/ Dobby.



歪み系のエフェクターにはいくつかのタイプがある。ジャンルごとにも適した歪み方があり、個人の好みも関わってくるので、基礎知識として歪み系エフェクターの種類を把握しよう(図1)。
まずはファズ。これは猛烈に歪むタイプで、ピッキングの強弱はほとんど感じられなくなるほど。あまりにも強烈な歪みなので1曲を通して使うことはあまりなく、ソロやイントロなどワンポイントでの使用が多い。
ディストーションはハードロックやヘヴィメタルで好まれる強めの歪みが特徴で、歪み系の基本エフェクターともいえる。
オーバードライブは、チューブ(真空管)アンプの歪み方をモデルにしたもので、クランチ程度の軽めの歪みを得意とする。ブルースなどピッキングのニュアンスを重視するギタリストに好まれるタイプだ。
ブースターは単体ではあまり歪まないものが多いのだが、名前の通り、このエフェクターでギターからの信号を増幅してチューブアンプに入れることで、アンプ自体をドライブさせて歪みを得るものだ。ナチュラルな歪み方を重視するギタリストが好んで使う。


ディストーション系のほかにも色々なエフェクターがあり、それらを接続する順番は大体決まっているので、自分の持っているエフェクターがどの系列に入るのかを把握して、エフェクターを接続してみよう(図2)。
あくまでこれは一例であり、接続順を変えたからといって音がおかしくなるわけではないし、あえて定番の接続順を崩すことで面白い効果が得られることもある。まずはこの接続順で試してみよう。


ハードロックなどでは歪みとクリーンな音色を切り替えるのが基本。このスタイルは、アンプはクリーントーンが出る状態にしてエフェクターだけで歪みを作るようにすると、エフェクターのオン/オフだけで音色を切り替えられる(図3)。


基本的な考え方はディストーション系と同じだが、ここではチューブアンプとオーバードライブの組み合わせについて紹介しよう。
歪み系エフェクターは、チューブアンプのボリュームを上げたときに生じるプリアンプ部分の歪みをシミュレートすることからはじまった。つまり、チューブアンプはそれ単体で歪むのだ。そして、アンプを軽く歪ませた状態でも、ギターのボリュームを下げるとクリーントーンになるという特徴がある。歪み系エフェクターがなくてもすでに2種類のトーンが出せるわけ。そこにオーバードライブを加えると、強い歪み、軽い歪み、クリーントーンが出せる。
この3種類のトーンそれぞれに対し、ギターのボリューム操作やピッキングの強弱でさらに音色を変えるというのがチューブアンプとオーバードライブの典型的な使い方になる。Ex-1で歪み具合をチェックしてみよう。
チューブアンプに対し、プリアンプ部が歪まないトランジスタアンプというものがある。ローランドのJCシリーズがその代表で、透明感のあるクリーントーンに向いている。アンプ単体で歪みを作ることができるものもあるが、それはアンプの中にディストーション系エフェクターが入っているからだ。



リハスタなどに2チャンネルを持つチューブアンプがあれば、かなり幅広いディストーション系の音作りが可能だ。2チャンネルとは、アンプのプリアンプ部が2個あることで、チャンネル1でクリーントーン、チャンネル2でディストーションを作り、付属のフットペダルで切り替えればお手軽に2音色を使い分けられる。さらにディストーション系エフェクターを加えれば、バンドで必要な歪みはこのシンプルなセッティングだけで充分にまかなえるだろう(図5)。
ちなみに、チューブアンプの見分け方だけど、アンプの裏側にガラス製の筒のようなもの(それが真空管)があるので簡単にわかる(図6)。それから、アンプの電源を入れた状態で真空管を素手で触るとヤケドするので注意!


(Go!Go! GUITAR 2015年3月号に掲載した内容を再編集したものです)
Edit:溝口元海
この記事を読んだ人におすすめの商品